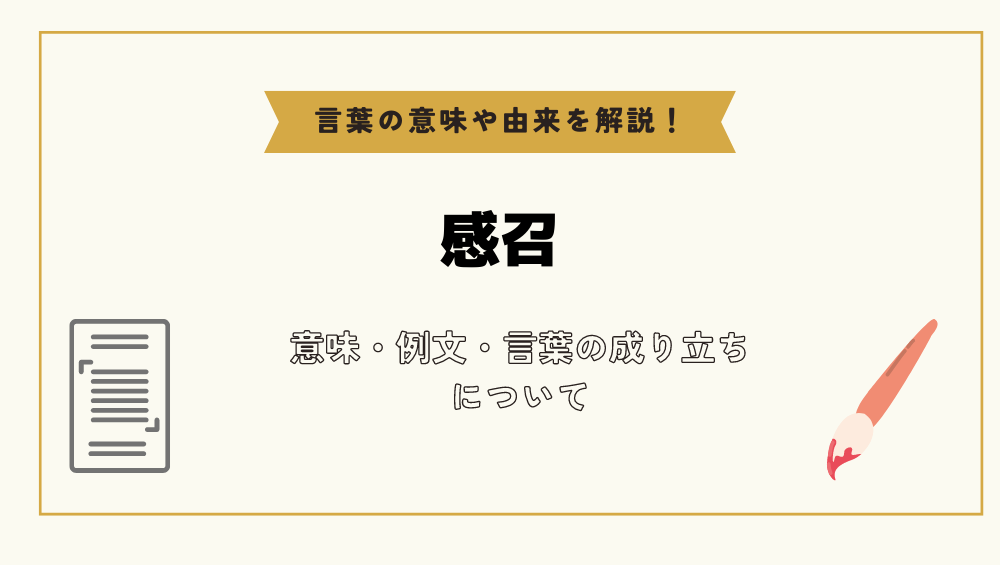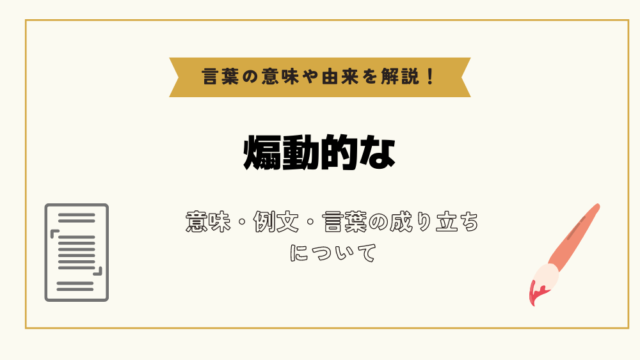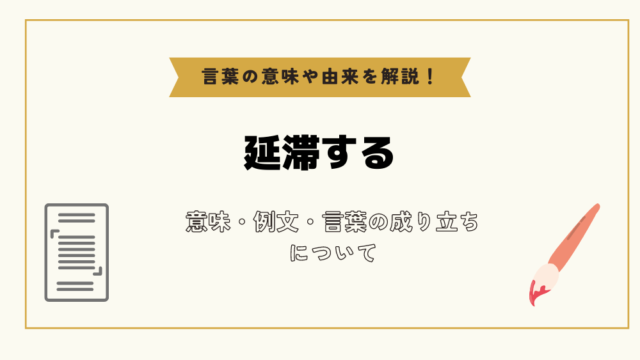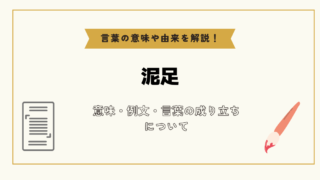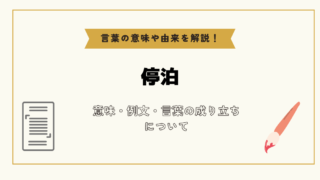Contents
「感召」という言葉の意味を解説!
「感召」という言葉は、他人や環境の影響を受けて動かされることを表す言葉です。
自分の心や身体が何かしらの影響を受けて変化することを指します。
この言葉には、何かしらの力や影響を受けて感じる、受け止めるという意味合いが含まれています。
「感召」は、外部からの刺激や影響を受けて、その影響を受け入れることを意味する言葉です。
。
「感召」の読み方はなんと読む?
「感召」という言葉は、「かんしょう」と読みます。
この読み方は慣用的で、日本語の発音に従ったものです。
日常的に使われることは少ない言葉ですが、文章や文学作品などで見かけることがあります。
「感召」という言葉は、「かんしょう」という読み方が一般的です。
。
「感召」という言葉の使い方や例文を解説!
「感召」という言葉は、主に文学作品や専門的な文書で使用されることが多いです。
例えば、「彼の言葉には何か特別な力があって、心に感召されるような気持ちになる」という使い方があります。
このように、「感召」は言葉や情報、状況などによって心や感情が影響を受ける様子を表現する際に使われます。
「感召」という言葉の成り立ちや由来について解説
「感召」という言葉は、中国語由来の日本語です。
中国語の「感召」という言葉が転じて、日本語でも同じ意味で使用されるようになりました。
日本語では、外来語や外国語からの借用語が多く使われていますが、「感召」という言葉もその1つです。
「感召」という言葉は中国語由来の日本語であり、外来語の1つです。
。
「感召」という言葉の歴史
「感召」という言葉は、古くから日本語に存在していた言葉のひとつです。
日本の文学や詩歌、仏教などの宗教文化においても、多く使われてきました。
古典文学や歴史書にも、「感召」という言葉の使用例が見られ、その意味合いや使い方が時代と共に変化していったことがわかります。
「感召」という言葉は、古くから日本語に存在し、文学や歴史書に多く使われてきた歴史があります。
。
「感召」という言葉についてまとめ
「感召」という言葉は、他人や環境の影響を受けて動かされることを表す言葉です。
外部からの刺激や情報によって心や感情が変化する様子を表現する際に使われます。
日本語の古典文学や歴史書においてもよく見られる言葉であり、日常会話ではあまり使われることがない言葉です。
「感召」という言葉は、他者や環境からの影響を受けて心が動かされる様子を表現する言葉です。
。