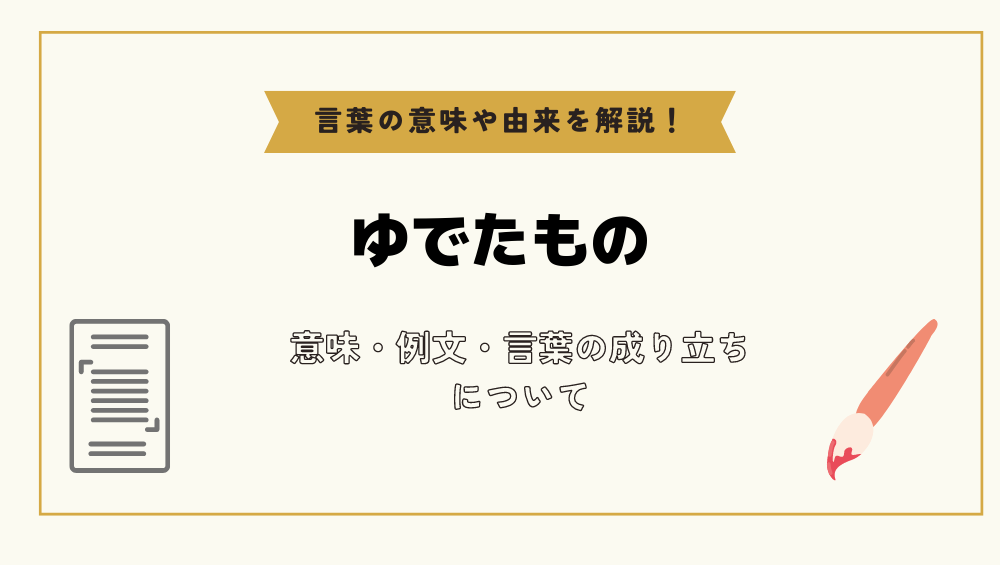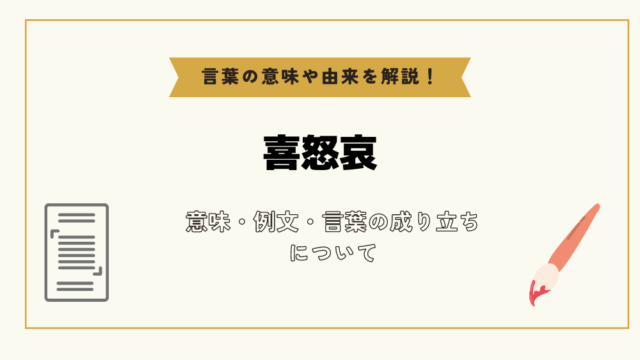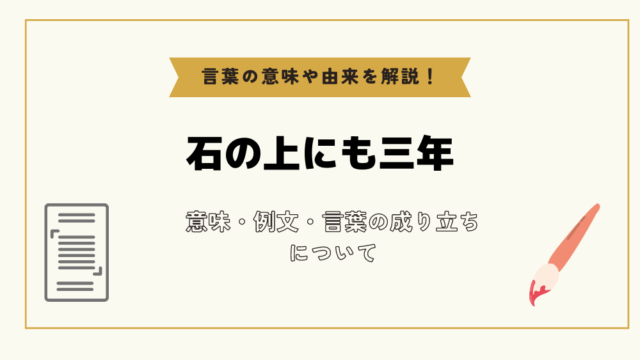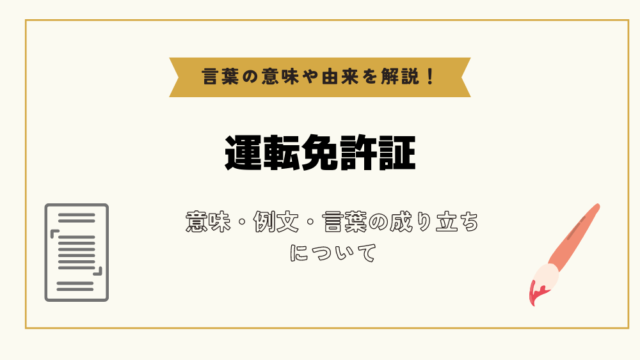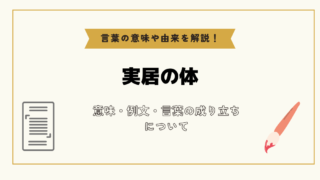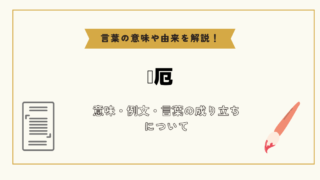Contents
「ゆでたもの」という言葉の意味を解説!
「ゆでたもの」という言葉は、お湯や湯気を使って調理した料理や食材を指します。
主に野菜や魚、肉などの食材がゆでられることが多いです。
ゆでた食材は、調理しやすく、体にやさしい栄養価が豊富な一品です。
ゆでたものは、日本の伝統的な調理法の1つであり、身体に優しい食事として注目されています。
。
「ゆでたもの」の読み方はなんと読む?
「ゆでたもの」は、読み方は「ゆでたもの」です。
日本語の基本的な読み方に従った言葉であり、誰でもすぐに理解できる読み方です。
ゆでたものを食べるときは、ぜひその美味しさと栄養価を楽しんでください。
「ゆでたもの」という言葉の読み方は、そのまま「ゆでたもの」と読みます。
。
「ゆでたもの」という言葉の使い方や例文を解説!
「ゆでたもの」は、日常の食事や料理の中でよく使われる言葉です。
例えば、「今日の夕食は、ゆでた野菜と白身魚のメニューです。
」と使うことができます。
料理の中でゆでたものを使うことで、体にやさしい食事を摂ることができます。
「ゆでたもの」は、料理のバリエーションを豊富にし、健康的な食生活をサポートします。
。
「ゆでたもの」という言葉の成り立ちや由来について解説
「ゆでたもの」という言葉は、元々は古代から伝わる日本の伝統的な調理法に由来します。
お湯を使って調理する方法は、栄養価を保ちつつ、食材の味を引き立てる効果があります。
このような調理法が日本の食文化に根付いていると言われています。
「ゆでたもの」という言葉の由来は日本の古来からの調理法にあり、美味しさと栄養価を兼ね備えています。
。
「ゆでたもの」という言葉の歴史
「ゆでたもの」の歴史は、日本の古代からさかのぼることができます。
古代の日本人は、野菜や魚をお湯でゆでて食べることで、生活の中で栄養バランスを保ちながら健康を守ってきました。
現代でも、ゆでたものは健康的な食事として重要な位置を占めています。
古代から今日に至るまで、日本の食文化における「ゆでたもの」は健康を守る食事として愛され続けています。
。
「ゆでたもの」という言葉についてまとめ
「ゆでたもの」という言葉は、日本の伝統的な料理法や食文化に根付いている言葉であり、健康的な食事として重要な存在です。
野菜や魚、肉などの食材をお湯でゆでることで、栄養価を保ちながら調理することができます。
食事のバリエーションを豊かにし、健康維持に役立つ「ゆでたもの」を積極的に取り入れてみてください。
「ゆでたもの」は日本の伝統と健康を象徴する食事方法であり、食卓に欠かせない存在です。
。