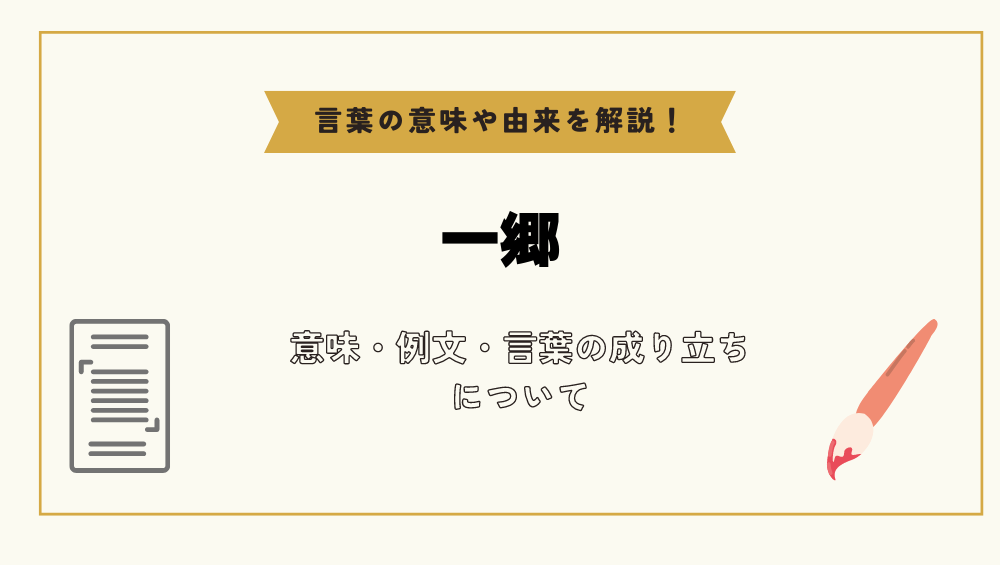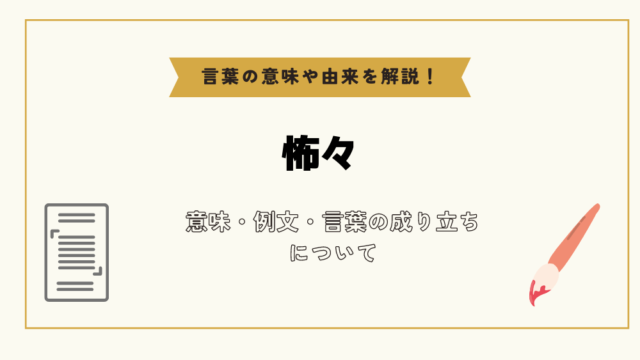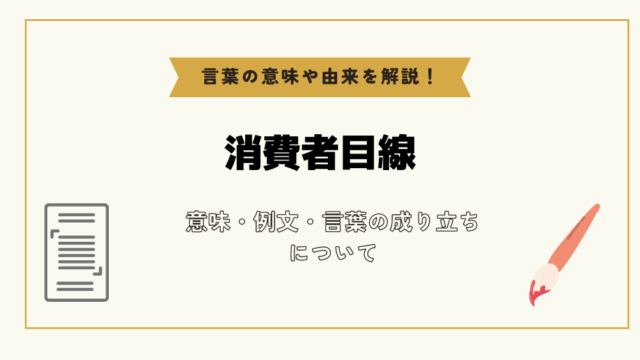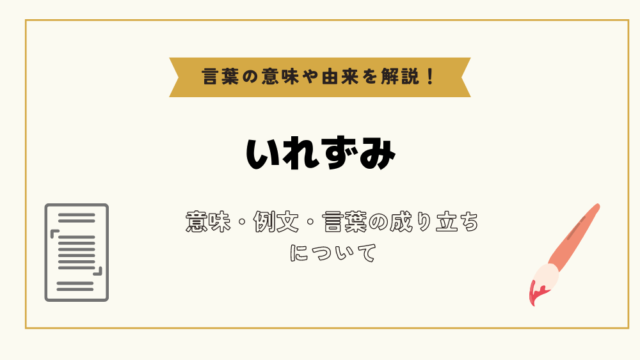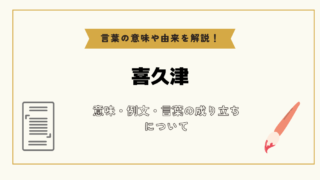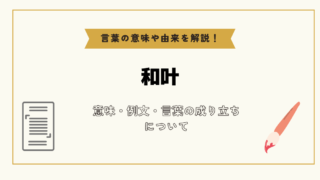Contents
「一郷」という言葉の意味を解説!
「一郷」とは、一つの地域や地域社会のことを指す言葉です。私たちはそれぞれが異なる場所や環境に生きていますが、その中で共通のルーツやつながりを持つ地域社会を指すときに使用されます。
一郷は、地域ごとの文化や風土、伝統などが詰まった大切な概念であり、地域の誇りやアイデンティティを表現する言葉でもあります。
「一郷」の読み方はなんと読む?
「一郷」は、「いっきょう」と読みます。この読み方は、一つの地域や集落が一つのまとまりとして捉えられていることを表しています。
一郷は、地域の一体感や一体性を強調する言葉として用いられており、地域の連帯感や結びつきを表現する際に使用されます。
「一郷」という言葉の使い方や例文を解説!
「一郷」は、例えば「私たちは一つの一郷として協力し合い、地域の課題に取り組んでいます。」のように使われます。このように、「一郷」は地域社会全体を表す言葉として使われます。
地域の住民が一つのまとまりとして協力し合い、地域の発展や活性化に取り組む様子を表現する際には、「一郷」という言葉が適しています。
「一郷」という言葉の成り立ちや由来について解説
「一郷」という言葉は、元々は地方の小さな集落や地域を指す言葉として使用されていました。その後、地域社会全体の結束や一体感を表すために広く用いられるようになりました。
「一郷」という言葉の成り立ちは、地域の人々が共に生活し、協力し合う中で生まれた言葉であり、地域社会の絆やつながりを表す重要な概念となっています。
「一郷」という言葉の歴史
「一郷」という言葉は、古くから地域社会の一体性や連帯感を表すために使われてきました。日本の伝統文化や歴史の中で、地域の人々が共に暮らし、助け合う姿が「一郷」の精神を表しています。
地域の繁栄や発展に寄与するために一体となって努力する姿勢が、「一郷」の精神として受け継がれてきました。
「一郷」という言葉についてまとめ
「一郷」という言葉は、地域社会全体の一体性や結束を表す大切な概念です。地域の住民が共に協力し合い、地域の課題に取り組む姿勢が、「一郷」という言葉に表れています。
地域社会の一体感や共同体の結びつきを大切にし、地域の活性化や発展に貢献するために、「一郷」の精神を大切にしていきましょう。