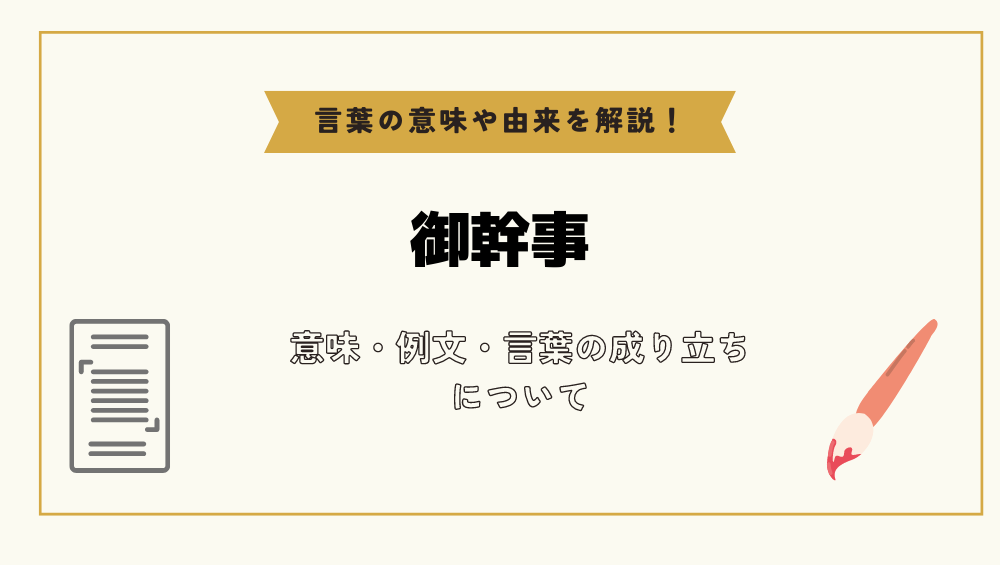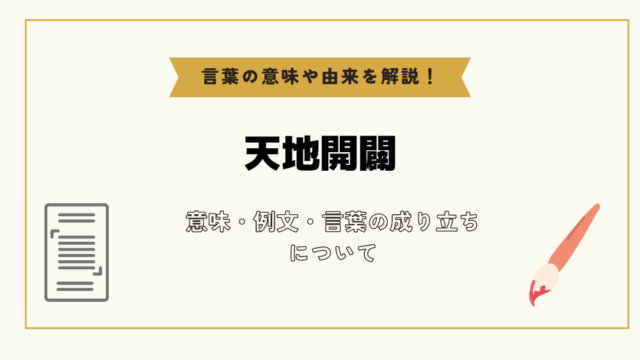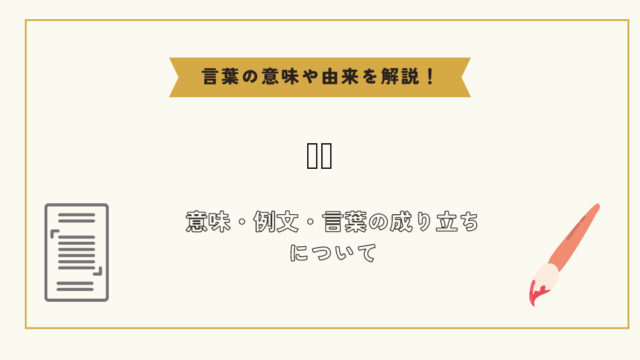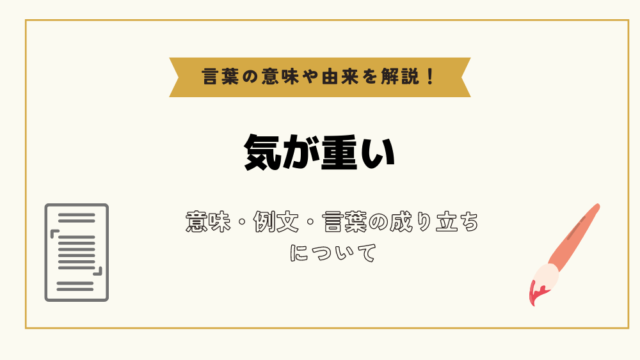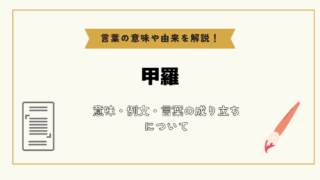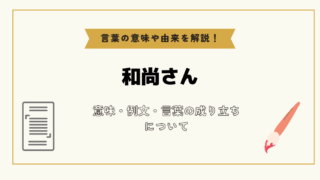Contents
「御幹事」という言葉の意味を解説!
「御幹事」とは、特定の行事やイベントで、その準備や進行を取りまとめる責任者のことを指します。
主催者や企画者から、異なるお役目を担当する方に対して使われることが多い言葉です。
「御幹事」という言葉は、行事やイベントを成功させるために欠かせない重要なポジションを指す言葉として活用されています。
。
「御幹事」の読み方はなんと読む?
「御幹事」の読み方は、「おかんじ」と読みます。
この読み方は、丁寧な言い方で幹事を表す言葉に「お」をつけています。
「御幹事」という言葉は、敬意を表する言葉として、「お」という接頭語をつけて呼ばれることが一般的です。
。
「御幹事」という言葉の使い方や例文を解説!
「御幹事」という言葉は、主にお世話になりたい方や依頼したい方に使われます。
例えば、結婚式やパーティーなどのイベントで、幹事をお願いする際に使われることが多いです。
「御幹事、よろしくお願いいたします」という言葉は、イベントを成功させるために重要なお願いをする際に使われる一例です。
。
「御幹事」という言葉の成り立ちや由来について解説
「御幹事」という言葉は、江戸時代に起源を持ち、当時の律令制度に由来しています。
律令制度では、宴席のために幹事を任命し、席次や進行を取り仕切らせることが行われていました。
「御幹事」という言葉は、古くから行事やイベントでの司会や進行を担当する責任者を表す言葉として用いられています。
。
「御幹事」という言葉の歴史
「御幹事」という言葉は、日本の歴史の中で古くから使われてきました。
律令制度や武家社会、さらに現代でも行事やイベントでの幹事を指す言葉として広く認知されています。
「御幹事」という言葉は、歴史を通じて日本のイベントや行事において重要な役割を果たしてきたことを物語っています。
。
「御幹事」という言葉についてまとめ
「御幹事」という言葉は、行事やイベントでの進行や準備を取りまとめる責任者を指す言葉です。
異なるお役目を担当する方に与えられることが多く、その重要性を示す言葉として一般的に使われています。
「御幹事」という言葉は、行事やイベントの成功に欠かせない重要なポジションを表す言葉として、日本の文化や歴史の中で根付いています。
。