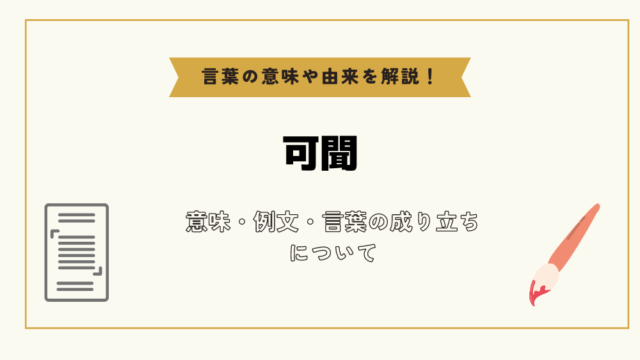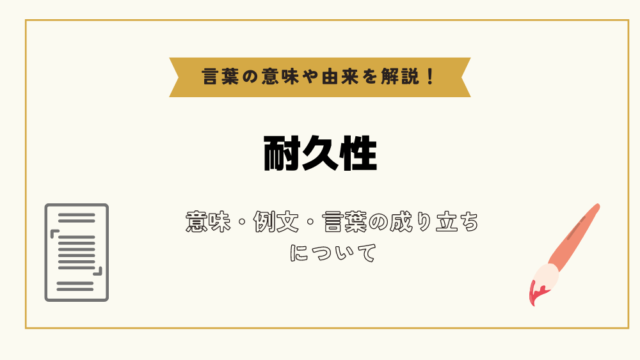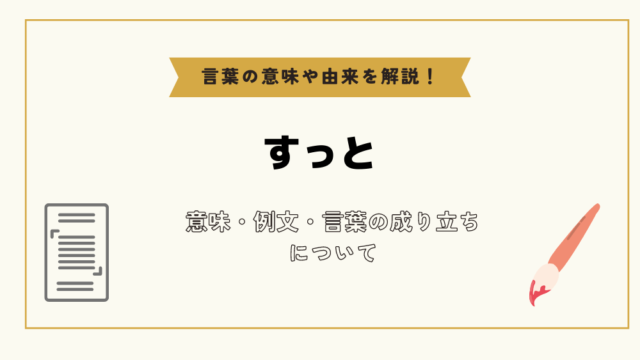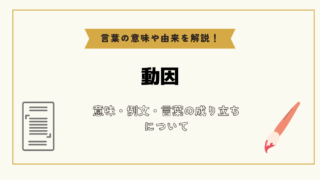Contents
「参勤交代」という言葉の意味を解説!
「参勤交代」とは、江戸時代において大名や幕府の役人が、一定の期間ごとに居城と本城を往復しながら勤務した制度のことを指します。
これは、大名や役人が地方と都市を行き来することで、政権の統治や情報の収集を効率よく行うために行われたものでした。
「参勤交代」の読み方はなんと読む?
「参勤交代」は、日本語の読み方としては「さんきんこうたい」と読みます。
この言葉は、江戸時代における特定の制度を指す際に用いられることが一般的です。
「参勤交代」という言葉の使い方や例文を解説!
「参勤交代」という言葉は、主に歴史や文学の分野で使用されることが多いです。
例えば、「大名が毎年のように参勤交代を行う様子が描かれた物語」などと使われることがあります。
「参勤交代」という言葉の成り立ちや由来について解説
「参勤交代」の成り立ちや由来は、江戸時代の政治や社会の状況に根ざしています。
大名や役人が領地に赴くことで、統治や情報収集を行うため、この制度が生まれたと言われています。
「参勤交代」という言葉の歴史
「参勤交代」の制度は江戸時代に定着し、幕府や諸大名によって実施されていました。
この制度は、大名たちが領地と都市を行き来することで、政権の運営や情報の収集を効率的に行うことができたとされています。
「参勤交代」という言葉についてまとめ
「参勤交代」とは、江戸時代において大名や役人が領地と都市を往復しながら勤務する制度であり、政権の運営や情報収集に重要な役割を果たしていました。
この制度は日本の歴史や文化において、重要な位置を占めていると言えます。