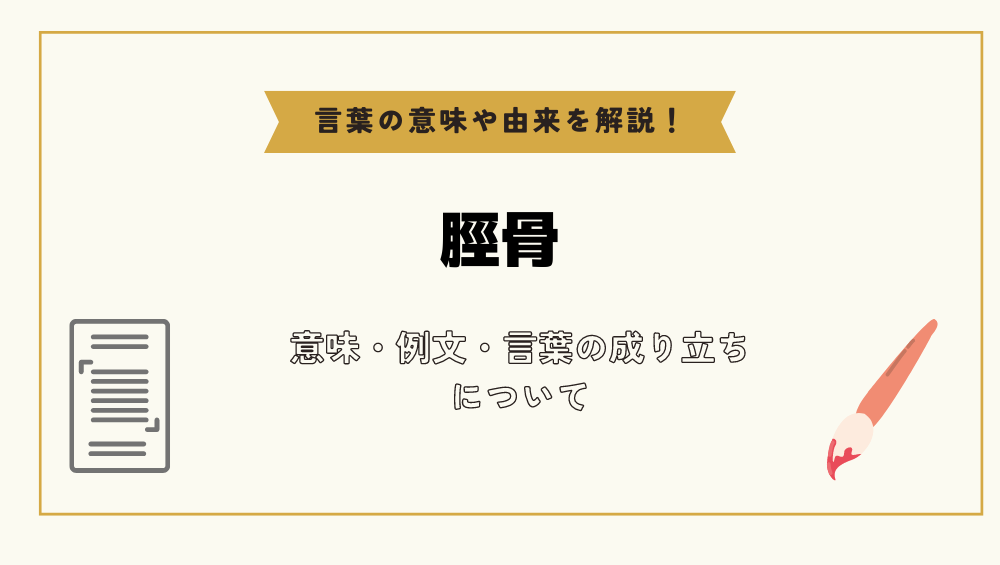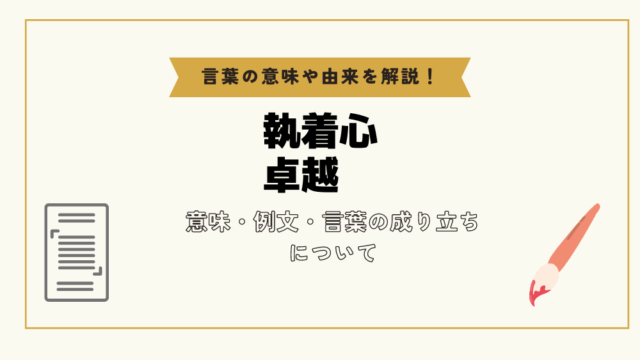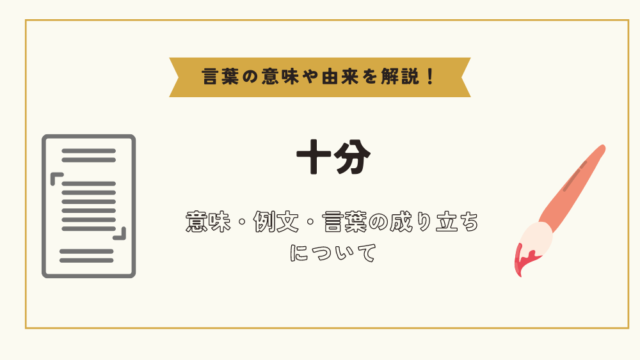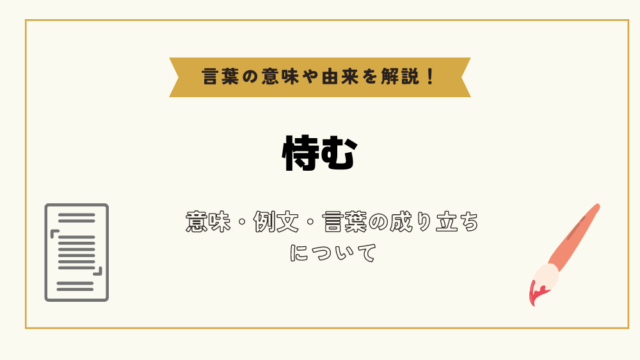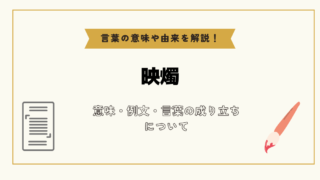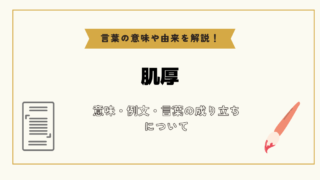Contents
「脛骨」という言葉の意味を解説!
脛骨(けいこつ)とは、人体の下肢にある骨の一つで、膝から足首にかけて位置しています。
四肢の中でも特に力を受ける部分で、歩行や走行などの運動時に重要な役割を果たしています。
脛骨はふくらはぎとしても知られ、主に下腿部を形成する骨として知られています。
。
「脛骨」の読み方はなんと読む?
「脛骨」という言葉は、「けいこつ」と読みます。
日本語での読み方になりますが、医学や解剖学などの専門用語としても使用されています。
「脛骨」という言葉の使い方や例文を解説!
「脛骨」は、主に解剖学や医学の分野で使用される言葉ですが、日常会話で使用されることは少ないです。
例えば、「脛骨の構造にはどのような特徴があるか?」など、専門的な文脈で使用されます。
「脛骨」という言葉の成り立ちや由来について解説
「脛骨」という言葉の成立や由来については、古代ギリシャ語やラテン語に由来することが知られています。
具体的な語源は諸説ありますが、折れやすい部位である脚の骨を指す言葉として定着したと考えられています。
「脛骨」という言葉の歴史
「脛骨」という言葉は古代医学から現代医学まで、長い歴史を持つ言葉の一つです。
古代ギリシャやローマ時代から、人体の骨組織を調査し、脛骨などの骨の名称や構造について研究が行われてきました。
「脛骨」という言葉についてまとめ
脛骨は、人体の下肢に位置する重要な骨の一つであり、歩行や走行などの運動時に不可欠な役割を果たしています。
専門用語として使用されることが多い「脛骨」という言葉には、古代ギリシャやラテン語などの歴史的な要素も含まれており、その由来や成立にも興味深い点が多く語られています。