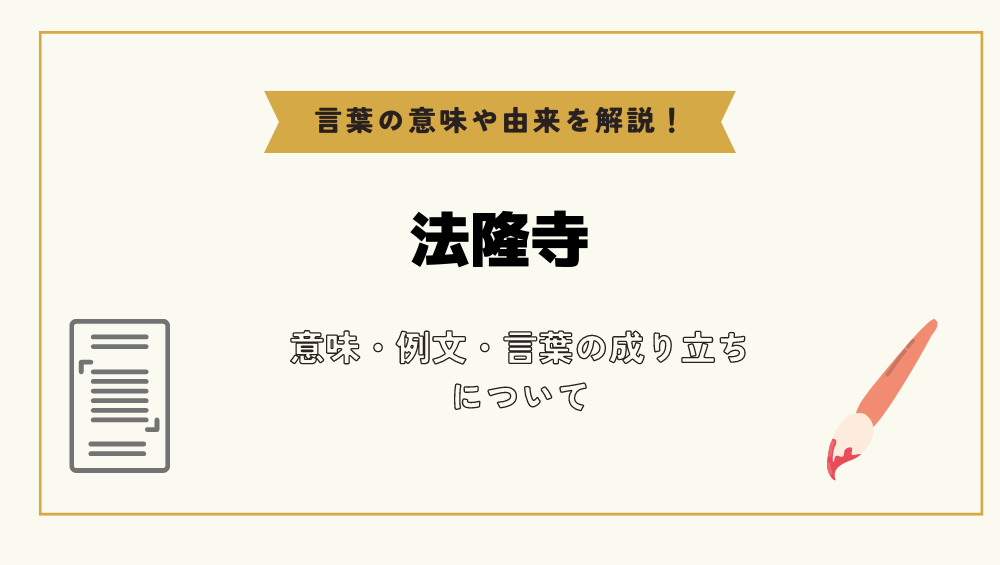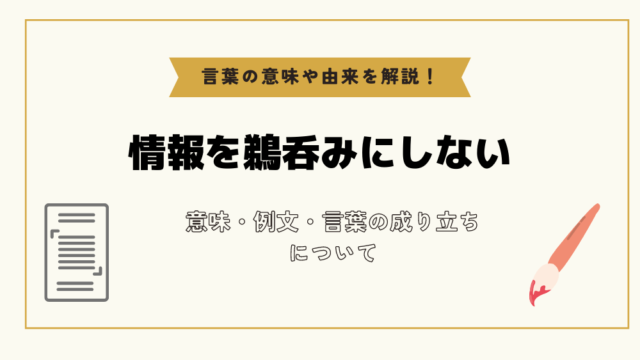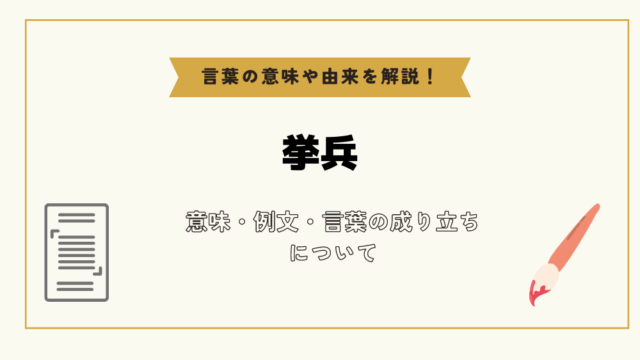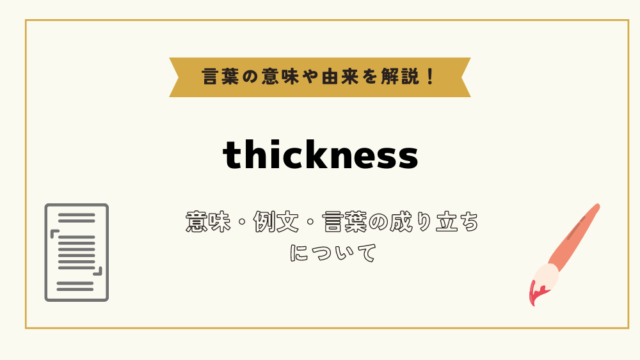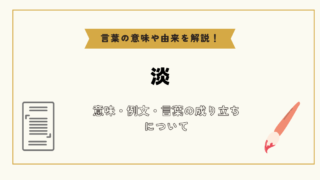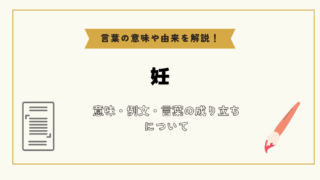Contents
「法隆寺」という言葉の意味を解説!
「法隆寺」という言葉は古代日本の仏教寺院の名称です。この寺は、奈良県にある日本最古の仏教寺院であり、世界遺産にも登録されています。その名前の由来は、仏教の教えを広めるために建てられたとされています。そして寺院内には多くの重要な文化財や美しい景観が存在し、多くの観光客に愛されています。
「法隆寺」の読み方はなんと読む?
「法隆寺」は、ほうりゅうじと読みます。古代から伝わる言葉のため、その響きには歴史や威厳を感じます。日本の仏教文化を代表する寺院として知られているため、その名前だけでも多くの人々に感動を与える言葉となっています。
「法隆寺」という言葉の使い方や例文を解説!
「法隆寺」を使った例文をご紹介します。例えば、「法隆寺は日本の代表的な仏教寺院の一つです。」や「法隆寺の美しい庭園を訪れたことがありますか?」など、日常会話や文章中でも頻繁に使用される言葉です。
「法隆寺」という言葉の成り立ちや由来について解説
「法隆寺」という言葉の成り立ちは、仏教の教えを広めようという意志から生まれました。この寺院は聖武天皇によって建立され、聖徳太子によって法隆寺の寺域が寄進されたことでも知られています。その由来や歴史には多くの教訓が詰まっており、多くの人々に愛され続けています。
「法隆寺」という言葉の歴史
「法隆寺」という寺院は、奈良時代の7世紀に建立されました。その後も修復や増改築が繰り返され、現在に至るまで多くの歴史的建造物や仏像が残されています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし続けており、多くの人々に敬愛されています。
「法隆寺」という言葉についてまとめ
「法隆寺」という言葉は、日本の仏教寺院の名称として知られています。その由来や歴史、文化的意義など、さまざまな側面から見ることができる言葉です。多くの人々に愛され続ける「法隆寺」は、日本の誇るべき文化遺産の一つとして、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。