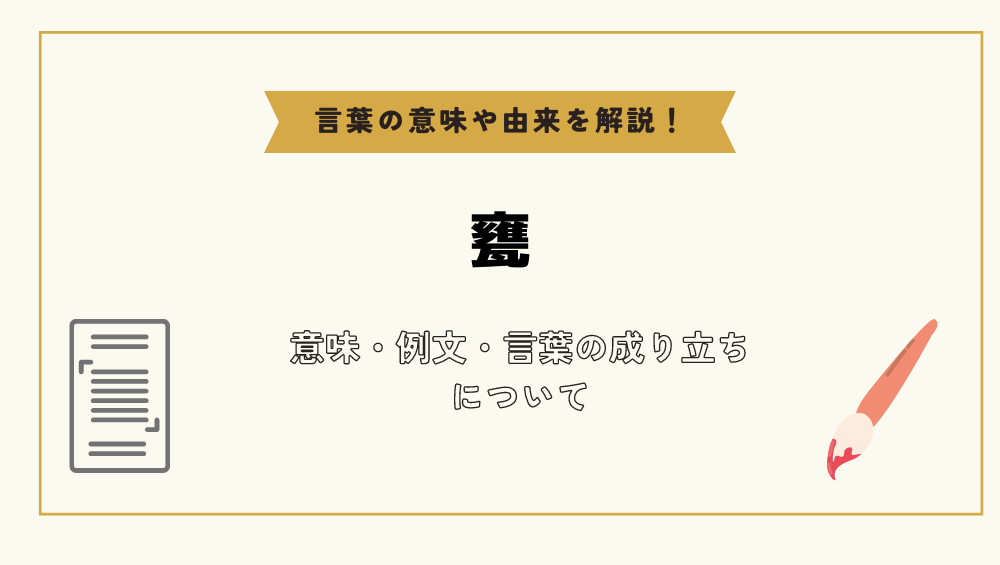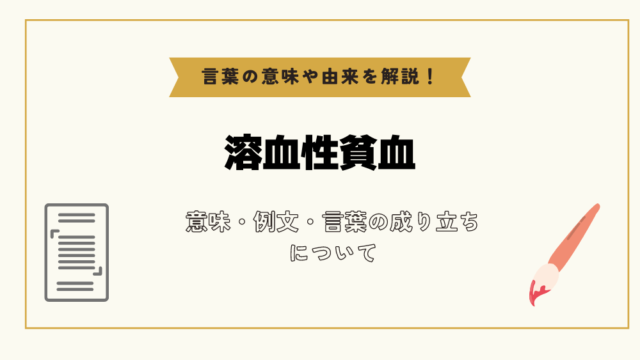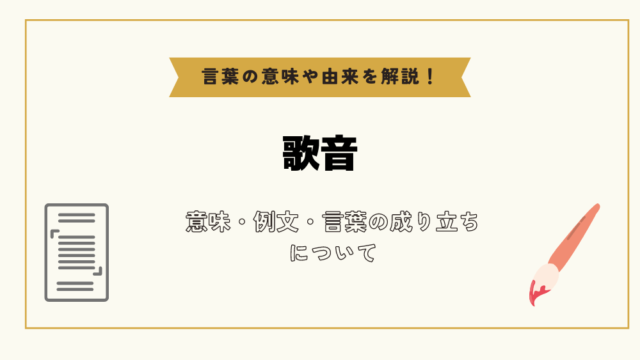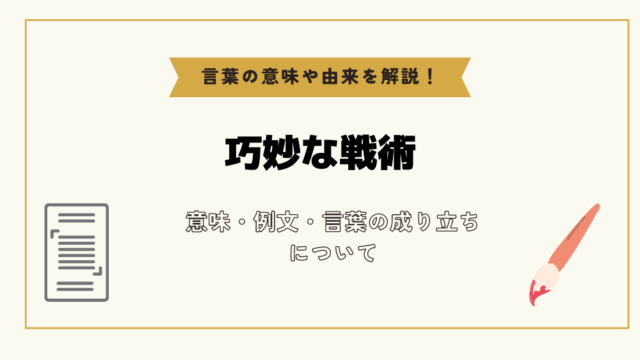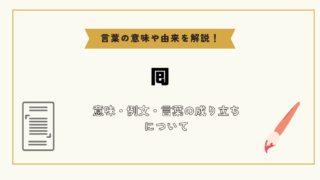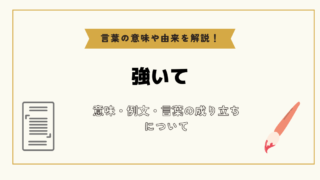Contents
「甕」という言葉の意味を解説!
甕(かめ)とは、古くから使われてきた容器の一種であり、主に液体や粉状のものを貯蔵するために用いられています。
陶器や木製、金属製などさまざまな素材で作られており、形状も様々です。
「甕」の読み方はなんと読む?
「甕」は、日本語の読み方で「かめ」と読まれます。
音読みの場合は「きょう」とも読むことがありますが、日本語では主に「かめ」という読み方が一般的です。
「甕」という言葉の使い方や例文を解説!
「甕」という言葉は、古い日本の家屋や田畑などで使われることが多く、主に液体の貯蔵や保存に用いられます。
例えば「水甕」や「醤油甕」といった言葉があり、古くからの生活や伝統に息づいています。
「甕」という言葉の成り立ちや由来について解説
「甕」は、古代から日本で使用されてきた容器であり、その由来は古代中国や朝鮮半島から伝わったとされています。
古くから様々な文化で使われており、日本独自の形や使い方が生まれました。
「甕」という言葉の歴史
甕は、古くから日本の暮らしに欠かせない存在であり、民家や寺社などさまざまな場所で使用されてきました。
歴史の中で多くの人々に愛用され、その姿は日本の文化や伝統を象徴しています。
「甕」という言葉についてまとめ
「甕」という言葉は、日本の歴史や文化に根付いた重要な容器であり、古くから使われてきた貴重な存在です。
その形や使い方はさまざまであり、現代でも様々な場面で活躍しています。
古今の人々に愛され続ける「甕」の魅力を再発見してみましょう。