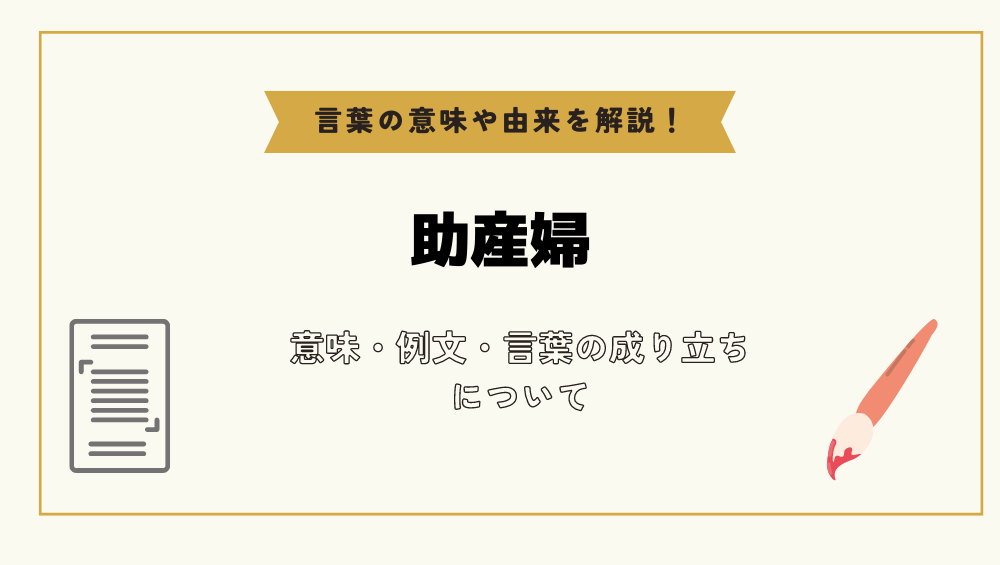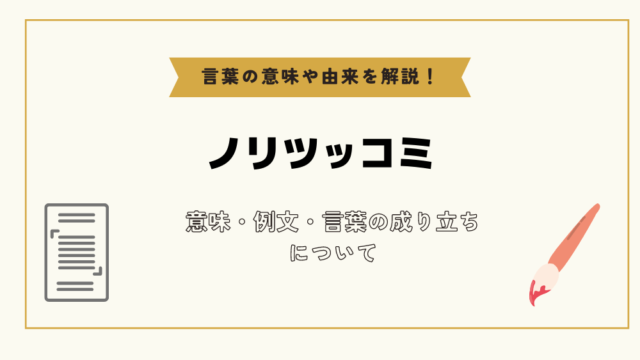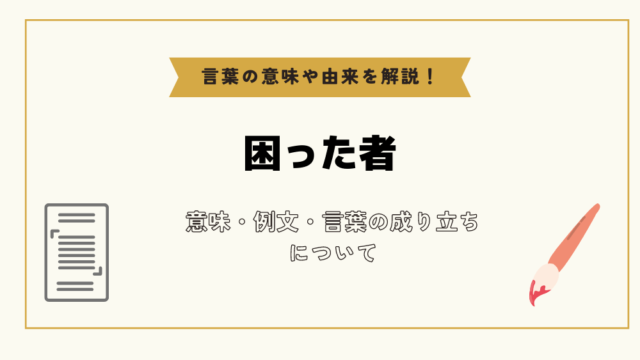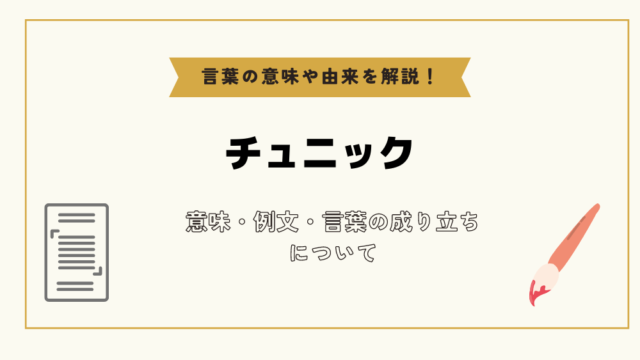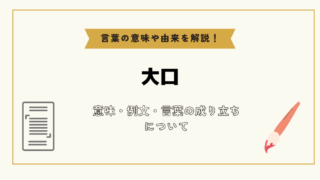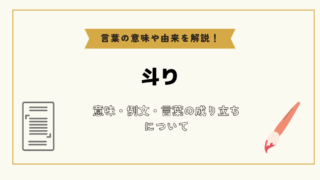Contents
「助産婦」という言葉の意味を解説!
「助産婦」とは、妊娠、出産、産後のケアなどを専門に行う女性の医療従事者のことを指します。
日本語では「じょさんふ」と読みます。
助産婦は、母親と赤ちゃんの健康を守りながら、安全な出産をサポートする重要な役割を果たしています。
彼らは、医療の知識と技術を駆使して、母子の安全と安心を守ります。
「助産婦」の読み方はなんと読む?
「助産婦」は、日本語で「じょさんふ」と読みます。
助産婦は、出産における専門家であり、母親と赤ちゃんの健康をサポートする重要な存在です。
彼らは、母子の安全を守りながら、安全な出産をサポートすることが使命です。
「助産婦」という言葉の使い方や例文を解説!
例文:彼女は助産婦として数々の出産を見守ってきた。
助産婦は、出産において母親と赤ちゃんの安全を守る専門家です。
彼らは、妊娠から出産、産後のケアまで幅広いサポートを提供しています。
「助産婦」という言葉の成り立ちや由来について解説
「助産婦」という言葉は、もともと「助ける」と「産む」から成り立っています。
古くから、妊娠、出産、産後のケアなどを専門に行う女性の存在がありました。
彼らは、母子の健康と安全を守りながら、出産をサポートしてきました。
「助産婦」という言葉の歴史
助産婦の歴史は古く、古代から現代に至るまで存在しています。
昔は、村のおばあさんなどが助産の役割を果たしていました。
近年では、専門の教育を受けた助産士が、安全な出産を支援する重要な存在となっています。
「助産婦」という言葉についてまとめ
助産婦は、妊娠、出産、産後のケアなどを専門に行う女性の医療従事者です。
彼らは、母子の健康と安全を守る使命を果たす重要な存在であり、安心して出産できる環境づくりに貢献しています。
彼らの専門知識と技術により、母子の安全が守られることが期待されています。