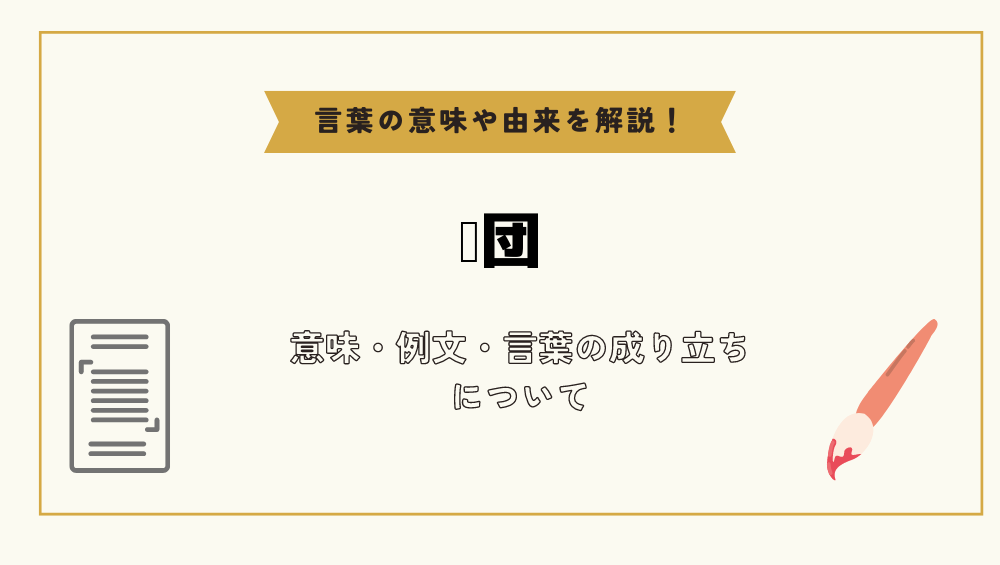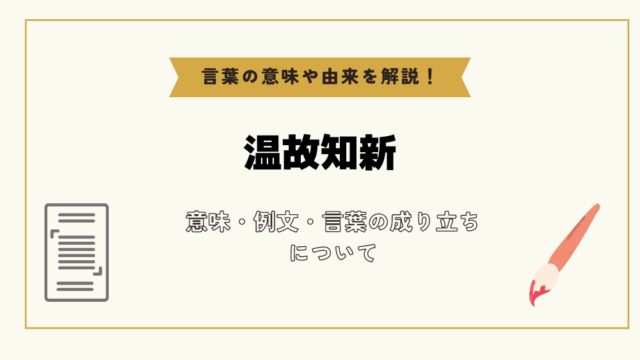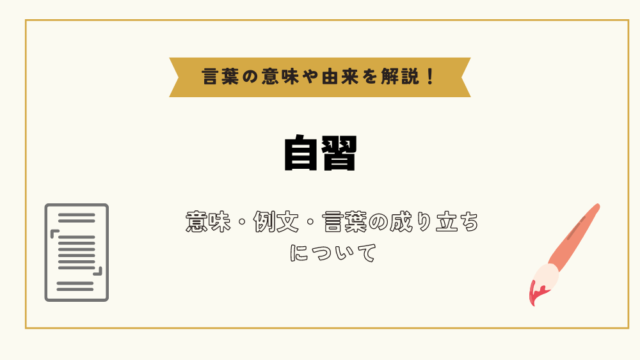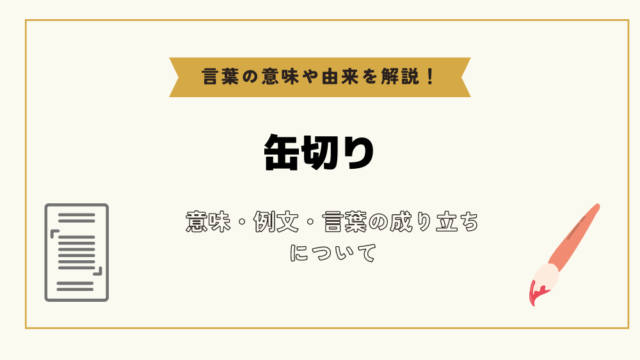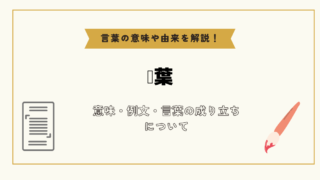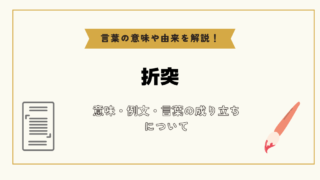Contents
「葯団」という言葉の意味を解説!
「葯団」とは、花の雄蕊(おうすい)にある葯(やく)が集まってできる部分を指します。
葯は花粉が作られる場所であり、団はまとまっているという意味があります。
つまり、「葯団」とは花の雄蕊にある花粉がまとまっている部分を指す言葉なのです。
花の繁殖にとって重要な役割を果たす部分なので、植物学や生物学の分野では重要な概念とされています。
。
「葯団」の読み方はなんと読む?
「葯団」の読み方は、「ようだん」と読みます。
日本語では少し難しい読み方かもしれませんが、植物の構造を表す言葉として覚えておくと、植物学や生物学の知識が深まります。
「葯団」という言葉を使う機会があった時に、自信を持って正しく読み方を把握しましょう。
。
「葯団」という言葉の使い方や例文を解説!
「葯団」という言葉は、主に植物の解剖学や生殖学の分野で使用されます。
例えば、「この花の葯団には多くの花粉が集まっています」というように、花の構造や機能を説明する際に使用されることが多いです。
専門的な用語ですが、日常生活で使う言葉にも取り入れてみると、より専門知識が身につくかもしれません。
。
「葯団」という言葉の成り立ちや由来について解説
「葯団」という言葉は、葯という構造がまとまっている部分を指し、団という語がまとまっていることを表しています。
つまり、葯が集まって固まっている部分を指す言葉となっています。
植物の生殖器官である花の部位を示す言葉として、その成り立ちや由来が理解されることで、専門知識が深まります。
。
「葯団」という言葉の歴史
「葯団」という言葉は、植物学や生物学の分野で古くから使用されてきました。
その歴史は古いですが、未だに現代でも植物の解剖学や生殖学の分野で重要な概念として使用されています。
植物の研究を進める上で不可欠な言葉として、歴史的な価値があります。
。
「葯団」という言葉についてまとめ
「葯団」という言葉は、花の雄蕊にある花粉がまとまっている部分を指す重要な概念です。
日本語では「ようだん」と読みますが、専門的な分野ではよく使用されます。
植物学や生物学の知識を深める際には、ぜひ覚えておきたい言葉です。
植物の研究や花の構造を理解する上で、欠かせない概念として「葯団」は重要な役割を果たしています。
。