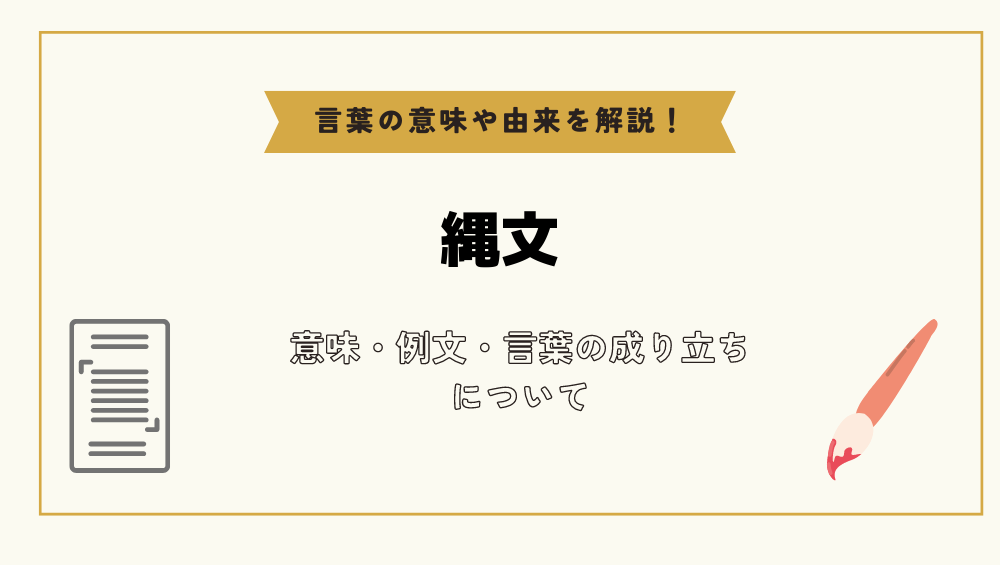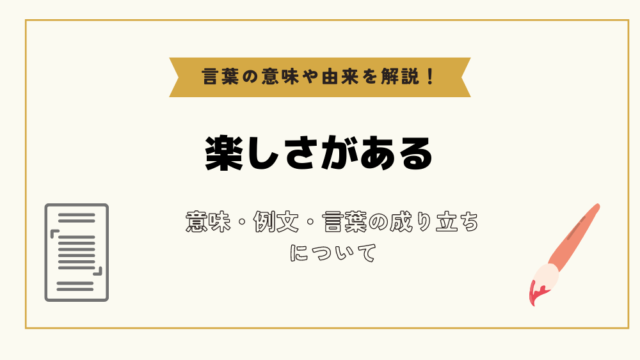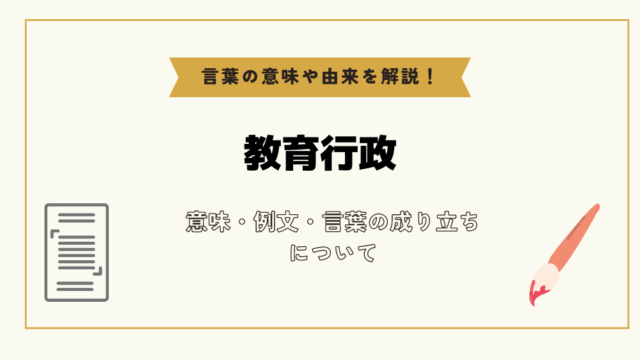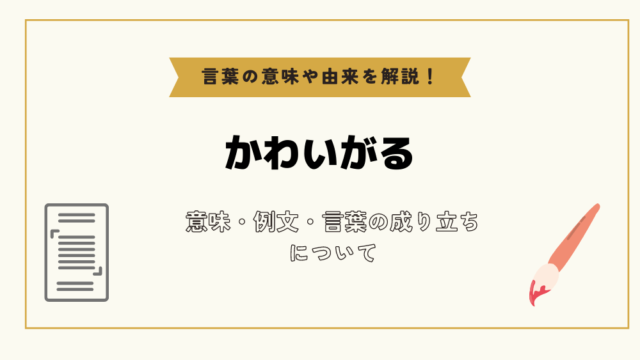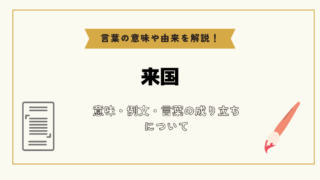Contents
「縄文」という言葉の意味を解説!
「縄文」という言葉は、日本の先史時代の時期や文化を表す言葉です。
縄文時代は約1万年前から約2千年前にかけて続いた時代で、狩猟や採集を中心とした生活が行われていました。
この時代の特徴は、土器や縄文土器が作られるようになったことや、神社跡や住居跡が発見されることなどです。
「縄文」の読み方はなんと読む?
「縄文」の読み方は、「じょうもん」と読みます。
この言葉は、日本の歴史を学ぶ際に欠かせない重要な概念です。
縄文時代の生活や文化を理解することで、日本の先史時代について深く知ることができます。
「縄文」という言葉の使い方や例文を解説!
「縄文」は、日本の先史時代を指す言葉として使われます。
例えば、「縄文時代の遺跡が新たに発見された」というように使われることがあります。
縄文時代の遺産や文化遺産が多く残されており、それらが日本の歴史を紐解く重要な手がかりとなっています。
「縄文」という言葉の成り立ちや由来について解説
「縄文」という言葉の由来は、縄で陶器に模様を描いたことに由来しています。
縄文土器には特徴的な模様が描かれており、この模様が縄で描かれたものから「縄文」と呼ばれるようになりました。
縄文時代は土器文化が隆盛を極めた時代でもあります。
「縄文」という言葉の歴史
「縄文」の歴史は、約1万年前から2千年前まで続いたとされる縄文時代に始まります。
この時代には、日本列島に独自の文化が栄えました。
縄文時代の遺産や遺跡から、当時の人々の生活や文化を知ることができます。
「縄文」という言葉についてまとめ
「縄文」という言葉は、日本の先史時代の時期や文化を表す重要な概念です。
縄文時代は土器や縄文土器が作られるようになった時代であり、日本の歴史を学ぶ上で欠かせない時代となっています。
縄文時代の遺産や遺跡から、日本の先史時代の生活や文化を知ることができます。