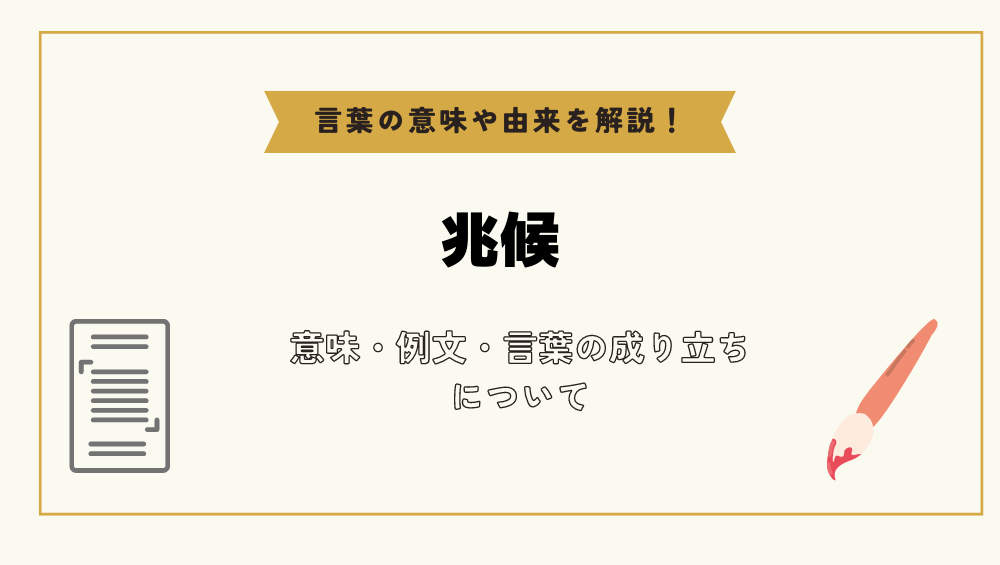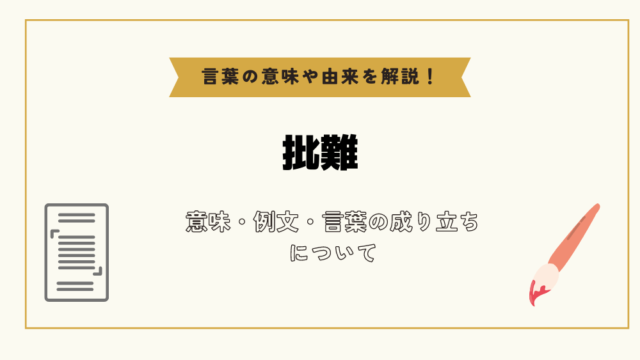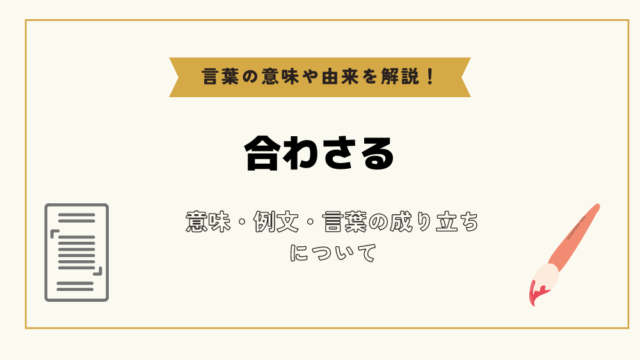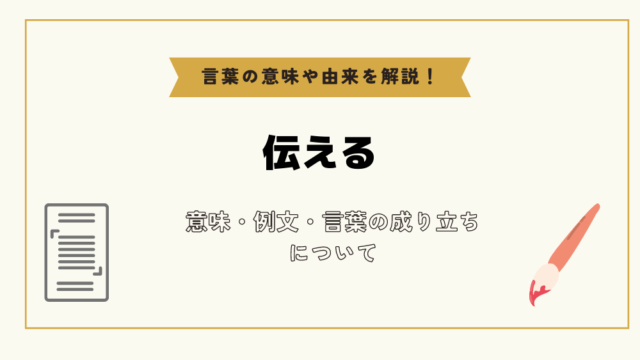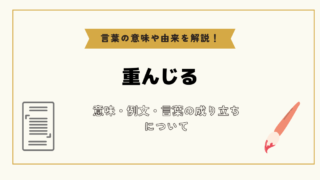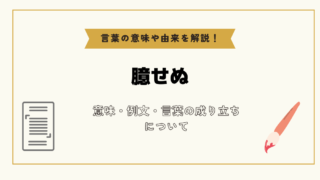Contents
「兆候」という言葉の意味を解説!
「兆候」という言葉は、何かしらの出来事や状態の前兆や合図を意味します。
何かが起こる前に、その予兆や兆しを示すものを指す言葉です。
例えば、風が吹く兆候や、雲行きが怪しい兆候などがあります。
この言葉の使い方には注意が必要です。
「兆候」は否定的な意味で使われることが多いため、問題や病気の前兆など、悪いニュアンスを持つことが多いです。
しかし、状況によっては良い兆候や希望の兆しを指すこともあります。
「兆候」という言葉の読み方はなんと読む?
「兆候」という言葉は、「ちょうこう」と読みます。
漢字の「兆」は、未来を予知することを意味し、「候」は、出来事の前兆や兆しを意味します。
一緒に読むと、「ちょうこう」となります。
「兆候」という言葉の使い方や例文を解説!
「兆候」という言葉は、問題や病気の前兆を表す際によく使われます。
例えば、「風邪の兆候が出たので、早めに休んだほうがいいですよ」と言われた場合、体の具合が悪くなる前の症状や状態を指しています。
また、「好景気の兆候が見られる」という表現もあります。
経済やビジネスの文脈で使われることが多く、景気が上向いていることや、将来的に好転の可能性がある状況を表します。
「兆候」という言葉の成り立ちや由来について解説
「兆候」という言葉は、漢字で表記すると「兆」と「候」からなります。
「兆」は、未来を予知することを意味し、「候」は、出来事の前兆や兆しを意味します。
この言葉の由来は、古代中国の占いや風水の考え方に関連しています。
人々は自然現象や動物の行動から、未来を予測しようとしたため、それに伴って「兆候」という言葉が使われるようになりました。
「兆候」という言葉の歴史
「兆候」という言葉は、日本では平安時代から使われてきました。
古代中国の文化や思想が日本に伝わり、言葉として定着したものです。
また、江戸時代に入ると、医学や科学の分野での使用が増え、現在でも病気の診断などで頻繁に使用されています。
「兆候」という言葉についてまとめ
「兆候」という言葉は、何かしらの出来事や状態の前兆や合図を指し、否定的な意味合いが強いことが特徴です。
「兆候」という言葉は、病気や問題の前兆を指すことが一般的ですが、良い兆候や希望の兆しを指すこともあります。
この言葉は、古代中国の占いや風水の文化から派生し、日本に伝わって使われるようになりました。
現在でも病気の診断や経済の動向など、様々な分野で使用されています。