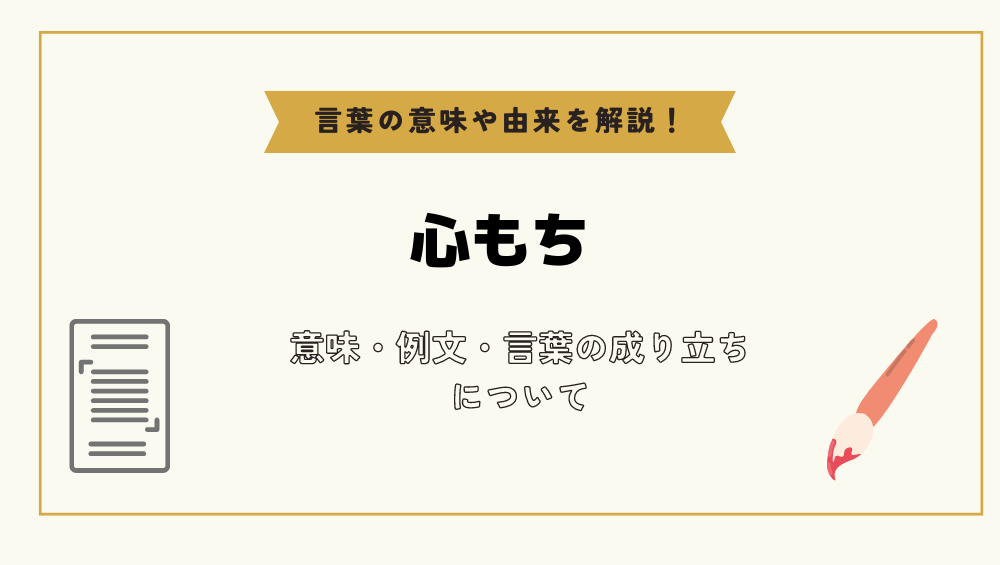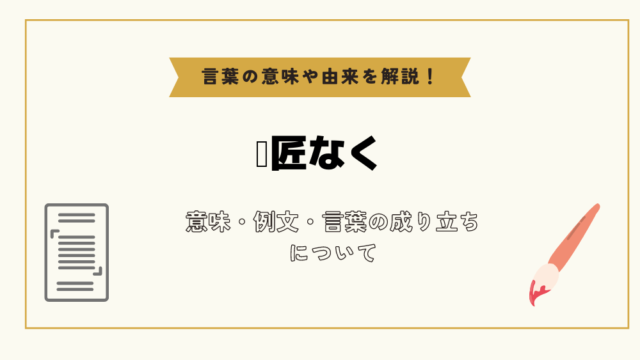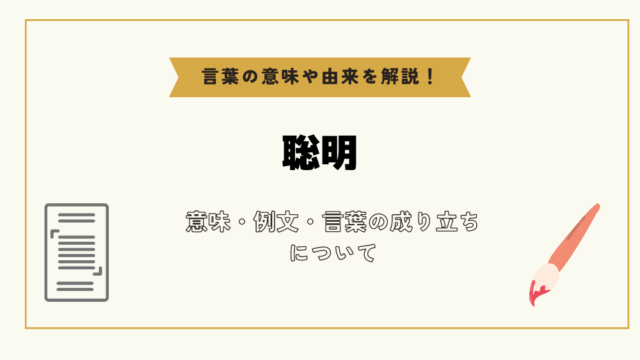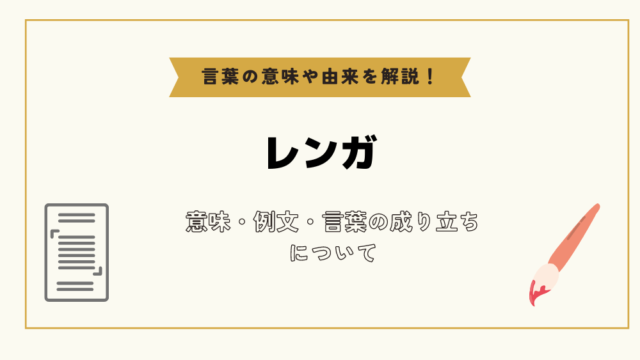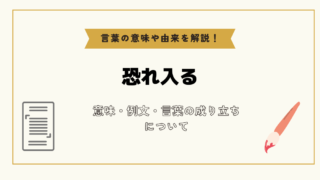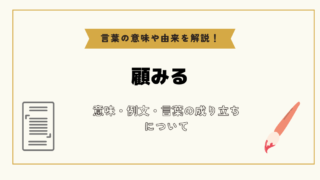Contents
「心もち」という言葉の意味を解説!
「心もち」という言葉は、少しの程度や量を表す際に使われます。
心もちは、少しでも多くの感情や思いを含めることを示します。
例えば、相手の意見に心もち反対するというのは、少しの反対の気持ちを持っているという意味です。
心もちは、会話や文章でよく使用される表現です。
日本語のニュアンスが含まれた言葉であり、単に「少し」という意味だけではなく、微妙な感覚や感情の範囲を表現する際に利用されます。
「心もち」という言葉の読み方はなんと読む?
「心もち」という言葉は、「こころもち」と読みます。
日本語の「心」の読み方は「こころ」であり、少しの程度や感情を表す「もち」も合わせて「こころもち」と読むのです。
「心もち」という言葉の使い方や例文を解説!
「心もち」は、日常会話や文章中でさまざまなシチュエーションで使用されます。
例えば、「この料理には塩を心もち足してみてください」という表現は、料理には少し塩を足してみてほしいという意味です。
また、「彼の態度には心もち不満を感じます」という表現は、彼の態度に少しの不満を感じていることを示しています。
「心もち」という言葉の成り立ちや由来について解説
「心もち」という言葉の成り立ちは、「こころ」という日本語の「心」と、「もち」の組み合わせです。
日本語には、微妙なニュアンスや感覚を表現するために、このような言葉が生まれました。
由来や起源については明確な情報はありませんが、昔から使われている言葉であり、日本語の特徴を表しています。
「心もち」という言葉の歴史
「心もち」という言葉の歴史は古く、江戸時代から使われていると言われています。
日本語特有の意味や使い方を持つ言葉として、現代でも頻繁に使用されています。
少しだけの感覚や程度を表現する際に、「心もち」という言葉が用いられることは、日本の言葉の豊かさを示しています。
「心もち」という言葉についてまとめ
「心もち」という言葉は、少しの程度や感情を表す際に使用されます。
日本語特有のニュアンスを持った言葉であり、微妙な感覚や感情の範囲を表現するために利用されます。
日本語の言葉の豊かさや細かさを感じることができる「心もち」という表現は、日本語文化の一部として大切な言葉です。