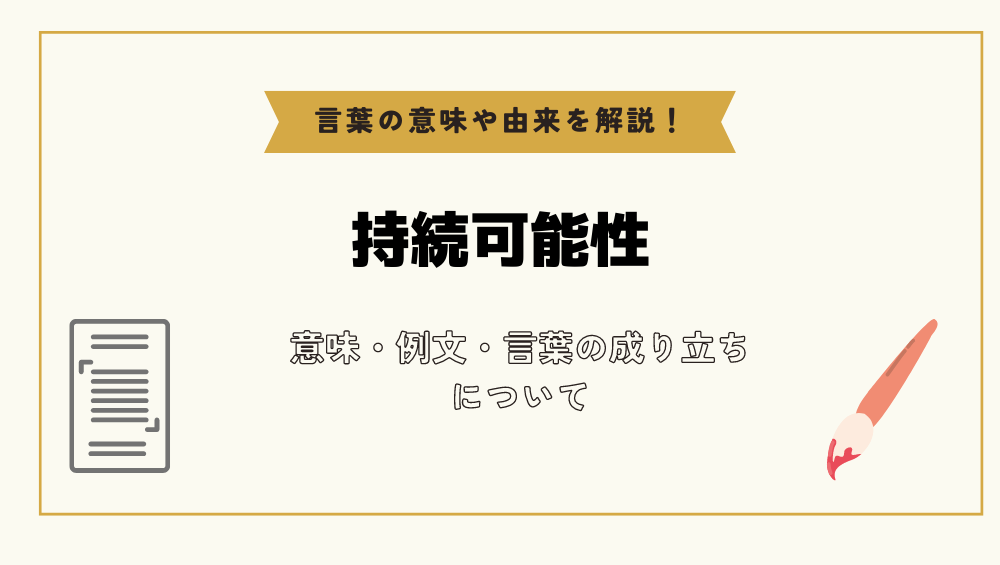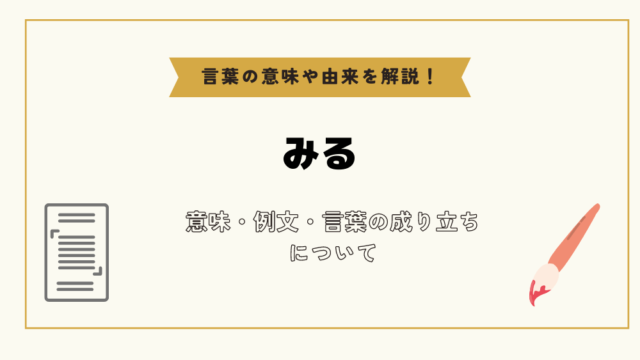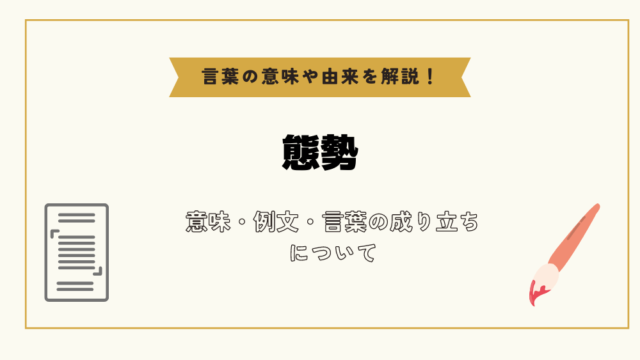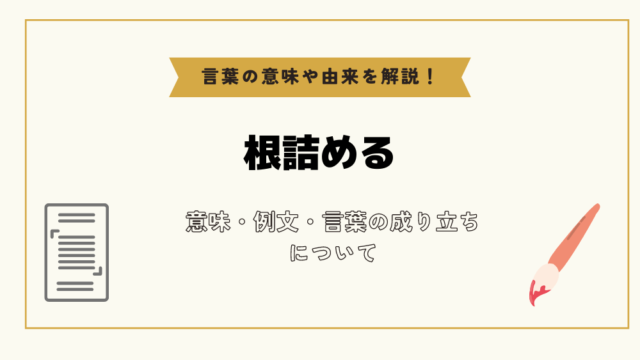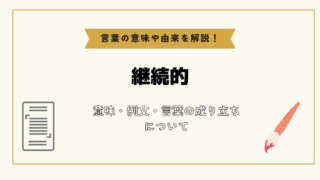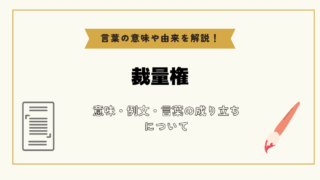Contents
「持続可能性」という言葉の意味を解説!
「持続可能性」とは、環境や社会、経済の発展を永続的に保つことを指す言葉です。
持続可能性は、将来の世代にも良好な環境や資源を提供し、社会の不平等を是正し、豊かな生活を実現することを目指しています。
持続可能性を実現するためには、環境への負荷を軽減する取り組みや、社会的な課題を解決する政策の策定が必要です。
また、個人や企業、地域社会など、様々なレベルでの取り組みが重要です。
持続可能性には、環境の保護や自然資源の効果的な利用、循環型社会の構築、社会的な包摂や貧困の解消、さらには経済成長の持続性などが含まれます。
持続可能性について考えることは、地球上の資源を適切に管理し、将来の世代に引き継ぐための重要な課題です。
「持続可能性」という言葉の読み方はなんと読む?
「持続可能性」は「じぞくかのうせい」と読みます。
この読み方は日本語のルールに基づいています。
日本語では漢字の音読みを用いて言葉を読むことが一般的です。
「じぞくかのうせい」という言葉は、持続性と可能性の2つの語が組み合わさっています。
意味の通り、持続的な発展と可能性を表現しています。
「持続可能性」という言葉の使い方や例文を解説!
「持続可能性」という言葉は、環境や経済、社会の分野でよく使われる言葉です。
例えば、企業が環境に配慮した製品を開発したり、地域が再生可能エネルギーを利用したりする場合に、「持続可能性の観点から」というように使用されます。
また、政策やプログラムを立案する際にも「持続可能性を考えた取り組み」という表現がよく使われます。
例えば、都市計画においては、交通の流動性やエネルギー効率を向上させるなど、持続可能なまちづくりを目指します。
持続可能性の考え方を取り入れることで、地球環境の保護や資源の効率的な利用、社会の課題の解決など、より良い未来を築くことができます。
「持続可能性」という言葉の成り立ちや由来について解説
「持続可能性」という言葉は、1983年に国際連合(UN)が開催した「持続可能な生活のための世界委員会」で初めて使用されました。
この委員会は、持続可能な開発に関する報告書「われわれの未来」をまとめ、その中で「持続可能性」という言葉を提案しました。
「持続可能性」という言葉の由来は、英語の「sustainability(サステイナビリティ)」にあります。
この言葉は、持続的な発展や生活の維持を表す言葉であり、環境保護や社会的な包摂、経済成長などの要素を含めた総合的な概念です。
「持続可能性」という言葉は、その後、国際的な議論や取り組みで広く使用されるようになりました。
現在では、持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定など、国際的な枠組みでも重要な概念として位置づけられています。
「持続可能性」という言葉の歴史
「持続可能性」という言葉の歴史は、環境問題や資源の枯渇といった課題に関心が高まった20世紀半ばにまで遡ります。
人々は持続可能な未来をどのように築くかを考え始め、国際連合や各国の政府、NGOなどがさまざまな活動や議論を展開しました。
1987年に発表された「われわれの未来」報告書が「持続可能性」という言葉を初めて提案したことから、その概念が広まりました。
その後、1992年の地球サミットや2005年の持続可能な開発目標(SDGs)採択など、国際的な枠組みが進展しました。
現在、持続可能性は多くの人々にとって重要なテーマとされ、私たちの生活や社会のあり方に大きな影響を与えています。
「持続可能性」という言葉についてまとめ
「持続可能性」とは、環境、社会、経済の発展を永続的に保つことを目指した概念です。
環境負荷の軽減や社会課題の解決に取り組むことで、豊かな未来を実現することが求められています。
この言葉は、1983年に国際連合が提案し、その後、国際的な議論や取り組みで広く使用されるようになりました。
持続可能な開発目標やパリ協定など、政府や国際機関の取り組みにも取り入れられています。
持続可能性について考えることは、地球環境を保護し、資源を適切に管理するために重要です。
私たち一人ひとりが行動を起こし、持続可能な未来を築いていくことが求められています。