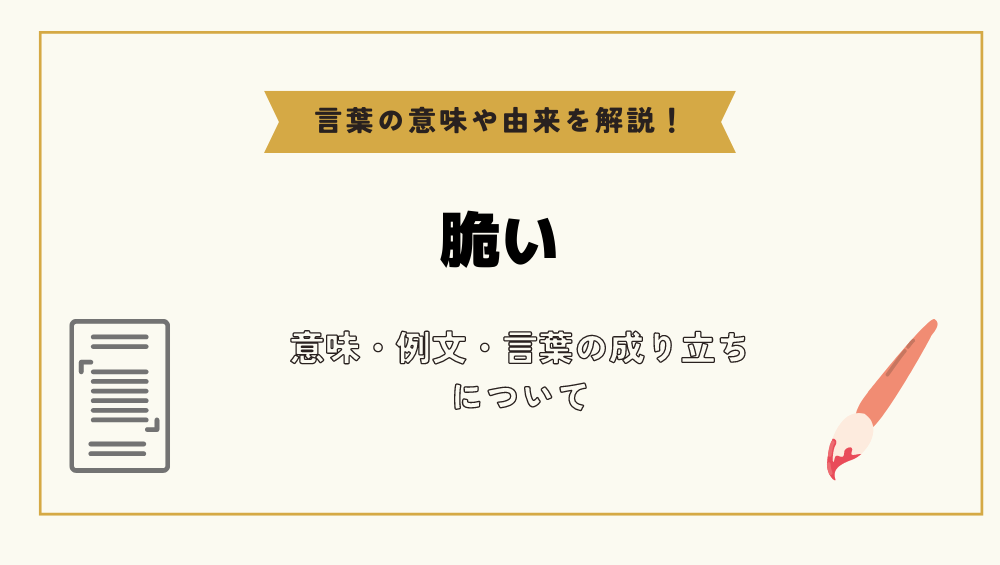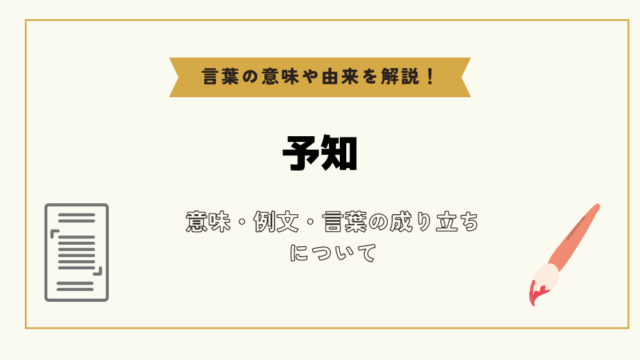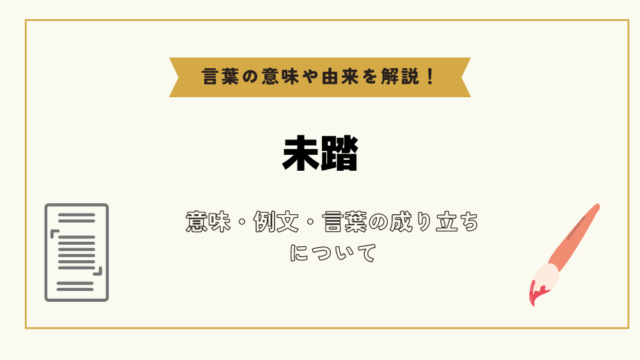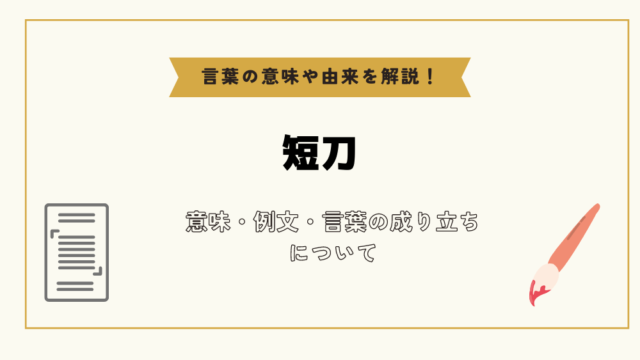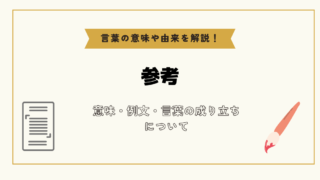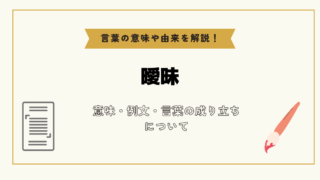「脆い」という言葉の意味を解説!
「脆い」は「壊れやすく、抵抗力が弱い状態」を示す形容詞で、物質・精神・制度など対象を限定せず広く使われます。第一に物理的な意味では、ガラスや薄い氷のように外力に対して破断しやすい様子を表します。第二に比喩的には、人間関係や感情、システムなどが少しの負荷で崩れる不安定さを指すことが多いです。日常会話では「脆いガジェット」「人間関係が脆い」のように硬い物から抽象概念まで自在に修飾できます。
脆さを語る際は「硬い=丈夫」とは必ずしも一致しない点が重要です。硬い材質ほど割れやすい「脆性破壊」という現象があるため、金属工学でも「硬度」と「靭性」が区別されます。「脆い」は単なる弱さではなく「靭性の低さ」を示す専門的な形容表現としても機能するのです。
また心理学では「レジリエンス(回復力)」の逆概念として脆さが論じられ、ストレス耐性の低さを説明する際に用いられます。このように対象が異なっても「小さな衝撃で大きく損なわれる」という共通イメージが核となります。
「脆い」の読み方はなんと読む?
「脆い」は一般に「もろい」と読みます。送り仮名は「脆い」と「脆し」の二通りがありますが、現代文では「脆い」が圧倒的に多用されます。「脆し(もろし)」は古典的表現で、和歌や古文で目にする程度です。
漢字としての「脆」は常用漢字表に含まれておらず、新聞・放送では「もろい」と仮名書きにするのが原則です。ただし技術論文や専門書では「脆性(ぜいせい)」など熟語に組み込まれる形で頻繁に登場します。
パソコンやスマートフォンで入力する際は「もろい」と打鍵して変換候補から「脆い」を選ぶのが一般的です。なお「ぜい」と読むケースは「脆弱(ぜいじゃく)」の熟語内に限られるため、単独形容詞では用いません。
「脆い」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方のポイントは「①壊れやすさを強調する ②原因より結果の儚さを描写する ③比喩対象を限定しすぎない」の三つです。まず物理的事象の例としては「凍った池の表面は思ったより脆い」など、実際の破壊を伴う場面で用います。
次に抽象的用法としては感情・信頼・計画など人の心や制度に焦点を当て、「長年築いた関係が案外脆かった」のように儚さを示します。
【例文1】この会社のセキュリティ体制は外部からの攻撃に脆い。
【例文2】彼の自信は批判の一言で脆くも崩れた。
注意点として「脆弱」との混同がしばしば起こりますが、「脆い」は形容詞、「脆弱」は形容動詞なので活用が異なります。「脆い計画」は可能ですが「脆弱い計画」とは言いません。
「脆い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「脆」は「肉月(にくづき)偏」に「危」を組み合わせた形で、「体が危ういほど弱い」を象形的に表しています。肉月偏は人体や肉体に関連する意味を持ち、「危」は崖の上で不安定に立つ人を象る古い字形です。これが転じて「少しの揺らぎで崩れる様子」を刺し示すようになりました。
日本語の形容詞「もろし」は奈良時代の『万葉集』に既に登場し、当時は「脆し」「毀し」など複数の漢字が混用されています。平安期には「もろき」の形も見られ、「尊き」「危うき」と同様に古語の形容詞語尾「き」「し」が使われていました。
近世以降、「もろい」という口語形と「脆」という一字表記が定着しました。同時に漢語の「脆弱」が輸入され、明治期の翻訳文献で工学・軍事の脆性を説明する際に頻出したことで技術用語としての側面も強まりました。
「脆い」という言葉の歴史
「脆い」は奈良時代の歌謡に始まり、中世の和歌を経て近代文学では人生の儚さを象徴するキーワードとなりました。『万葉集』巻九の「いわねもろし」では岩に掛けて愛情の脆さが詠まれています。平安和歌では「花の命はもろくあはれ」といった脆さの美学が確立し、無常観と結びつきました。
江戸期になると「もろい土蔵」「もろい紙細工」など具体物の描写が増え、町人文化で工芸品の質評にも用いられます。明治以降は漱石や芥川が精神の脆さを描写する際に用い、西洋心理学との接点を持ちました。
戦後、高度経済成長期の技術論文で「ガラスが高硬度でも脆い理由」という議論が活発化し、材料力学の専門用語としての地位が確立されます。現代ではサイバーセキュリティやサプライチェーンの堅牢性を論じる際にも用いられ、社会構造の弱点を示すキーワードへと拡張しました。
「脆い」の類語・同義語・言い換え表現
代表的な類語には「壊れやすい」「弱い」「儚い」「脆弱」「破損しやすい」などがあり、文脈で選択すると表現が豊かになります。「儚い」は無常観や短命さを含意し、感情の機微を描く際に向きます。「壊れやすい」は主として物体に使われ、技術文書でも誤解が少ないです。
一方「脆弱」はやや硬い表現で、法律・医療・ITにおけるリスク分析で多用されます。「弱い」は汎用的ですが、力や影響に対し抵抗が小さいという意味が主で、破壊そのものを示唆しません。
【例文1】この合金は靭性が低く、極低温では脆性破壊しやすい=「脆い」を「脆弱」と置換可。
【例文2】計画は脆くも崩れた=「儚い計画」に置換すると情緒が強まる。
ニュアンスの差を理解すれば、文章の意図を正確に伝えることができます。
「脆い」の対義語・反対語
「脆い」の対義語は「頑丈」「強靭」「堅牢」「しなやか」など、衝撃や負荷に耐える性質を表す語が該当します。「頑丈」「堅牢」は主に物理的構造物に使われ、建築や製造業で用例が多いです。「強靭」は金属や繊維の靭性を示し、折れず曲がってもしぶとい特性を強調します。
比喩的な反対語としては「強固な信頼」「不屈の精神」があり、脆さの欠如を示す際に便利です。技術分野では「延性(ductility)が高い」「タフネスがある」が対比的キーワードとして挙げられます。
【例文1】このポリマーは高い延性を持ち、脆いガラスに比して強靭だ。
【例文2】彼女の意志は脆くない、むしろ不屈そのものだ。
対義語を併記すると文章のコントラストが際立ち、読者の理解を助けます。
「脆い」についてよくある誤解と正しい理解
「柔らかい=脆い」という誤認が多いのですが、実際には硬くても脆い物質が存在し、その逆もある点が要注意です。例えばゴムは柔らかいものの大きく伸びて切れにくいので「脆い」とは言いません。むしろガラスやセラミックのように非常に硬いが割れやすい材料が「脆い」の典型例です。
また「脆弱」と「脆い」が同義という誤解もあります。脆弱は形容動詞で名詞「弱さ」に近い抽象度があり、法律文書では「脆弱な立場」と物理現象以外にも適用範囲が広いです。一方「脆い」は形容詞で、語調が口語的なため小説や会話で自然に使えます。
最後にIT分野で「ぜいじゃく性」という専門語があるため「脆性」と混同しやすいですが、前者は脆弱性(vulnerability)、後者は材料の壊れやすさ(brittleness)を指します。文脈に応じて正しく使い分けましょう。
「脆い」を日常生活で活用する方法
日常生活では「形ある物」より「形のないコト」に脆さを見いだすことで、言葉に深みが生まれます。例えば人間関係や心の状態を描写する際に「脆い友情」「脆い自尊心」と使えば、単に「弱い」よりも儚さと危うさを同時に表現できます。
DIYや料理でも応用可能で「脆いクッキー生地」「脆い陶器の皿」のように状態を細やかに伝えられます。子どもに科学を教えるときには「チョコレートは低温で硬いが脆いんだよ」と示すと、材料特性の理解が進みます。
【例文1】新築の壁はまだ乾燥し切っておらず衝撃に脆い。
【例文2】睡眠不足の脆い集中力ではミスを招きやすい。
言葉選び次第で文章の情景が鮮明になり、コミュニケーションの質が向上します。
「脆い」という言葉についてまとめ
- 「脆い」は少しの衝撃で壊れる、または崩れる性質を示す形容詞。
- 読み方は「もろい」で、常用漢字外のため仮名書きも一般的。
- 奈良時代から用例があり、古語「もろし」を経て現代に定着した。
- 技術・心理・日常の幅広い分野で使えるが、硬さと脆さを混同しない注意が必要。
「脆い」は物理的にも心理的にも「小さな負荷で崩れる性質」を端的に捉える便利な言葉です。硬度や強度と混同しないよう注意しつつ用いれば、文章に繊細なニュアンスを与えられます。
古典から最新技術まで活躍する語彙であり、ガラスの割れやすさを示すときも、組織のガバナンス不足を指摘するときも同じ語で表現できます。本記事で紹介した成り立ちや使い方を踏まえ、的確に「脆い」を使いこなしてみてください。