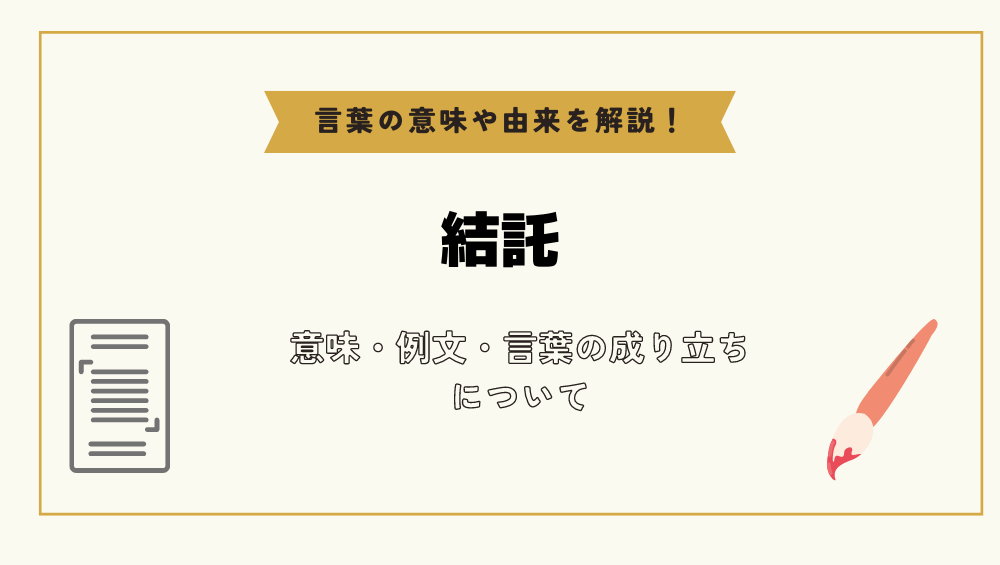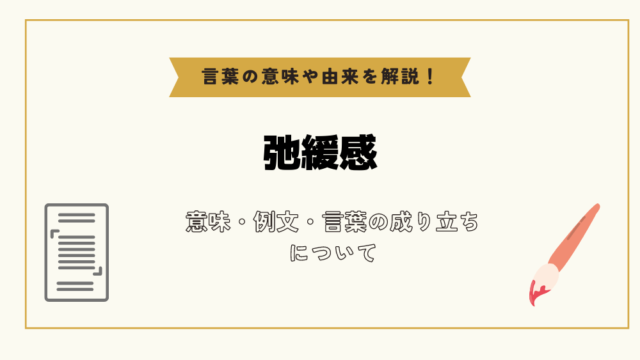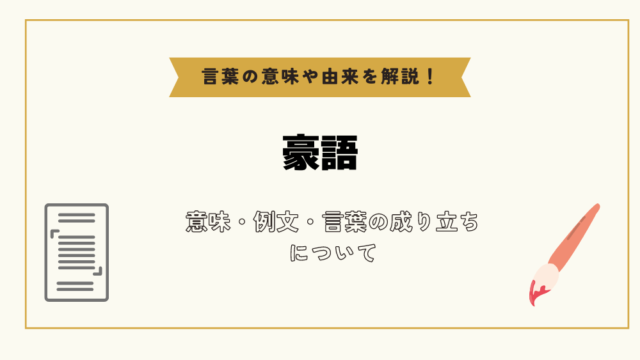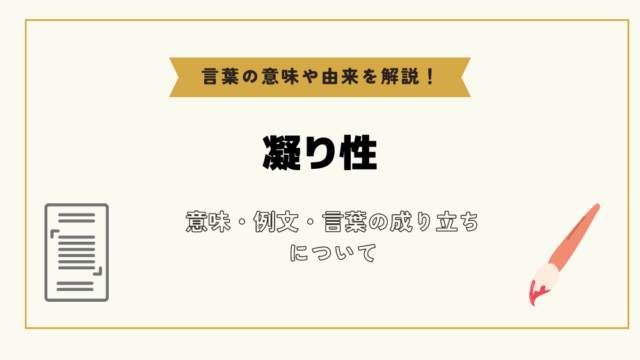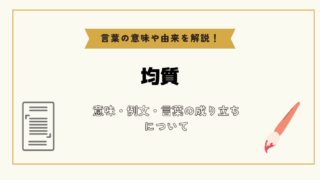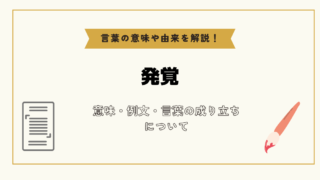Contents
「結託」という言葉の意味を解説!
結託(けったく)とは、複数の人や団体が力を結集して一体となることを指します。結託は、共同の目的や利益のために団結し、力を合わせることを表しています。結託によって、個々の力や能力が相乗効果を生むことが期待されます。
結託は、組織やグループのメンバー同士が協力し、連携して行動することで実現されます。個々の力やアイデアを結集し、結託することによって、より大きな成果や効果を生み出すことができるのです。
「結託」という言葉の読み方はなんと読む?
「結託」という言葉は、「けったく」で読みます。2つの漢字から成り立っており、それぞれの漢字の読み方に注目すると、このように読むことがわかります。
「結」は、「けつ」という読み方が一般的ですが、連濁の影響で「けっ」と読まれることもあります。「託」は、「たく」という読み方が一般的です。したがって、「結託」は「けったく」と読むのです。
「結託」という言葉の使い方や例文を解説!
「結託」という言葉は、主に人や組織・団体の協力や連携に関する文脈で使われます。例えば、企業内の部署同士が結託してプロジェクトに取り組む、異なる団体が結託して社会的な問題に対処するなどの使い方があります。
具体的な例文としては、「私たちは結託して、地域の清掃活動に取り組みました」というような文が考えられます。「結託して」という表現は、様々な主体が協力して行動することを表しており、その結果として良い成果が生まれたことを示しています。
「結託」という言葉の成り立ちや由来について解説
「結託」という言葉は、漢字2文字から成り立っています。「結」という漢字は、「結ぶ」や「結合」といった意味を持ち、「託」という漢字は、「預ける」や「任せる」といった意味を持っています。
したがって、「結託」という言葉は、力や資源を集約し、互いに頼り合って一体となることを表しています。誰かに何かを預けて共同で目標を達成するという意味合いも含まれています。
「結託」という言葉の歴史
「結託」の使用や定着は、長い歴史を持っています。日本の古典文学や歴史書にもこの言葉が登場し、組織や団体の連携や協力に関する記述が存在します。
また、近代日本では、組合や労働組織、政治団体などが結託を行い、力を合わせて社会的な活動を展開してきました。結託の概念は、多様な分野で広く活用され、日本の社会や組織の発展に貢献してきた歴史を持っています。
「結託」という言葉についてまとめ
「結託」とは、複数の人や団体が力を結集して一体となることを指す言葉です。結託によって、共同の目的や利益のために団結し、協力して行動することが可能となります。
また、結託は組織やグループのメンバー同士が連携することで、より大きな成果や効果を生み出すことができます。結託は、私たちが力を合わせて共同で目標を達成するための重要な要素であり、社会や組織の発展に大きな貢献をしています。