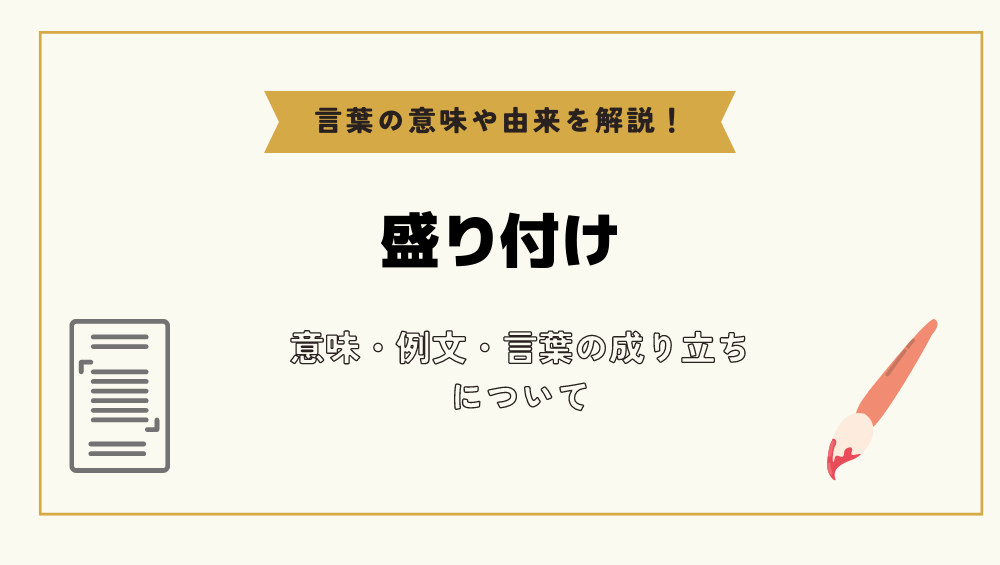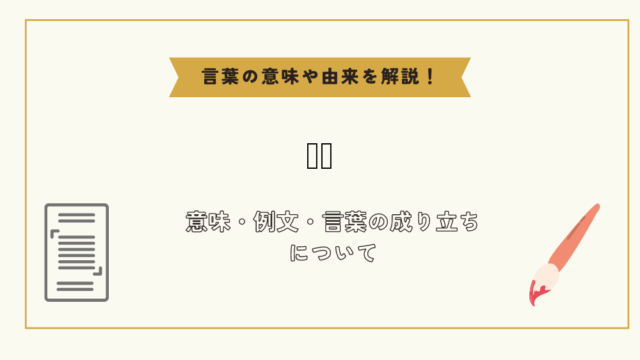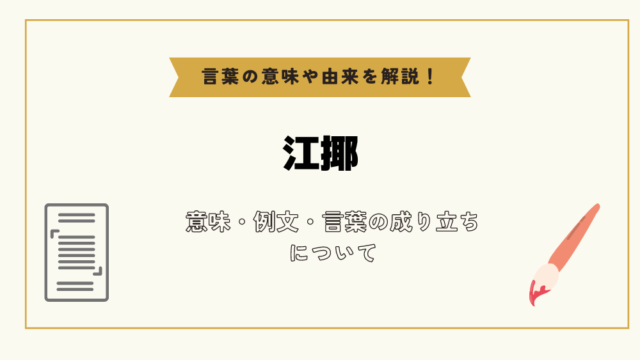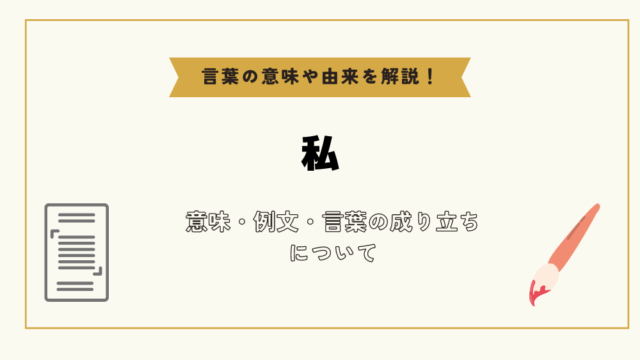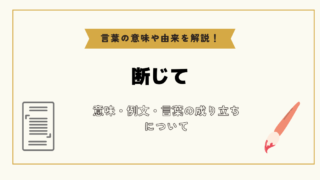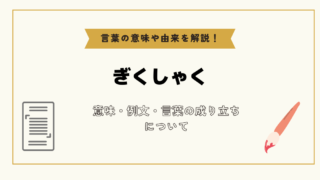Contents
「盛り付け」という言葉の意味を解説!
盛り付けとは、食べ物や料理の見た目を美しく整えることを指します。
料理を盛り付けることで、味だけではなく視覚的な楽しみも与えることができます。
盛り付けは、料理をより魅力的に見せるために行われる重要な作業です。
ただし、見た目だけにこだわるのではなく、料理の味や香り、栄養価も考慮する必要があります。
美しい盛り付けは、料理の魅力を引き出し、食欲をそそります。
「盛り付け」という言葉の読み方はなんと読む?
「盛り付け」という言葉は、「もりつけ」と読みます。
この読み方は、一般的に広く認知されています。
飲食業界や料理に関心のある人々の間では、当たり前のように使用されています。
料理番組や雑誌などでも、よく耳にする言葉です。
「盛り付け」という言葉の使い方や例文を解説!
「盛り付け」という言葉は、食事の際に特によく使われます。
例えば、「この料理の盛り付けを変えれば、もっと美味しそうに見えるかもしれませんね」というように使用されます。
また、「このデザートの盛り付けが素晴らしい」というように、料理の見た目の美しさを褒める際にも使われます。
盛り付けは、食事の楽しみを倍増させる大切な要素となっています。
「盛り付け」という言葉の成り立ちや由来について解説
「盛り付け」という言葉は、日本の食文化に由来しています。
日本料理では、料理を美しく盛り付けることが伝統とされており、器や盆などに料理を配置する技術が重要視されています。
そのような背景から、「盛り付け」という言葉が生まれたと考えられます。
日本料理の盛り付けは、鮮やかな色彩や繊細な形状など、芸術作品のような美しさを持っています。
「盛り付け」という言葉の歴史
「盛り付け」という言葉の歴史は、古くから存在しています。
日本の料理文化は、食事の際に料理を見せることが大切だという考え方に基づいています。
そのため、「盛り付け」という言葉が生まれ、定着してきたのです。
現代の日本では、料理の盛り付けがますます重要視されるようになり、飲食業界や料理愛好家たちの間で盛り付けの技術やアイデアが広がっています。
「盛り付け」という言葉についてまとめ
「盛り付け」という言葉は、料理を美しく整えるための作業を指します。
食事の楽しみを倍増させるために必要な要素であり、視覚的な魅力を与えることができます。
日本の食文化に由来している言葉であり、古くから存在しています。
現代ではますます重要視され、飲食業界や料理愛好家たちの間で技術やアイデアが広がっています。
料理を盛り付けることで、食事の魅力を引き立たせ、食欲をそそります。