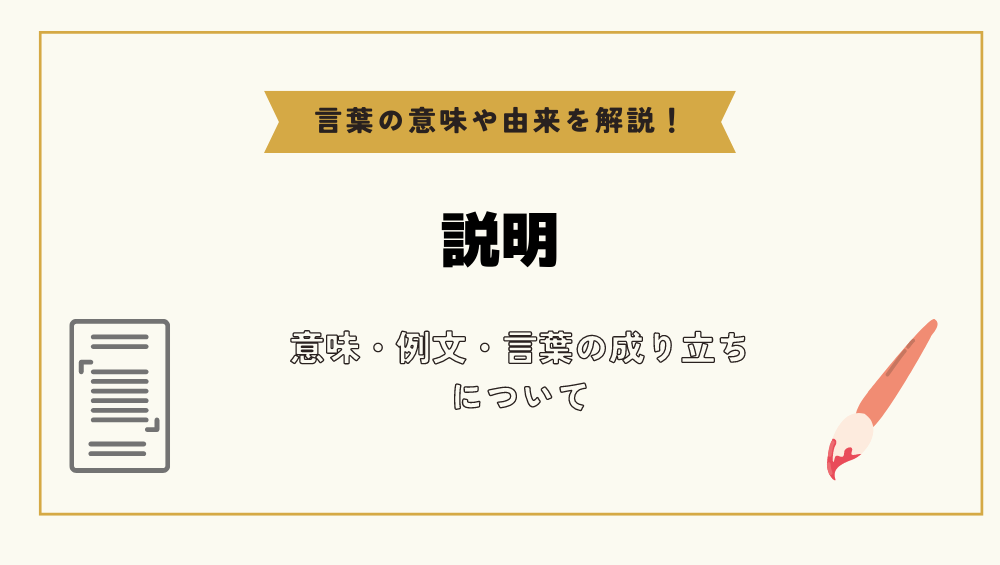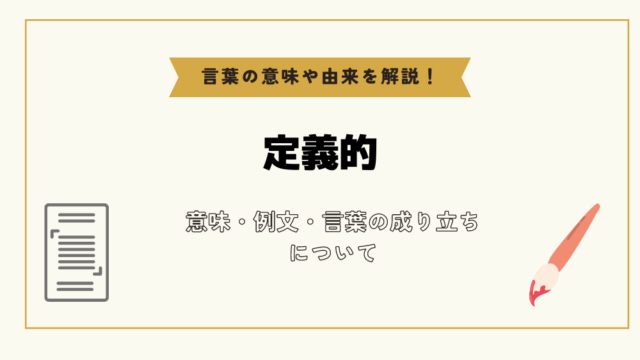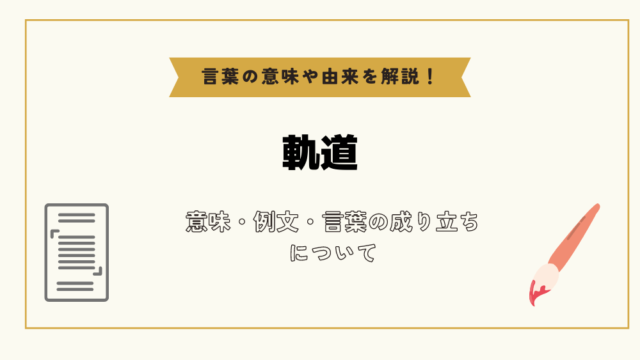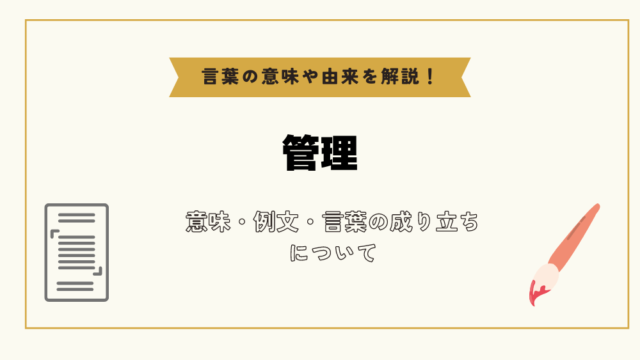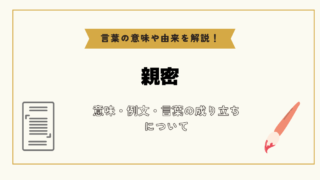「説明」という言葉の意味を解説!
「説明」は、物事の内容や理由を相手に分かるように述べる行為を指す名詞です。対象は概念・事実・手順など多岐にわたり、聞き手の理解を助けることが目的となります。現代ではプレゼンテーションや教育現場、ビジネス文書などで日常的に用いられています。
説明の語義は「説いて明らかにする」ことで、単に情報を列挙するだけでなく、全体像や因果関係を整理し、相手の疑問を解消させる役割を担います。文脈によっては「解説」「案内」とほぼ同義で扱われることもあります。
説明は「何を・なぜ・どのように」の三点を明確にすることで、相手の納得を引き出すコミュニケーション技法でもあります。
言語学では、説明文は「主題提示」「展開」「まとめ」の三部構成を取ることが多いと分析されます。つまり、最初にテーマを示し、次に理由やデータで補強し、最後に要点を再提示する流れです。
【例文1】彼は新サービスの仕組みを分かりやすく説明した。
【例文2】先生は歴史的背景を丁寧に説明し、生徒の理解を深めた。
「説明」の読み方はなんと読む?
「説明」は音読みで「せつめい」と読みます。訓読みは一般に存在せず、熟語として専ら音読みで用いられるのが特徴です。
「説」は「と(く)」の訓読みを持ちますが、「説に立つ」など特殊な場合を除き、日常語の「説明」では訓読みは使われません。「明」は「あきら(か)」とも読みますが、熟語中では「めい」と読むことで音読みが定着しています。
日本語教育では、小学四年生で「説」を、五年生で「明」を学習漢字として習いますが、「説明」という熟語自体は中学国語の語彙として扱われることが多いです。
読み方は一種類のみのため、ビジネスメールや公式文書で誤読や表記ゆれが起こりにくい語といえます。
【例文1】お客様に対して契約内容を「せつめい」します。
【例文2】「せつめい」が不足すると誤解が生じる。
「説明」という言葉の使い方や例文を解説!
説明は動詞化して「説明する」と使うのが最も一般的です。名詞としては「詳細な説明」「適切な説明」という修飾語を伴い、形容詞的な働きもします。
ビジネスでは、提案資料に「要点説明」という見出しを設け、概要を短時間で伝えるスタイルが定着しています。一方、学術論文では「方法の説明」「結果の説明」と章立てすることで、読者が情報を検索しやすくしています。
場面に応じて「説明の量と深さ」を調整することが、相手の理解度を高めるコツです。
敬語表現としては「ご説明いたします」「ご説明申し上げます」が代表的です。社外向けには丁寧語と尊敬語を併用し、社内向けでは簡潔な常体を使い分けると良いでしょう。
【例文1】資料に沿ってご説明いたします。
【例文2】手順が複雑なので改めて説明してください。
「説明」の類語・同義語・言い換え表現
説明の代表的な類語には「解説」「説明書き」「案内」「プレゼンテーション」「インストラクション」があります。いずれも情報を整理し相手に伝える点で共通していますが、用途やニュアンスが少しずつ異なります。
「解説」は専門的・技術的な内容を詳しく述べる場合に多用されます。「案内」は場所や手続きなど、行動を促す情報伝達に使われます。「プレゼンテーション」は聴衆を説得する目的が強く、視覚資料との併用が前提となることが多いです。
言い換えを選ぶ際は「情報の深さ」と「相手の期待」を意識すると、文章に説得力が増します。
「教示」「指導」「レクチャー」なども目的が共有化されやすい環境で使用される類語です。翻訳分野では「explanation」「description」など英語の対応語を選ぶ際、テクニカルライティングでは区別が重要です。
【例文1】製品の使用方法を解説した。
【例文2】来場者をロビーに案内する。
「説明」の対義語・反対語
説明の反対語として一般に挙げられるのは「省略」「黙秘」「隠蔽」「略述」「無言」などです。いずれも情報を十分に提示しない、あるいは伝達を意図的に控える行動を表します。
たとえば「省略」は冗長な部分を切り捨てる意図が強く、「黙秘」は法的・倫理的な理由で口を閉ざす状況を示します。「隠蔽」は事実を隠す行為であり、倫理的問題を含む場合があります。
対義語との対比を意識することで、説明の意義がより鮮明になり、情報開示の重要性を再確認できます。
【例文1】時間の都合で詳細を省略した。
【例文2】彼は事故原因について黙秘した。
「説明」についてよくある誤解と正しい理解
「説明=長く丁寧に話せば良い」という誤解が広がりがちですが、実際は「必要十分な情報を端的に伝える」ことが最優先です。長すぎる説明は聞き手の集中力を奪い、内容理解を阻害します。
また、「専門用語を多用すると賢く見える」という思い込みも誤解の一つです。専門用語は相手が理解できると分かっている場合にのみ効果的で、そうでなければ平易な語への置き換えが望ましいです。
説明とは相手の理解を助ける行為であり、自分が話したいことを並べる場ではないという原則を忘れてはいけません。
【例文1】専門用語ばかりで説明されても理解できない。
【例文2】短い説明でもポイントが押さえられていれば伝わる。
「説明」を日常生活で活用する方法
日常会話でも説明力を高めることで、家族・友人・同僚とのコミュニケーションが格段にスムーズになります。例えばレシピの手順を説明する際は、「材料」「分量」「タイミング」の順に整理すると相手が実践しやすくなります。
タイムマネジメントの場面では、予定変更を説明する際に「変更理由」「影響範囲」「代替案」をセットで示すと納得感が得られやすいです。
日常的に「結論→理由→具体例」の型を意識すると、短時間で的確に説明できるようになります。
【例文1】買い物リストの必要性を家族に説明した。
【例文2】交通渋滞のため到着が遅れると友人に説明した。
「説明」という言葉の成り立ちや由来について解説
「説明」は「説」と「明」の二字から成る熟語で、いずれも中国古典に由来します。「説」は『説文解字』で「とく、ときあかす」と解され、「明」は「光を当ててはっきりさせる」を意味します。古代より、知識や真理を人に伝える行為を尊ぶ思想が背景にあります。
奈良時代に編纂された漢文訓読の仏典に「説明」の語が確認でき、僧侶が経の教義を弟子に説き明かす場面で用いられました。やがて平安期には公家の日記にも現れ、政治文書で採用されることで定着しました。
「説き明かす」という思想的背景が、近世の教育普及とともに庶民へも浸透し、今日の一般名詞としての「説明」が形作られました。
【例文1】古文書に「経義を説明す」と記されている。
【例文2】教義を説明する僧侶の姿が描かれている。
「説明」という言葉の歴史
江戸時代の寺子屋では、師匠が算術や往来物を「説明」することが教育の中心でした。明治期になると、西洋の「explanation」「description」の訳語として「説明」が公式に採用され、教科書編纂で広がりました。
大正期には法令用語としての「説明責任」が議会で議論され、昭和後期にメディアで普及します。現代の企業統治では「説明責任(アカウンタビリティ)」がガバナンスの基礎概念となり、語の重要度がさらに増しました。
歴史の中で「説明」は単なる言語行為から、社会的責任を伴うキーワードへと進化しました。
【例文1】明治政府は近代科学を説明する教材を作成した。
【例文2】取締役は株主に対して経営状況を説明した。
「説明」という言葉についてまとめ
- 「説明」とは物事の内容や理由を説き明かし、相手の理解を促す行為である。
- 読み方は「せつめい」と音読みのみで、表記ゆれがほぼない。
- 古代中国の思想に端を発し、日本では奈良時代から用いられてきた歴史がある。
- 現代ではビジネス・教育・法律など多分野で重視され、量と深さの調整が重要である。
説明は情報を整理し、相手の疑問を解消するための基本動作です。読み方は一択で、誤読の心配が少ないものの、内容と構成を誤ると誤解を招きます。
成り立ちを知ると、単なる言葉以上に深い文化的背景が見えてきます。歴史を踏まえたうえで、日常のちょっとした会話から重要なプレゼンまで、「必要十分でわかりやすい説明」を心がけていきましょう。