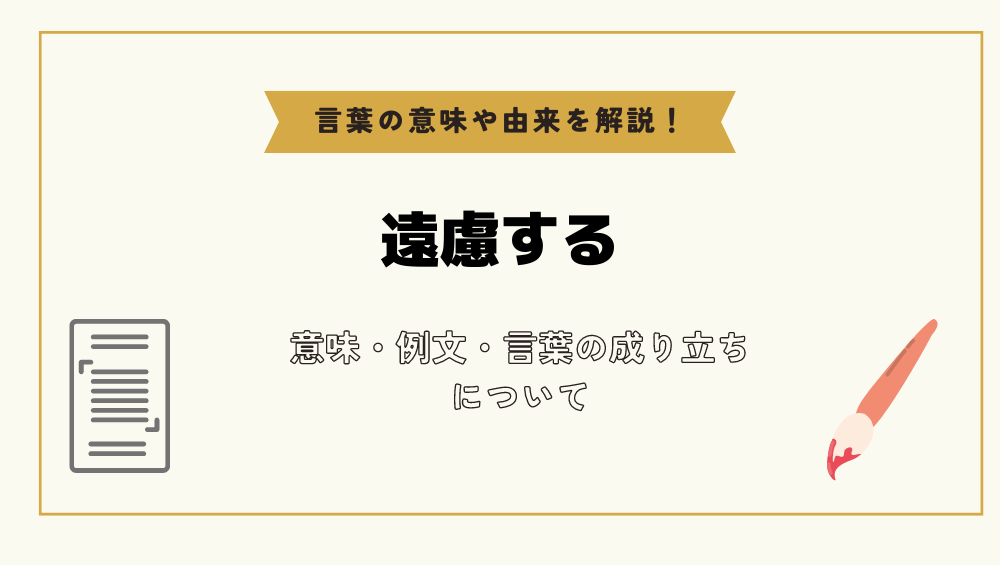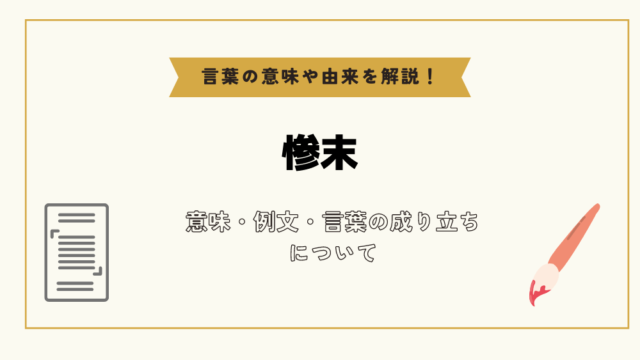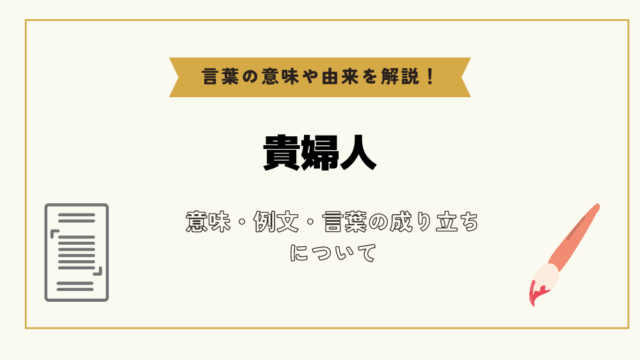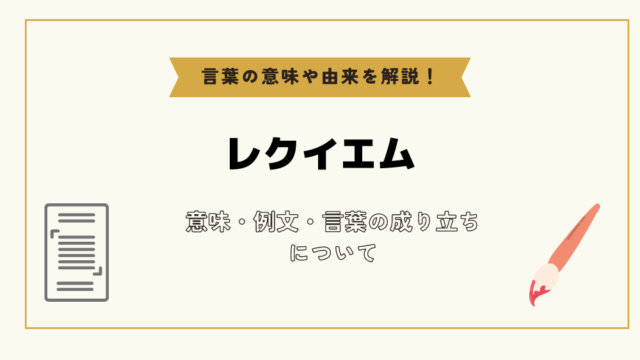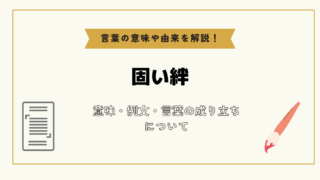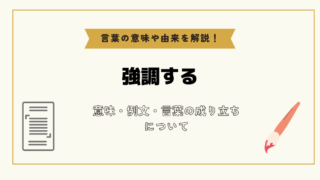Contents
「遠慮する」という言葉の意味を解説!
「遠慮する」という言葉は、他の人に対して配慮し、自分の意見や要望を控えることを指します。
つまり、相手に対して気を使い、お節介や迷惑をかけないようにすることです。
これは日本人の間柄を重んじる文化に根付いている言葉であり、相手を尊重するために用いられることが多いです。
「遠慮する」の読み方はなんと読む?
「遠慮する」は、「えんりょする」と読みます。
もともとは漢語であり、その発音は日本語の音読みになります。
多くの人がこの読み方を知っているため、コミュニケーションの場面で遠慮の意思を伝える際には、この言葉を使用することが一般的です。
「遠慮する」という言葉の使い方や例文を解説!
「遠慮する」という言葉の使い方は様々ですが、主に相手の要望や意見に対して控えめな態度を取ることを指します。
例えば、友人から食事に誘われた際に、「いいですよ。
でも、私が遠慮しておごらせていただきます」と言うのは一般的な使い方です。
また、会議で自分の意見を言いたいときに、周りの人が既に意見を述べている場合には、「遠慮してお聞きしておきます」と言って意見を控えることもあります。
「遠慮する」という言葉の成り立ちや由来について解説
「遠慮する」という言葉は、元々は中国で生まれた言葉です。
中国の伝統的な尊敬の心を表す言葉であり、日本にも漢字として伝わりました。
その後、日本独自の文化に合わせて使われ方が変化し、相手を思いやる行動を指すようになりました。
遠慮の文化は日本独特のものであり、日常生活において大切な価値観となっています。
「遠慮する」という言葉の歴史
「遠慮する」という言葉は、奈良時代に中国から日本に伝わりました。
当時は、貴族の間で礼儀作法として使われていました。
しかし、平安時代に入ると広まり、庶民の間でも一般的になりました。
江戸時代になると、遠慮の意識がより強まり、相手を思いやる心が重んじられるようになりました。
その結果、遠慮することが美徳とされ、日本人の特徴的な行動様式となりました。
「遠慮する」という言葉についてまとめ
「遠慮する」という言葉は、他の人に対して気を使い、自分の意見や要望を抑えることを指します。
相手を思いやる心があり、日本人の価値観とも密接に結びついています。
遠慮の文化は古くから存在し、日本の歴史や伝統にも深く根付いています。
普段のコミュニケーションやビジネスの場でも、相手を思いやる態度を大切にすることが求められます。