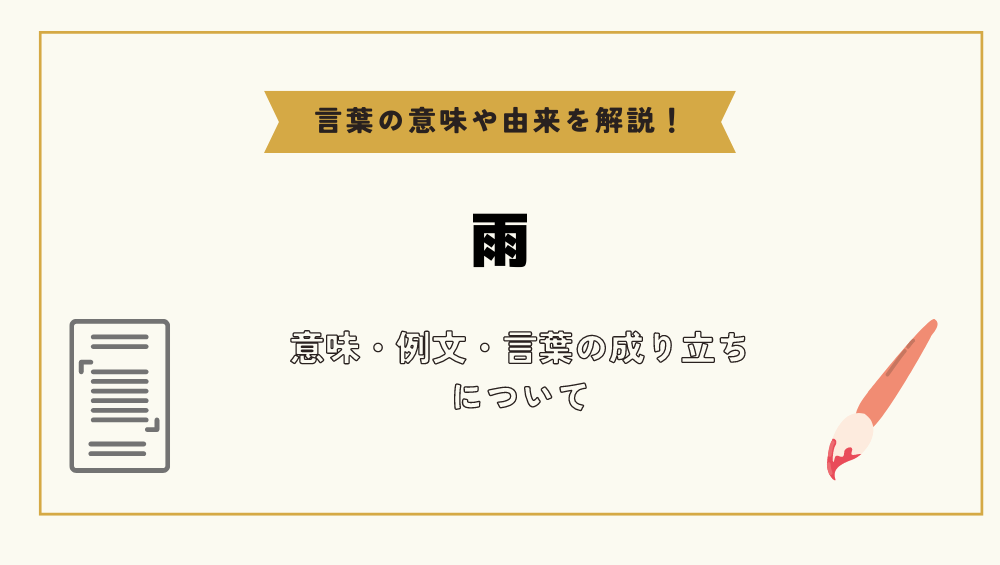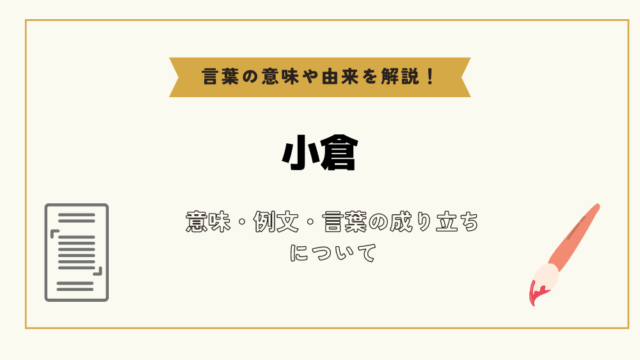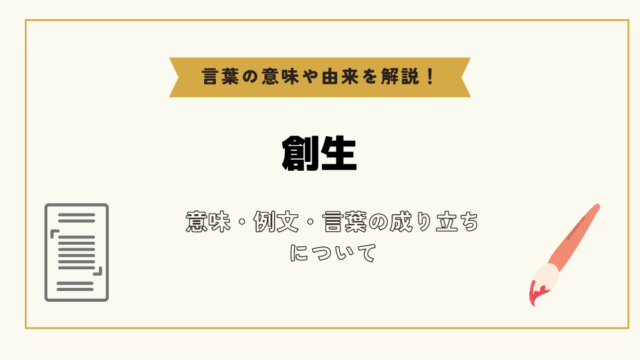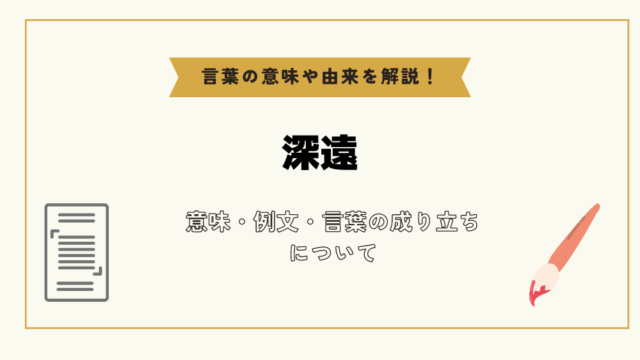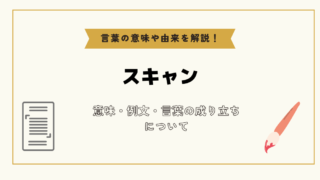Contents
「雨」という言葉の意味を解説!
雨(あめ)という言葉は、空から降る水の粒や水滴を指す名詞です。
普通、雨は雲の中で水蒸気が冷やされて水滴となり、地上に降り注ぐ現象のことを指します。
雨は植物の成長や農作物の育成に欠かせない恵みのひとつでもあります。
また、雨は涙とも関連があり、人間の感情や心情を表す隠喩としても使われることもあります。
「雨」という言葉の読み方はなんと読む?
言葉「雨」は「あめ」と読みます。
この読み方は親しみやすく、日本人にとってなじみのある読み方です。
日本語の基本的な発音ルールに従っており、「あ」と「め」という音が組み合わさっています。
「雨」という言葉の使い方や例文を解説!
「雨」の使い方はさまざまです。
例えば、「雨が降っているので傘を持って行きましょう」というように、雨の有無によって行動する際に使用されます。
また、「雨に濡れながら遠足に行った」というように、雨を経験した状況を表現することもあります。
このように、雨は日常生活において頻繁に使われる言葉です。
「雨」という言葉の成り立ちや由来について解説
「雨」という言葉の成り立ちや由来については複数の説がありますが、明確なことは分かっていません。
ただし、古代日本の言葉である「あめ(天女)」という語と関連していると考えられることがあります。
天女は雨を司る存在として信じられており、その信仰が言葉と結びついて「雨」という言葉が生まれたのかもしれません。
「雨」という言葉の歴史
「雨」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や歌にも頻繁に登場します。
万葉集や古今和歌集などの古典的な作品には、雨を詠んだ詩や歌が多く含まれています。
また、雨は風情を感じさせる自然現象としても重要視され、日本の美意識や文化にも深く根付いています。
「雨」という言葉についてまとめ
「雨」という言葉は、空から降り注ぐ水の粒を指す言葉です。
雨は自然現象としてだけでなく、人々の感情や心情を表現する隠喩としても使用されます。
その由来や成り立ちについては諸説ありますが、古代の天女信仰と関連があると考えられています。
日本の古典文学や歌にもよく登場する言葉であり、日本の美意識や文化に深く根付いた存在です。