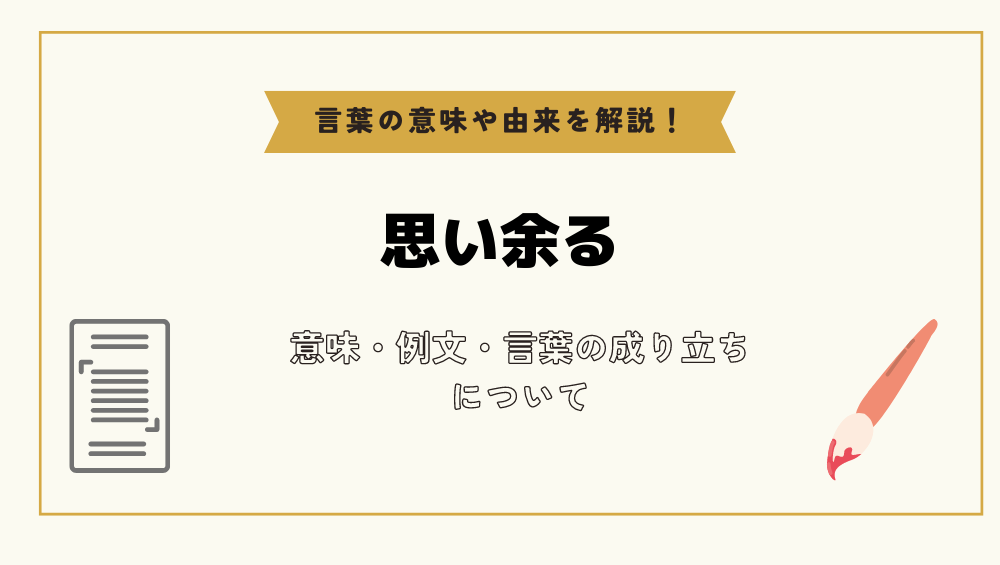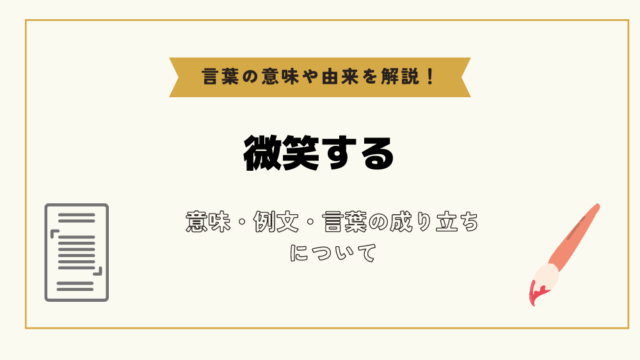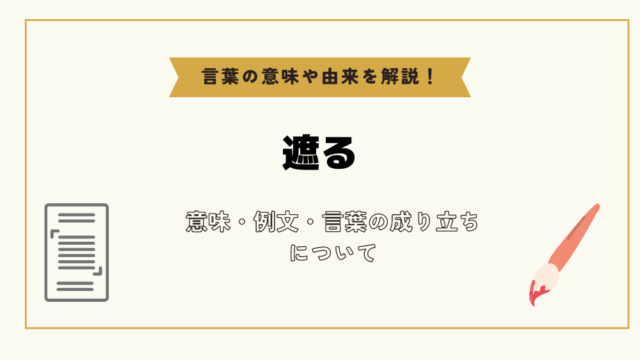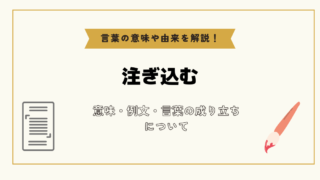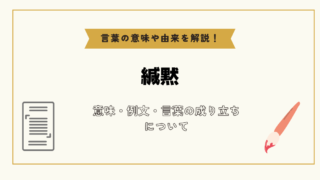Contents
「思い余る」という言葉の意味を解説!
「思い余る」という言葉は、物事や感情が自分の制御を超えて溢れるさまを表現する表現です。
何かに対して非常に感銘を受けたり、考えが膨らんでしまったりする様子を指します。
「思うよりも余計に感じる」とも言えるでしょう。
「思い余る」という言葉の読み方はなんと読む?
「思い余る」という言葉は、「おもいあまる」と読みます。
いかにも愛嬌のある読み方ですよね。
この読み方を知っているだけでも会話の中で披露することで、相手に親近感を与えることができるでしょう。
「思い余る」という言葉の使い方や例文を解説!
「思い余る」という言葉は、感動や感謝の気持ちを表現する場合によく使われます。
仕事での成功や友人からのサプライズなど、思わず胸が踊ったり、感激したりする瞬間に用いられることが多いです。
「あの映画を観て、思い余ってしまいました!」と言うことで、自分の感動を周囲に伝えることができます。
「思い余る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「思い余る」という言葉は、一見すると漢字の組み合わせから成り立っているように思えますが、実は漢字の合成語ではありません。
元々は口語表現であったため、そのままひらがなで表記されています。
日本語は表現豊かな言語であり、このように自由に新しい言葉を作り出すことができるのが特徴です。
「思い余る」という言葉の歴史
「思い余る」という言葉は、古くは平安時代から存在していたと言われています。
当時は、文学や歌において感情の奔流や思うままに巻き起こる情念を表現するための言葉として使われていました。
時代が変わっても、その響きと意味深さは変わることなく受け継がれてきました。
「思い余る」という言葉についてまとめ
「思い余る」という言葉は、感情の高ぶりや物事への感銘を表現する際に使われる表現です。
非常にパワフルで響きのある言葉であり、自分の感情や考えを表現する際に使うと相手に強い印象を与えることができます。
ぜひ積極的に使ってみてください。