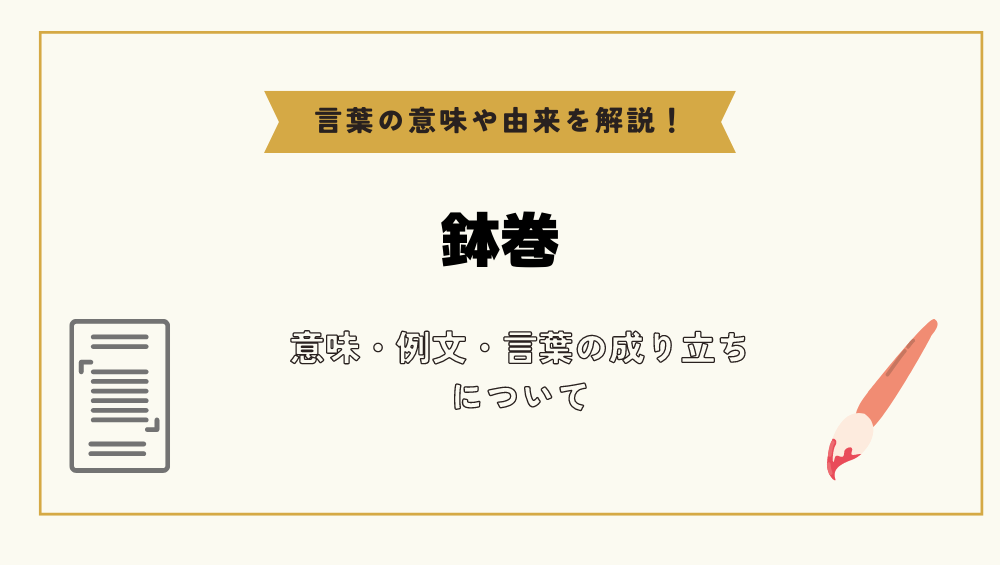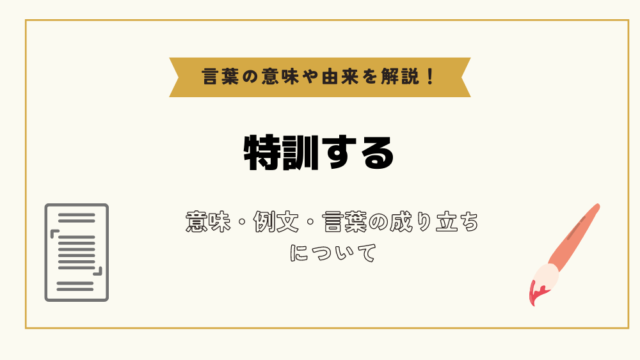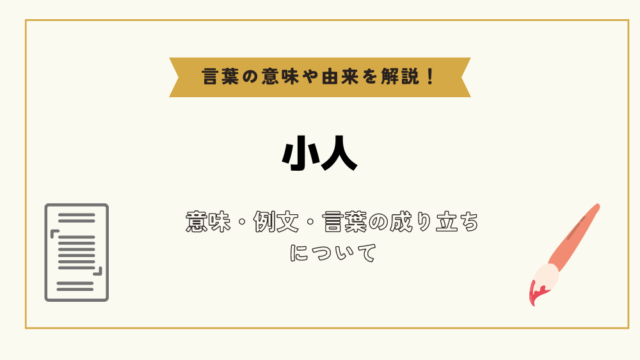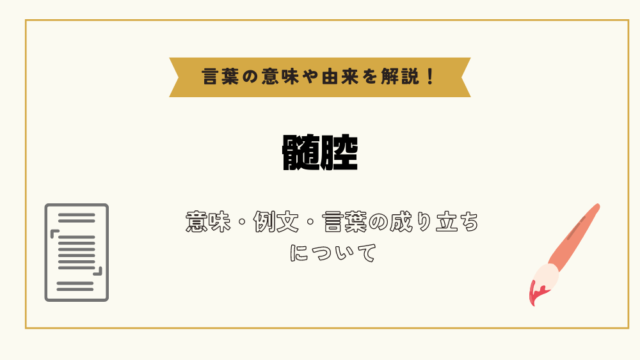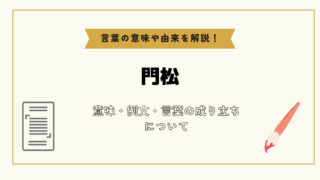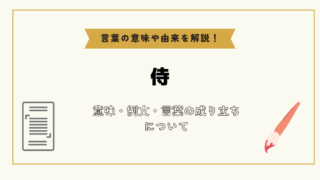Contents
「鉢巻」という言葉の意味を解説!
「鉢巻」とは、頭につける装飾品の一つであり、主に武道やスポーツの際に使用されます。
鉢巻は、頭を守るために使用されることがありますが、その目的は単に機能的なものだけではありません。
鉢巻には、勇気や力強さの象徴としての意味も込められています。
そのため、鉢巻は多くの人々にとって大切なアイテムとなっています。
「鉢巻」の読み方はなんと読む?
「鉢巻」は、「はちまき」と読みます。
この読み方は、一般的なものであり、日本語の学校教育やメディアなどでもよく使用されている表現です。
「はちまき」という言葉は、日本文化に深く根付いており、多くの人々に馴染みのある言葉です。
「鉢巻」という言葉の使い方や例文を解説!
「鉢巻」という言葉は、特に武道やスポーツの分野で頻繁に使用されます。
例えば、柔道や空手などの武道では、選手たちは試合中に鉢巻を着用します。
「鉢巻を巻く」や「鉢巻をつける」という表現が一般的であり、どちらも同じ意味で使われます。
また、勇壮な姿勢や団結を象徴するために、鉢巻を応援グッズとして利用することもあります。
「鉢巻」という言葉の成り立ちや由来について解説
「鉢巻」という言葉は、その形状から名付けられました。
鉢巻の形は、鉢(はち)のような形状をしており、このことから「鉢巻」と呼ばれるようになったのです。
「巻」という言葉は、布や紐を巻くという意味を持ちます。
頭に巻き付ける形状のため、「鉢巻」という名前が付けられたのです。
「鉢巻」という言葉の歴史
鉢巻の歴史は古く、日本の武道や伝統に深く関わっています。
過去には、武士や武術家などが鉢巻を着用していたことが記録に残っています。
その後、鉢巻はスポーツや学校の体育活動などにも広まり、多くの人々に愛されるようになりました。
現代では、鉢巻は日本独特のアイテムとして世界中で認知されています。
「鉢巻」という言葉についてまとめ
「鉢巻」とは、勇気や力強さの象徴として使用される頭につける装飾品です。
武道やスポーツの際に使用されることが一般的であり、その使い方や意味は幅広く存在します。
日本文化において深い意味を持つ「鉢巻」という言葉は、多くの人々に愛される存在です。