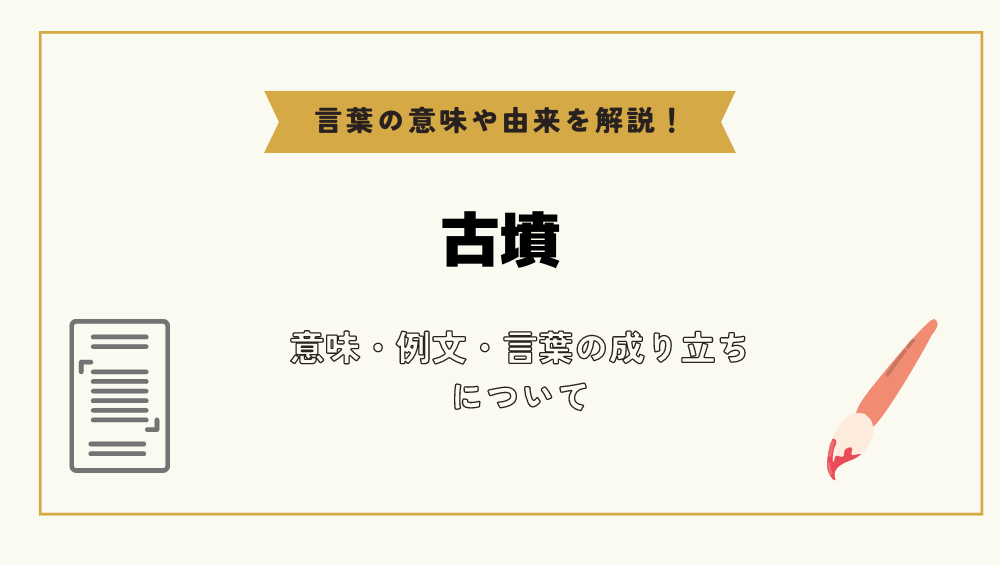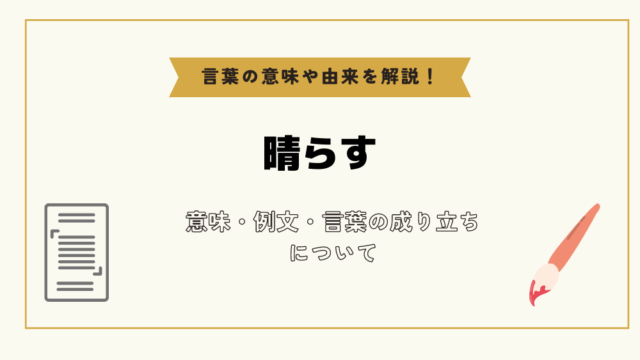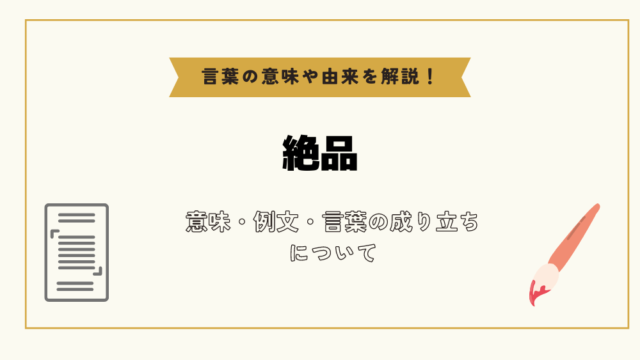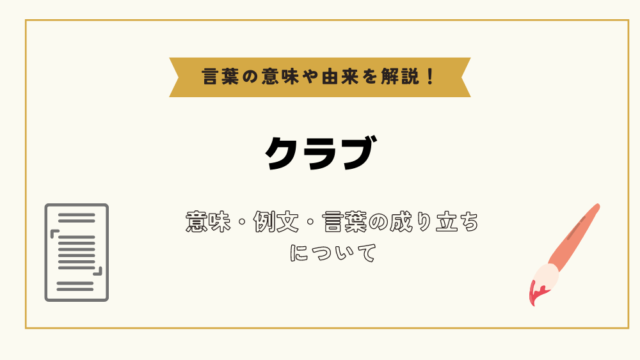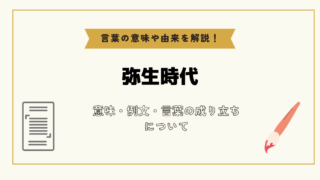Contents
「古墳」という言葉の意味を解説!
「古墳」という言葉は、日本において古代の墳墓を指す言葉です。
具体的には、古代の王や豪族のために築かれた巨大な墓のことを指します。
これらの墳墓は、縄文時代末期から弥生時代にかけて築かれ、古代の日本の社会や文化を知る上で重要な要素となっています。
「古墳」の読み方はなんと読む?
「古墳」は、日本語の「こふん」という読み方で表されます。
この読み方は一般的で広く使われています。
古墳は日本古代の王墓や豪族の墓であり、その存在は日本の古代史を学ぶ上で非常に重要なものです。
「古墳」という言葉の使い方や例文を解説!
「古墳」という言葉は、古代の日本の墓や墳墓を指す際に使用されます。
例えば、「昔、この地域にはたくさんの古墳があった」というように使います。
また、「日本の古墳は世界的にも注目されている」というように、古墳の特徴や重要性について語る際にも使われます。
「古墳」という言葉の成り立ちや由来について解説
「古墳」という言葉は、古代の墳墓を指すために用いられるようになりました。
日本における古墳は、古代の王や豪族のために築かれたものであり、その存在は古代日本の社会や文化を理解する上で非常に重要です。
このような墳墓が「古墳」という名前で呼ばれるようになった経緯は明確ではありませんが、古墳の存在は古代日本の歴史を知る上で欠かせない要素です。
「古墳」という言葉の歴史
「古墳」という言葉が使われるようになったのは、江戸時代以降のことです。
その頃になると、古代の墳墓に関心が寄せられるようになり、古墳の調査や研究が盛んに行われるようになりました。
そして、この頃から「古墳」という言葉が一般的に使われるようになりました。
「古墳」という言葉についてまとめ
「古墳」という言葉は、古代の王や豪族のために造られた墳墓を指す言葉です。
日本における古墳は、古代の社会や文化を理解する上で重要な要素であり、古代日本の歴史を知る上で欠かせないものとなっています。
古墳の存在は、日本の古代史や遺跡学の研究においても重要な役割を果たしています。