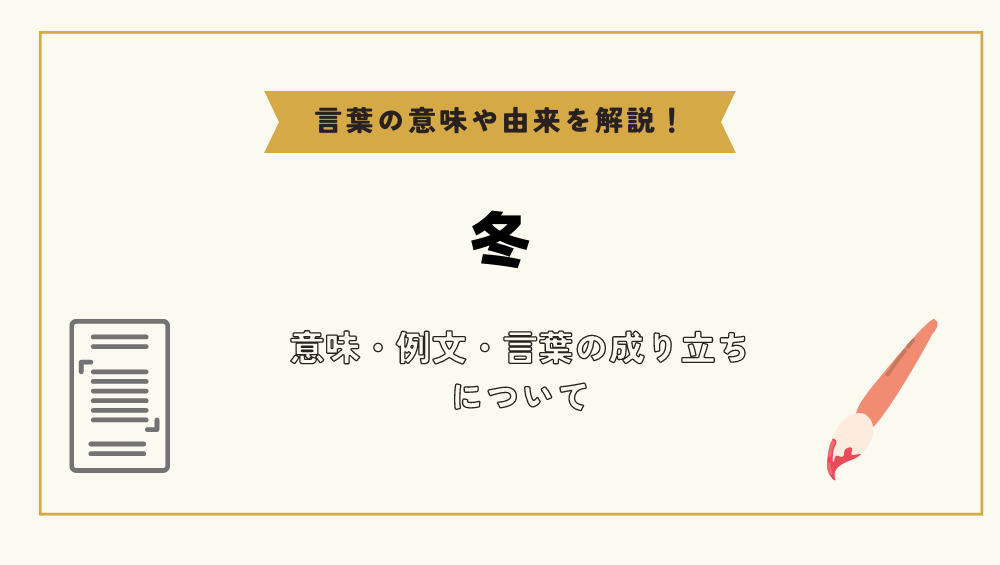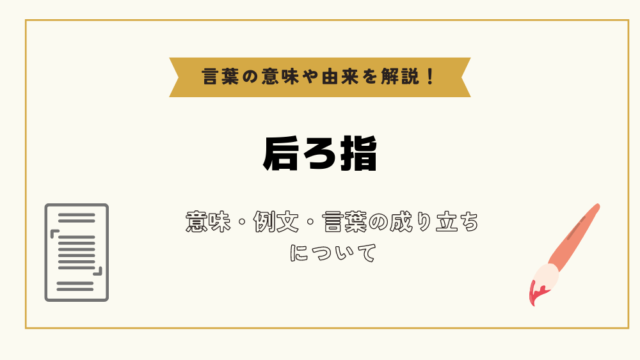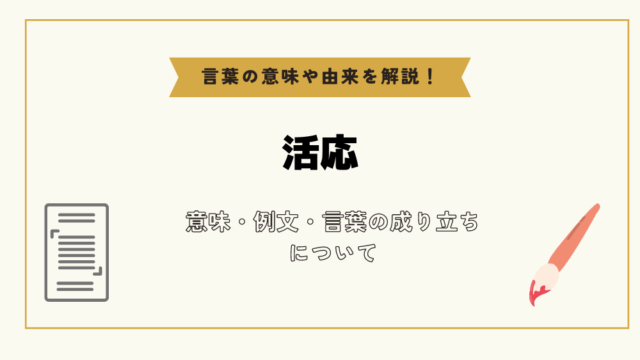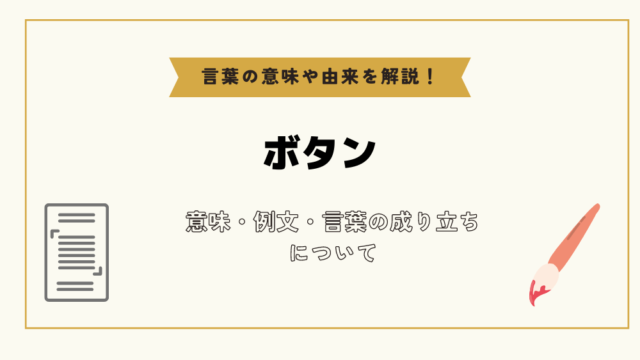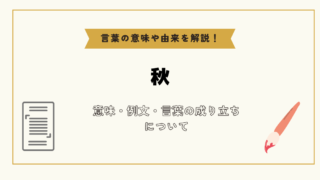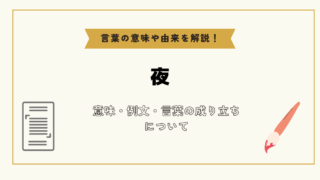Contents
「冬」という言葉の意味を解説!
「冬」という言葉は、四季の一つで、寒さが厳しくなり、雪や霜が降り積もる季節を指します。
寒い季節であることから、人々は冬の訪れを感じると同時に、温かい服や暖房器具などを用いて体を守ります。
「冬」という言葉の読み方はなんと読む?
「冬」という言葉は、「ふゆ」と読みます。
この読み方は日本語において一般的なものであり、最も一般的な読み方とされています。
他にも「とう」と読む地域もありますが、全体的には「ふゆ」という読み方が主流です。
「冬」という言葉の使い方や例文を解説!
「冬」という言葉は、季節を表現するときや寒さを指すときによく使用されます。
例えば、「冬の寒さに耐える」といった表現や、「冬服を着る」といった使い方があります。
また、「冬至」や「クリスマス」など、冬に関連するイベントや行事を表すときにも使用されます。
「冬」という言葉の成り立ちや由来について解説
「冬」という言葉は、古代中国の言葉である「陰」と「冬」を組み合わせたものです。
古代中国では、「陰」は陰陽思想に基づいて陰性・陰暗な要素を指し、「冬」は寒さや凍りついた状態を表す言葉でした。
これが日本に伝わり、「冬」という言葉が広まっていきました。
「冬」という言葉の歴史
「冬」という言葉の歴史は古く、日本の古代文献にも登場します。
古代の人々は、冬の訪れとともに寒さに耐え、生活の工夫を凝らして過ごしてきました。
また、冬には農業の作業が一段落し、人々は家族や友人と共に過ごす時間を大切にしてきました。
「冬」という言葉についてまとめ
「冬」という言葉は、寒さが厳しくなる季節やその寒さを指す言葉として使われます。
また、冬には季節のイベントや行事も多くあり、人々の暖かい思い出も詰まっています。
季節の中で重要な役割を果たす冬には、寒さと温かさ、厳しさとやすらぎが共存しています。