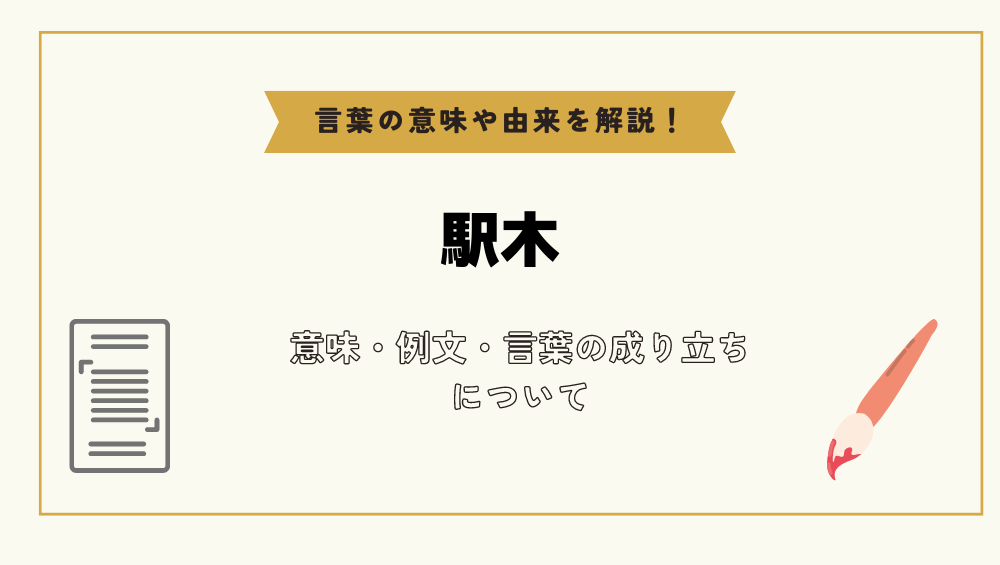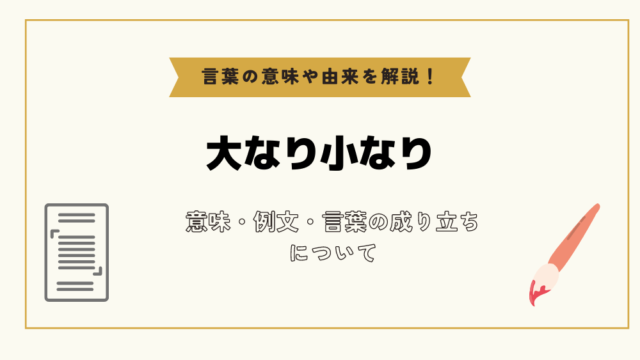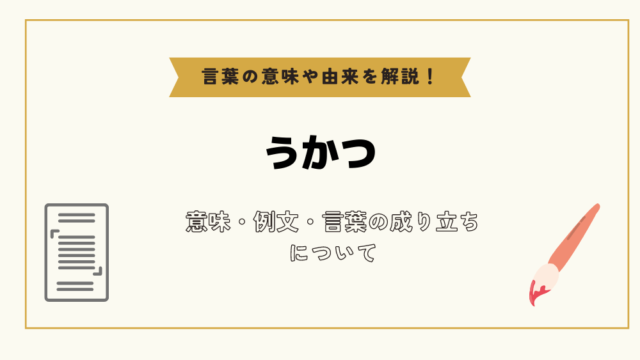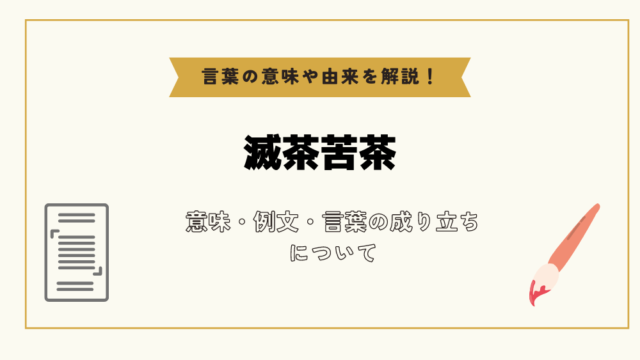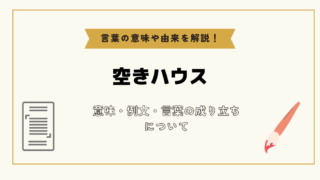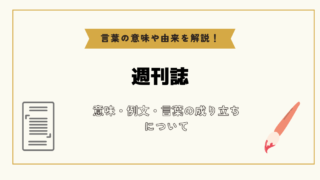Contents
「駅木」という言葉の意味を解説!
駅木とは、駅の周りや駅前に植えられる木のことを指します。
駅を訪れる人々に癒しや安らぎを提供するために、都市計画や景観整備の一環として植えられます。
駅木は緑の豊かさを持ち、都市の中でも自然を感じることができる貴重な存在です。
「駅木」という言葉の読み方はなんと読む?
「駅木」は、「えきぎ」と読みます。
日本語の読み方で「駅」は「えき」、「木」は「ぎ」と読まれます。
この言葉は、駅周辺に植えられる木を指すことから名付けられました。
「駅木」という言葉の使い方や例文を解説!
「駅木」は、駅周辺の環境を豊かにするために活用されます。
例えば、「新しい駅がオープンする際には、駅木の配置も考慮されます」と言うことができます。
また、「駅の待合室からは美しい駅木が見えるため、訪れる人々に心地良さを提供しています」とも言えます。
「駅木」という言葉の成り立ちや由来について解説
「駅木」の成り立ちは、日本の伝統的な景観造りの一環として始まりました。
駅周辺の環境を豊かにするために、都市計画や景観整備に取り組む中で、植栽の一環として駅木が生まれました。
これにより、都市の中でも自然を感じることができる場所が提供されました。
「駅木」という言葉の歴史
「駅木」の歴史は古く、明治時代から存在しています。
当時は主に松や桜などの木が植えられ、駅周辺の風景を彩っていました。
近年では、多様な種類の木や樹木が使われるようになり、駅周辺の環境がより豊かになっています。
「駅木」という言葉についてまとめ
「駅木」とは、駅の周りや駅前に植えられる木のことを指します。
駅木は都市の中において、自然との触れ合いを提供する貴重な存在です。
その歴史は古く、日本の伝統的な景観造りの一環として発展しました。
駅を訪れる人々に癒しや安らぎを与える一方で、都市の美しい景観を演出します。
駅木は、私たちの生活を豊かにする存在として大切にされています。