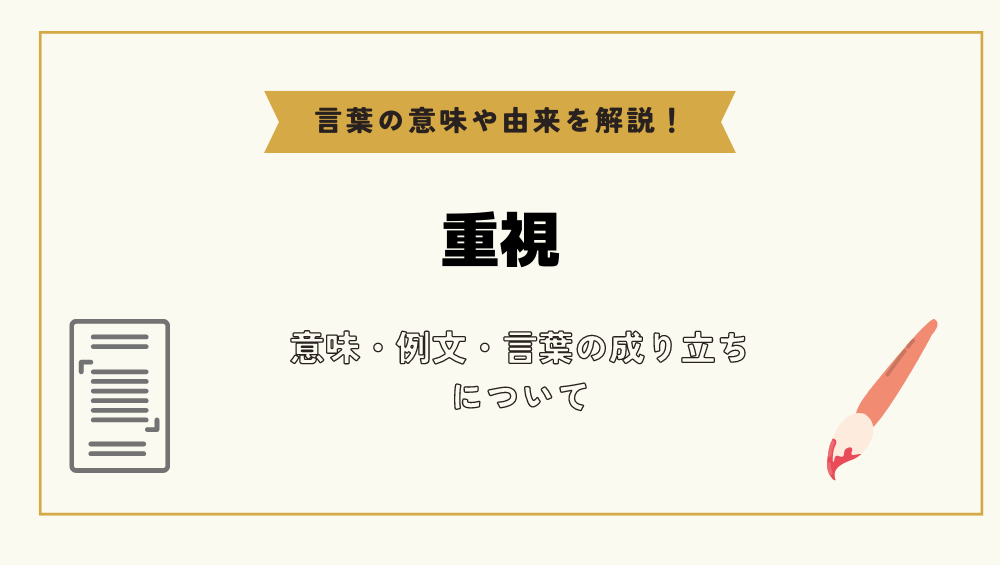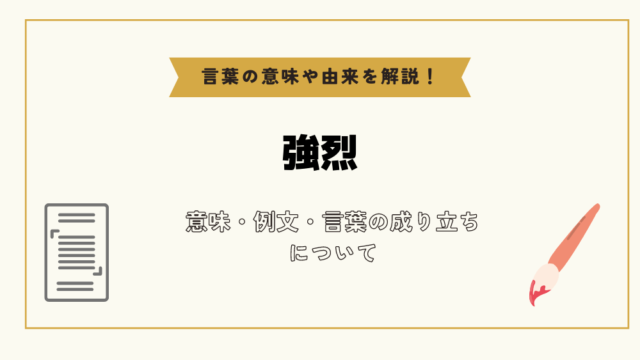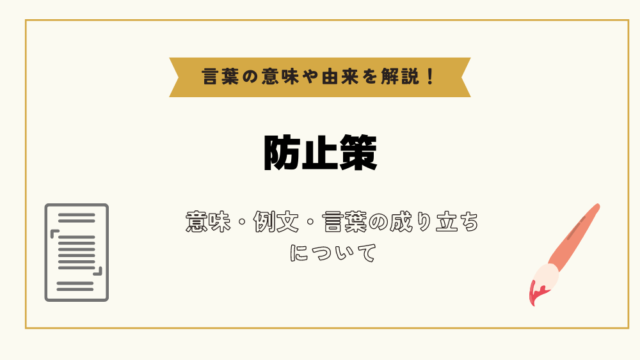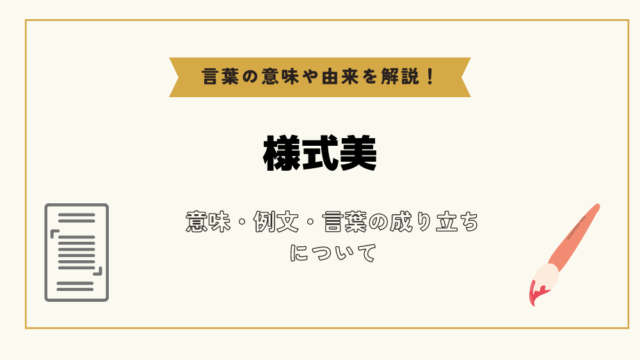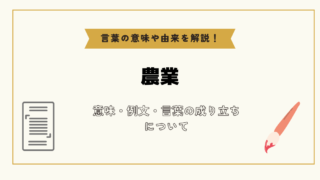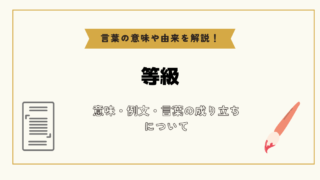「重視」という言葉の意味を解説!
「重視」とは、数ある要素の中で特に重要だと考え、優先的に扱うことを指す言葉です。ある対象を“重く見る”ことから転じて、“軽んじない”“大切に取り扱う”というニュアンスが含まれます。ビジネスで成果を重視すると言えば、成果を最優先で評価軸に置く姿勢を示します。反対に、コストを重視しないという表現は「コストより別の要素を優先する」ことを意味します。\n\n「重」という文字には「おもい・かさねる」の意があり、「視」は「みる」を表します。この二字が組み合わさり、“重く見て注視する”というイメージが生まれました。日常会話から学術論文、行政文書に至るまで幅広い場面で用いられる汎用性の高い言葉です。\n\n単なる「大事」との違いは、比較対象の存在が前提となり、その中で優先順位を示す点です。たとえば「健康は大事」の場合は重要性の強調にとどまりますが、「健康を重視する」と言えば「健康を第一に据える」という優先度のニュアンスがより明確になります。\n\n「重視」は抽象的な概念にも具体的な事柄にも使えるため、複数の要素を扱う場面で便利なキーワードとなっています。\n\n\n。
「重視」の読み方はなんと読む?
「重視」は音読みで「じゅうし」と読みます。訓読みや特殊読みは存在せず、基本的には“ジューシ”という四拍の発音が一般的です。アクセントは東京式では「ジュ↑ーシ→」と平板に発音されることが多いですが、文脈や地域によってやや高低が変わることもあります。\n\nひらがなで表記する場合は「じゅうし」、カタカナだと「ジュウシ」となります。いずれも公用文では漢字表記が推奨されますが、ルビやふりがなを添えて可読性を高めるケースも少なくありません。\n\n読みの間違いとして「ちょうし」「おもし」などが稀に見られますが、正式には「じゅうし」です。論文や公的文書で誤読を避けるためにふりがなを併記する配慮が行われることもあります。\n\n\n。
「重視」という言葉の使い方や例文を解説!
「重視」は動詞「重視する」の形で使用され、「〜を重視する」「〜を最も重視する」など目的語を取って用います。複数の要素を列挙して一つを強調する場面に適しており、文章にメリハリを付けられるのが特徴です。\n\n【例文1】私は健康を重視して野菜を多く食べる\n【例文2】企業は顧客満足度よりも短期的な利益を重視した\n【例文3】安全性を重視するなら、この素材の採用が望ましい\n\nビジネスメールでは「弊社は品質を重視しております」のように丁寧語で使用されます。対外文書では「〜を最も重視する所存です」といったフォーマルな表現も可能です。\n\n会話では「○○重視だよね」と略式に使われることもあり、文体によって柔軟に変化させられる点が利点です。\n\n\n。
「重視」という言葉の成り立ちや由来について解説
漢字の配置から見れば、「重」は“おもい”“かさねる”を示し、「視」は“みる”ことを表しています。中国古典では「重視」は「重大視」と同義で、物事の重要度を量る表現でした。日本には漢字文化が伝来した奈良〜平安期にかけてこの熟語が入り、律令制度の文書で確認できるのが最古の例とされています。\n\n当初は政治・軍事に関する議論で「軍備を重視すべし」のように使われ、武家政権期にも「礼法ヲ重視ス」といった用例が見られます。時代が下るにつれ、庶民の生活にも浸透して教育・商取引など多方面で用いられるようになりました。\n\n「重く見る」という和語に漢語が対応した結果、抽象度の高い意識を表現する便利な語として定着したのです。\n\n\n。
「重視」という言葉の歴史
近世以前の文献では「重視」は比較的硬い表現でしたが、明治期以降の近代化で使用頻度が急増しました。教育勅語の解説や新聞紙上で「教育を重視せよ」「工業化を重視する」など、多くのスローガンに登場します。\n\n昭和期の高度経済成長では「効率を重視する経営」が流行語のように語られ、平成には「ワークライフバランスを重視」という新しい価値観が脚光を浴びました。時代の要請に合わせて「重視」される対象が変化しつつも、常に“優先順位”を示すキーワードとして機能してきたことが歴史的特徴です。\n\n現代ではSDGsやESG投資など国際的な枠組みの中で「環境を重視」「社会的責任を重視」といった用法が一般化しています。\n\nこのように「重視」という言葉は、社会の価値観を映す鏡としての役割も果たしてきました。\n\n\n。
「重視」の類語・同義語・言い換え表現
「重視」と近い意味を持つ語には「重要視」「重んじる」「優先する」「着目」「主眼」などがあります。文脈に応じて語感を調整することで、文章の硬さやニュアンスを自在に操れます。\n\nたとえば「重要視」はほぼ同義ですが、やや説明的でフォーマルな印象です。「重んじる」は古風な響きがあり、敬意や道徳的価値を込めたい場面に適しています。「優先する」は実際の順序や優位性をはっきり示すため、具体的な行動計画に向いています。\n\n「着目」は注意を向ける段階を示し、必ずしも優先度を表しません。「主眼」は目的の核として据えるという意味合いが強く、論文のタイトルで多用されます。\n\n同義語を適切に選ぶことで、文章の単調さを防ぎ、読み手の理解を深める効果が期待できます。\n\n\n。
「重視」の対義語・反対語
「重視」の反対概念は「軽視」「無視」「等閑(なおざり)」「軽んじる」などです。特に「軽視」は“重要だと認めない”態度を示すため、強い否定的ニュアンスが含まれます。\n\n「無視」は“存在しないものとして扱う”という点でさらに強い度合いを帯びますが、実務上は「軽視」とほぼ同域で用いられることもあります。「等閑」は古語的で雅な響きがあり、文学作品や評論文に登場します。\n\n対義語を理解することで、文脈に応じたコントラスト表現が可能となり、注意喚起や批判のニュアンスをより鮮明にできます。\n\n「重視か軽視か」という二項対立で議論を整理すると、論旨が明確になり読者に伝わりやすくなります。\n\n\n。
「重視」を日常生活で活用する方法
日々の選択に「重視」を取り入れると、優先順位が可視化され意思決定がスムーズになります。たとえば「時間を重視するから時短家電を購入する」と言語化するだけで、購買行動の根拠が明確になります。\n\n家計管理では「固定費削減を重視」と掲げると、取り組むべき支出が絞られます。人間関係でも「相手の感情を重視する」と決めれば、コミュニケーションの方針が定まります。\n\nスマートフォンのリマインダーや手帳に「今月は健康を重視」とメモしておくだけでも、行動の軸として機能します。\n\n“何を重視するか”を明文化する作業は、ライフプラン設計やキャリア形成にも有効です。\n\n\n。
「重視」に関する豆知識・トリビア
ビジネス用語として多用される「重視」ですが、実は法律条文にも頻繁に登場します。たとえば労働安全衛生法では「労働者の安全を重視する措置」といった表現で義務が規定されています。\n\n国会会議録(衆議院・参議院)を検索すると、年間で「重視」が数千回以上使われていることが確認でき、公的議論で不可欠なキーワードであることがわかります。\n\nまた、国語辞典によっては「じゅうじ」と読む誤用例が載せられており、読み間違いへの注意喚起がなされる珍しい語でもあります。情報工学では「重視度」という指標を用いて変数の重要度を定量化する手法が研究されています。\n\nこうしたトリビアを知っておくと、会話やプレゼンの小ネタとして役立ちます。\n\n\n。
「重視」という言葉についてまとめ
- 「重視」は複数要素の中で特に重要と考え優先的に扱うことを示す語。
- 読みは「じゅうし」で、基本的に漢字表記が推奨される。
- 中国古典由来で奈良〜平安期に日本へ渡来し、近代以降急速に一般化した。
- 現代では政策やビジネスから日常生活まで幅広く使われるが、軽視との対比で用法に注意が必要。
「重視」という言葉は、単に重要性を示すだけでなく、複数要素の優先順位を明確にする役割を担っています。読み方は「じゅうし」で固定されており、誤読を避けるためには場面に応じてふりがなを活用するのも良いでしょう。\n\n歴史的には中国から伝来し、公文書や学術分野で根付いた後、近代の産業化とともに一般社会へ広がりました。現在はSDGsやダイバーシティといった新しい価値観の文脈でも活発に用いられています。\n\n何を「重視」するかを自覚し、言語化することで、仕事や生活の質を高めるヒントが得られます。反対語や類語を使い分けながら、目的に応じた適切な表現を心がけましょう。