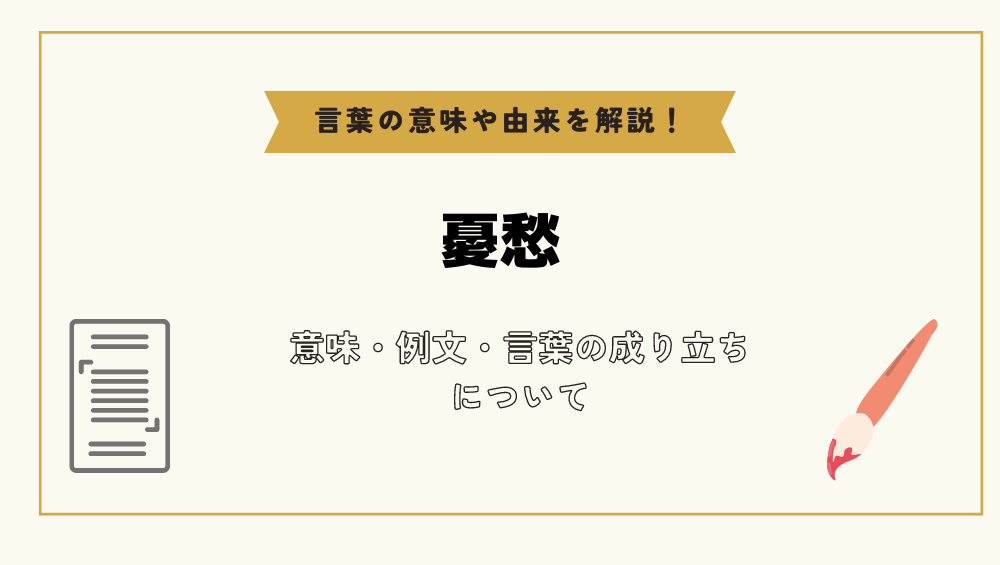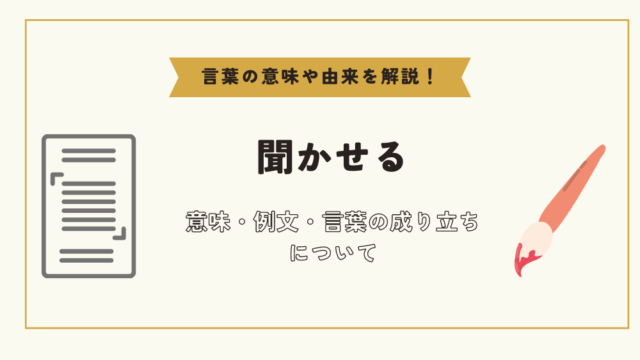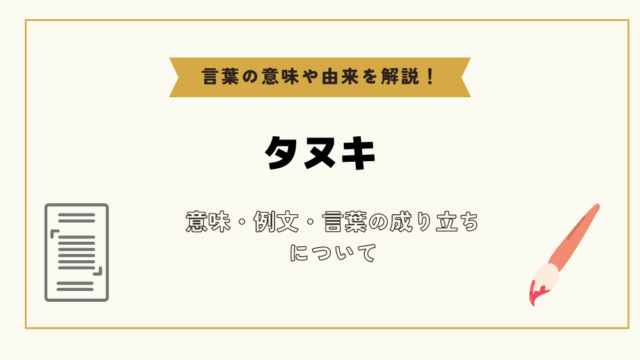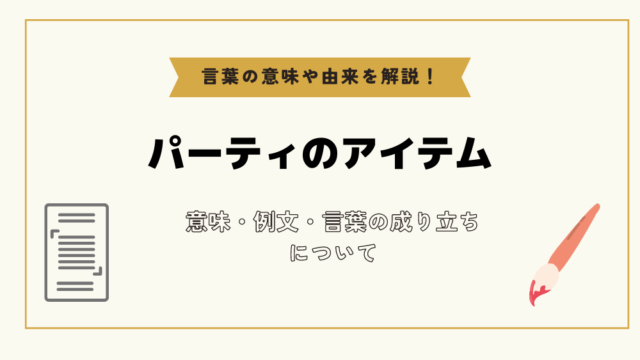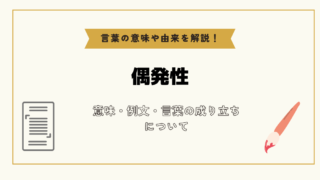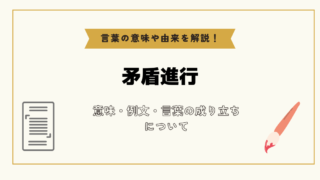Contents
「憂愁」という言葉の意味を解説!
「憂愁」という言葉は、ちょっと切なくて寂しい気持ちを表現する言葉です。
何かしらの失意や心の悲しみを抱えているときに使われることが多く、ノスタルジックで哀しい雰囲気を持っています。
憂愁
は、心に秘めた感情や思い出、過去の出来事から湧き上がる切なさや哀しみを指します。
人それぞれに憂愁を感じる場面や事情は違いますが、共感を呼ぶ言葉として多く愛されています。
「憂愁」という言葉の読み方はなんと読む?
「憂愁」という言葉は、「ゆうしゅう」と読みます。
これは、”ゆう”が「こゆう」と読むことがあるのと同じです。
日本語には様々な読み方がありますが、この読み方が一般的に使用されています。
「憂愁」という言葉の使い方や例文を解説!
「憂愁」という言葉は、詩や小説などの文学作品でよく使用されます。
たとえば、「彼女の美しい歌声には憂愁が漂っていた」というように、感情や雰囲気を表現する場合に使われます。
また、「彼は憂愁に暮れる日々を送っている」というように、個人の心情を表現する場合にも利用されます。
憂愁
は、繊細で儚い感情を表現する言葉として幅広く使われています。
ただし、明るい場面にはあまり合わないため、適切な使用場所を選ぶことが大切です。
「憂愁」という言葉の成り立ちや由来について解説
「憂愁」という言葉の成り立ちや由来については、明確な起源はありませんが、中国の古典文学においては「憂愁」という言葉が使われていることが知られています。
また、日本では明治時代から使われ始め、文壇でよく使用されるようになりました。
憂愁
は、その独特な響きと意味が人々に受け入れられ、広がっていった言葉と言えるでしょう。
「憂愁」という言葉の歴史
「憂愁」という言葉の歴史は古く、中国の古典文学には早くから使用されていました。
その後、日本でも明治時代から詩や小説などでよく使われるようになりました。
特に、明治から昭和初期にかけての文豪たちによって広められ、その人気は高まっていきました。
憂愁
は、日本の文学や詩において多く見られる言葉であり、その歴史も深いものとなっています。
「憂愁」という言葉についてまとめ
「憂愁」という言葉は、切なさや寂しさを表現する言葉であり、多くの文学作品で使用されています。
その読み方は「ゆうしゅう」となります。
個人の心情や詩的な表現に使われ、繊細で儚い雰囲気を持っています。
憂愁
は日本の文学や詩において多く見られ、明治時代からの歴史を持つ言葉です。
人々の心に響く言葉として愛されています。