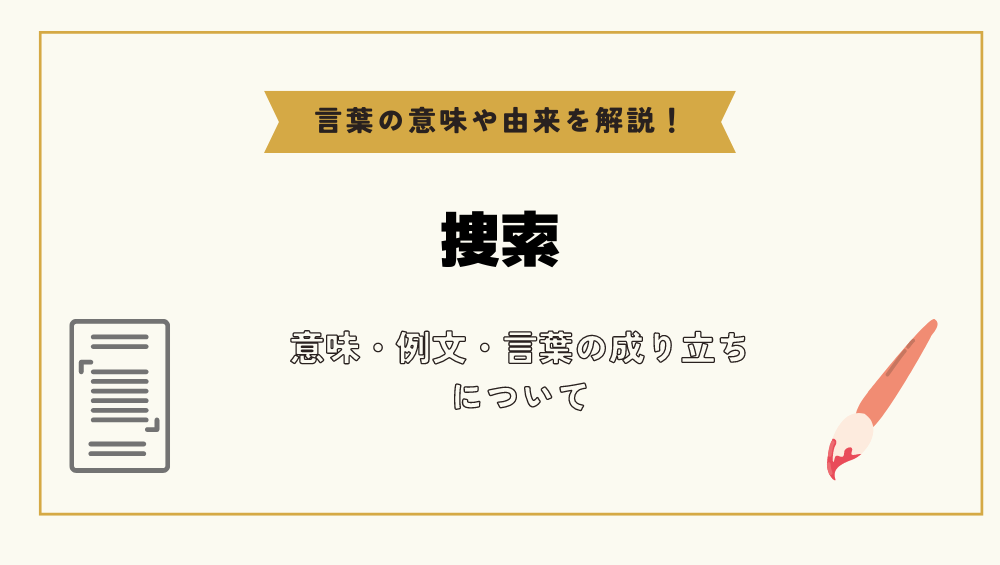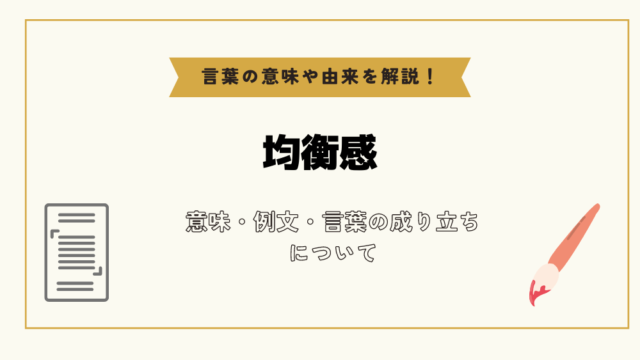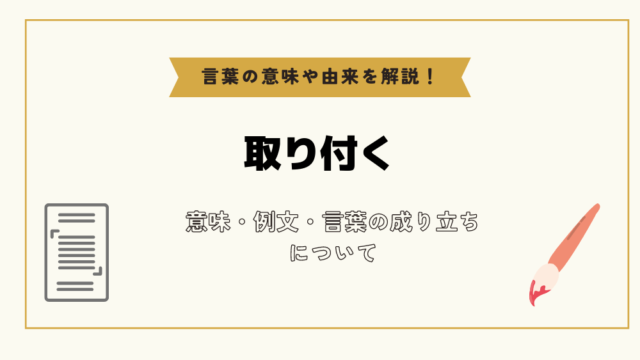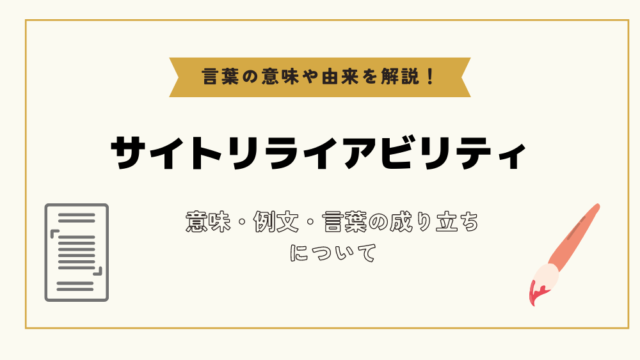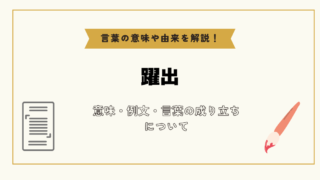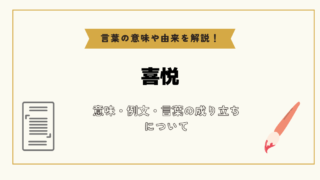Contents
「捜索」という言葉の意味を解説!
「捜索」とは、特定の目的や対象を見つけるために、注意深く調べたり探したりすることを指します。
また、何かを見つけ出すために情報を集めることや、複雑な場所や状況を探求することも含まれます。
捜索は、失われたものを見つけたり、問題を解決したり、真実を明らかにするために重要な手段となることがあります。
捜索とは、目的を果たすために努力を惜しまずに情報を探し求めることです。
「捜索」という言葉の読み方はなんと読む?
「捜索」という言葉は、「そうさく」と読みます。
この読み方は、一般的かつ正確な読み方です。
ただし、漢字の読み方は複数存在する場合がありますので、文脈に応じて適切な読み方をする必要があります。
例えば、「捜査」という言葉も「そうさ」と読まれることがありますが、捜索とは異なる意味となります。
ですので、文脈によっては正しく使い分けることが重要です。
「捜索」という言葉の使い方や例文を解説!
「捜索」という言葉は、主に法律や警察の分野で使われることが多いです。
例えば、「警察は容疑者の自宅を捜索し、証拠を押収した」や「事件の捜索範囲を広げるために、捜索隊は周辺を徹底的に探索した」といった表現があります。
また、ネット上で情報や資料を探す行為も「インターネットで情報を捜索する」と表現されることがあります。
捜索の対象が物理的なものから情報やデータへと広がっていることがわかります。
「捜索」という言葉の成り立ちや由来について解説
「捜索」という言葉は、古くから使われている言葉の一つです。
成り立ちは、「捜し」と「索(さく)」という漢字で構成されています。
「捜し」は「捜す」の連用形で、「索」は「探す」という意味を持つ漢字です。
江戸時代には、捜索の活動は主に城下町の治安維持や火災の防止のために行われており、その後も捜索の概念は拡がっていきました。
現代においても、刑事事件の捜査や迷子の捜索など、幅広い分野で活用されています。
「捜索」という言葉の歴史
「捜索」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学にも登場します。
古代文献である『万葉集』には、「捜し求める」という意味で使用されている句があります。
江戸時代以降、捜索の概念は法律においても重要視されるようになり、続く明治時代から現代に至るまで、捜索の方法や範囲の拡大が進んできました。
「捜索」という言葉についてまとめ
「捜索」という言葉は、情報や物事を探し求めるために行われる活動を指します。
捜索は、目的の達成や問題の解決に向けて重要な手段となることがあります。
また、捜索の対象や方法は様々であり、法律や警察の分野だけでなく、情報の探索やデータの収集など、幅広い場面において用いられます。
捜索は、まさに人間の探究心や知識の追求を表す言葉であり、社会の発展や安全にも貢献しています。