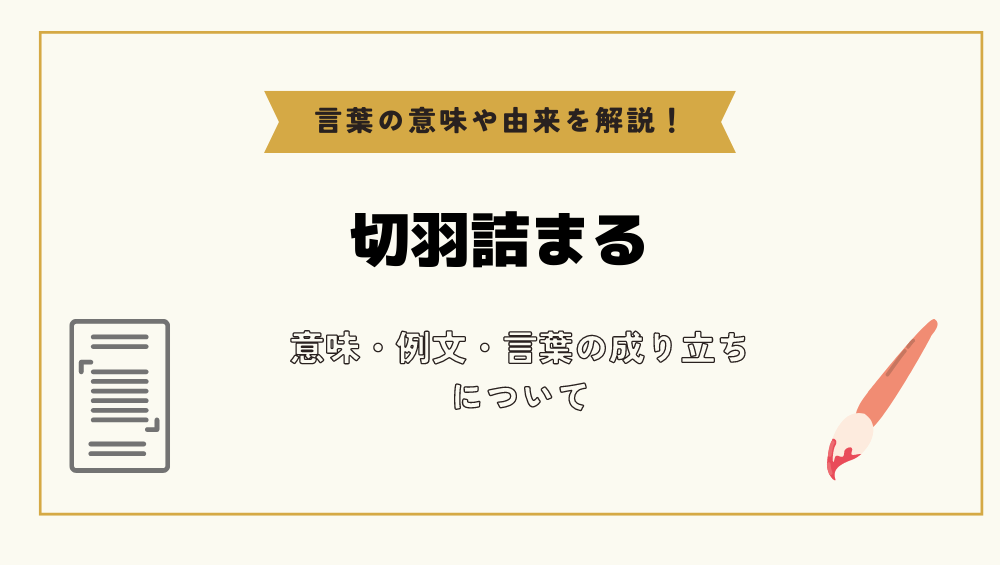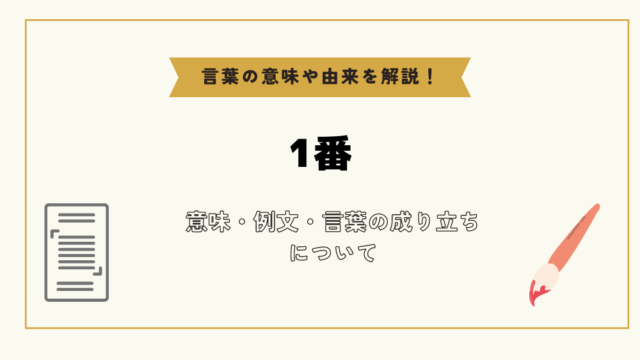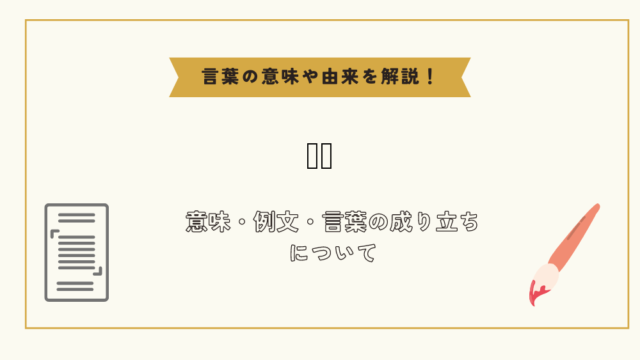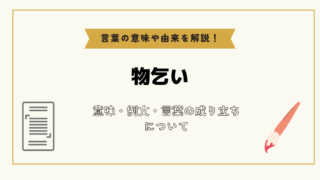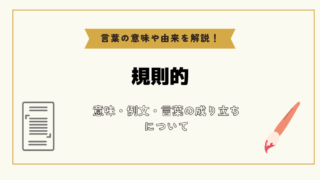Contents
「切羽詰まる」の意味を解説!
。
「切羽詰まる」とは、物事が非常に急ぎ、時間が迫っている状況を表現する言葉です。
切羽(せっぱ)とは、のみを仰ぐ鳥が水中の障害物を避けるために羽を切るように、限られた状況下での行動を余儀なくされることを意味します。
詰まる(つまる)とは、行き詰まって進めなくなることを指します。
つまり、「切羽詰まる」とは、緊急かつ困難な状況に追い込まれることを表現しています。
「切羽詰まる」の読み方はなんと読む?
。
「切羽詰まる」は、「せっぱつまる」と読みます。
日本語の言葉ですので、ひらがな表記で読むことが一般的です。
「切羽詰まる」の使い方や例文を解説!
。
「切羽詰まる」は、重要な案件の締め切りが迫っているときや、大切な試験の日が近づいているときなどによく使われます。
例えば、「仕事のプレゼンの準備が切羽詰まっているので、今日は残業します」と言った場合、時間的な制約やプレッシャーに追い込まれている様子が伝わります。
また、「テスト勉強のために切羽詰まる中、友達との予定をキャンセルしなくてはいけなくなった」と言った場合は、時間が迫っているからこそ、友達との予定をキャンセルせざるを得なくなったという状況が伝わります。
「切羽詰まる」の成り立ちや由来について解説
。
「切羽詰まる」の語源は、江戸時代の成立と考えられています。
江戸時代には、鷺(さぎ)などの野鳥が水の中で魚をつかもうとして、水面の下にいる魚を見つけるために、翼の羽を切る行為がありました。
この行為が「切羽(せつや)」と呼ばれるようになり、それがさらに転じて「切羽詰まる」という言葉が生まれたと考えられています。
「切羽詰まる」の言葉の歴史
。
「切羽詰まる」という言葉は、江戸時代から使われている言葉です。
当時の日本は、戦国時代から江戸時代にかけての長い戦乱期を経て、さまざまな困難に直面していました。
そのような背景からか、「切羽詰まる」という言葉が生まれ、継続して現代まで使われ続けているのです。
「切羽詰まる」の言葉についてまとめ
。
「切羽詰まる」という言葉は、緊急で困難な状況を表現する際に使われます。
締め切りや試験日が迫る中、時間的な制約やプレッシャーに追い込まれる様子が伝わる言葉です。
成り立ちや由来は江戸時代にさかのぼりますが、戦国時代から続く長い歴史を持つ言葉となっています。