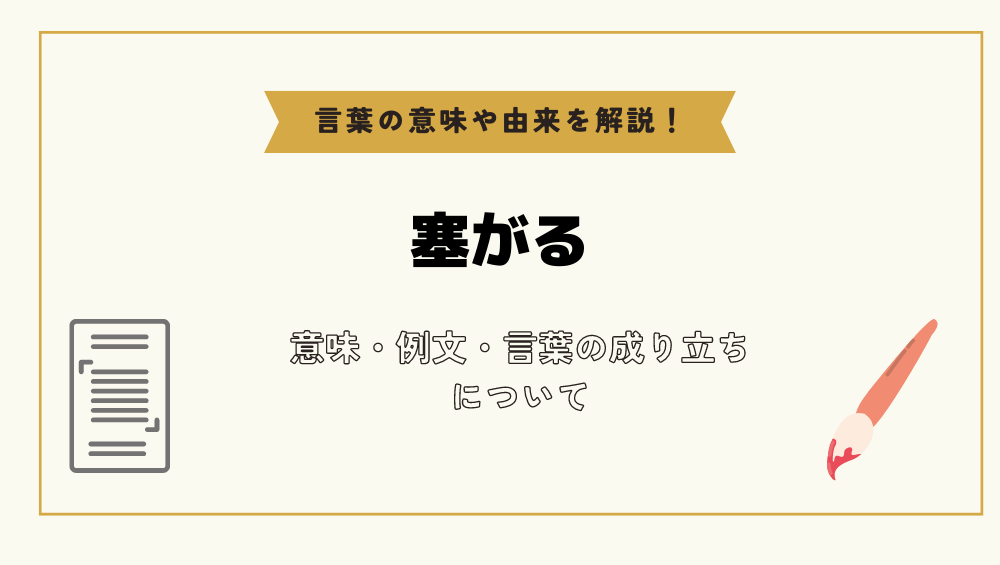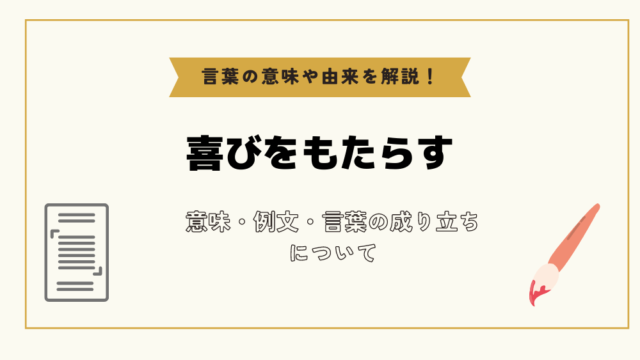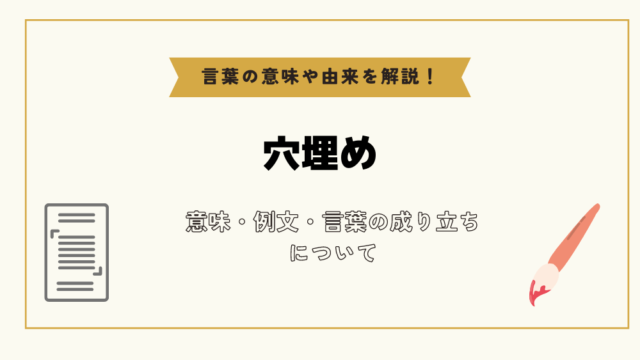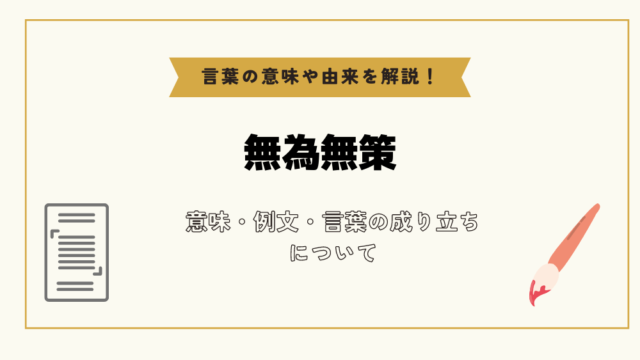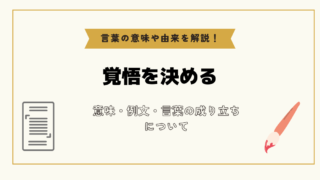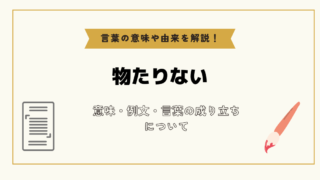Contents
「塞がる」という言葉の意味を解説!
。
「塞がる」という言葉は、何かの通り道や穴などが詰まって通れなくなることを表します。
例えば、道路の穴が埋まったり、水道の詰まりなどが起きると「塞がる」と言います。
また、心が物事で満たされてしまい、心に余裕がなくなることも「塞がる」と言われます。
「塞がる」の読み方はなんと読む?
。
「塞がる」は、「ふさがる」と読みます。
この読み方は、一般的な日本語の発音に合わせたものです。
ふさがるという言葉は、日常的によく使われるため、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「塞がる」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「塞がる」は、何かが通っていた箇所が詰まったり、閉じられてしまい通れなくなることを表します。
具体的な例を挙げると、道路の詰まりや水道管の詰まりが起きることがあります。
また、心が満たされ過ぎて他のことに集中できない状態も「塞がる」と言います。
。
例文としては、「道路の穴が埋まり、交通が塞がることがあります。
」や「仕事のストレスで心が塞がり、リフレッシュする機会を作りましょう。
」などがあります。
このように「塞がる」は、さまざまな状況に使われることが分かります。
「塞がる」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「塞がる」という言葉の成り立ちについては、具体的な由来は分かっていません。
ただ、「ふさぐ」という言葉に発展した形と考えられています。
かつては「ふさがる」という表現が主流でしたが、現代の日本語では「塞がる」と言われることが一般的になりました。
「塞がる」という言葉の歴史
。
「塞がる」という言葉の歴史は古く、日本語においては古代から使われてきた言葉です。
古文書や文学作品などにも頻繁に登場し、人々の日常生活に深く根付いています。
時代が経つにつれて、使用頻度は変化しましたが、今日でも私たちの会話や文書の中で活発に使われています。
「塞がる」という言葉についてまとめ
。
「塞がる」という言葉は、何かの通り道や穴などが詰まって通れなくなることを表します。
また、心が物事で満たされてしまい、心に余裕がなくなることも「塞がる」と言われます。
日本語の発音に合わせて「ふさがる」と読まれます。
道路や水道管の詰まりなど、さまざまな状況で使われます。
明確な成り立ちや由来は分かっていないものの、古代から使われている歴史のある言葉です。