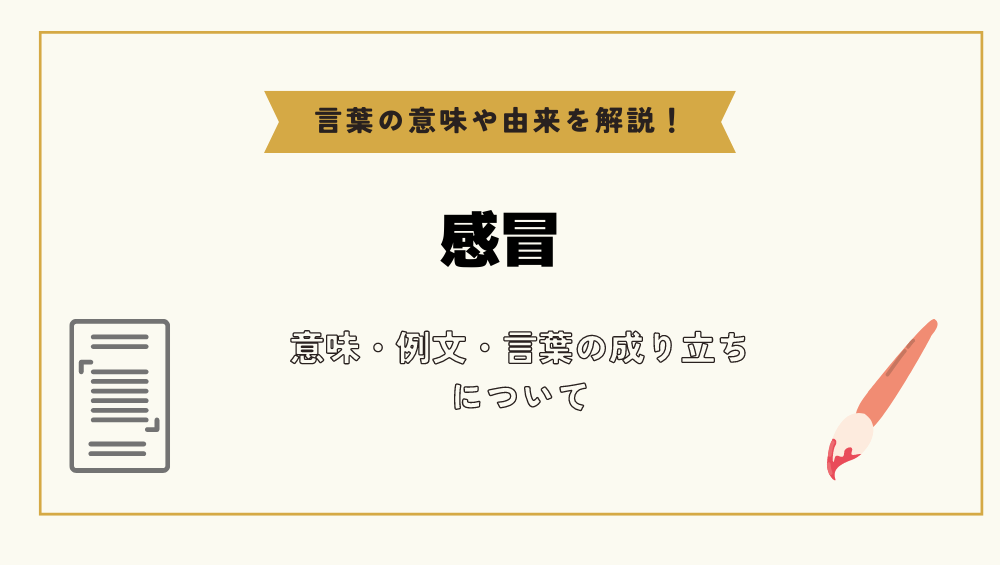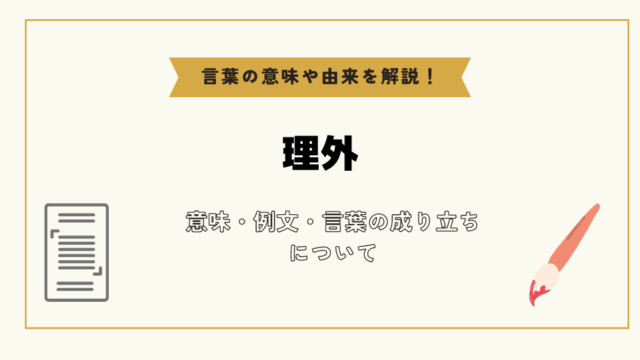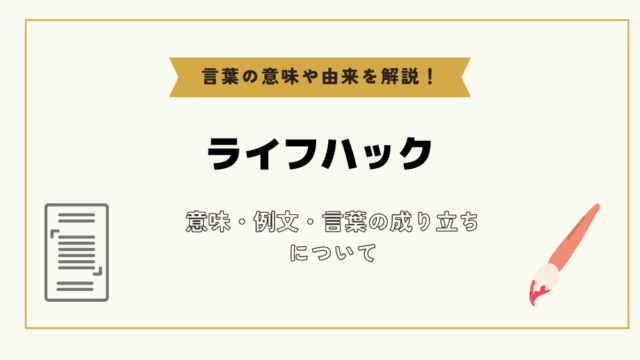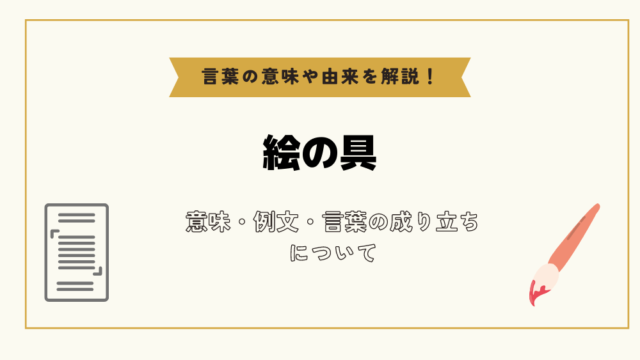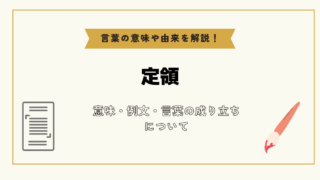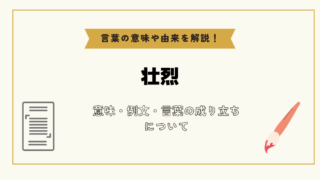Contents
「感冒」という言葉の意味を解説!
感冒(かんぼう)とは、風邪のことを指す言葉です。風邪は私たちの身体にさまざまな症状を引き起こすため、特定の病気を指す総称として「感冒」という言葉が使われることがあります。
私たちの身体が風邪にかかると、くしゃみや咳、鼻水などの症状が現れます。
また、体がだるくなったり、頭が重くなったりすることもあります。
これらの症状が現れると、私たちは「感冒にかかった」と言います。
「感冒」の読み方はなんと読む?
「感冒」は、漢字で書かれる場合は「かんぼう」と読みます。この読み方は、一般的な日本語の発音に準じたものとなっています。漢字の「感」は「かん」と読み、「冒」は「ぼう」と読みます。
「感冒」という言葉の使い方や例文を解説!
「感冒」という言葉は、風邪にかかったときや風邪に関連する症状を説明するときに使用されます。「彼は最近感冒にかかっているので、会議への出席を見合わせることにしました」というように、ほかの人に風邪を説明する際にも用いられます。
また、「昨日から感冒の症状が出ているので、しばらく休んでいました」というように、自分自身の状態を説明する場面でも使用されることがあります。
「感冒」という言葉の成り立ちや由来について解説
「感冒」という言葉は、漢字で書かれることから分かる通り、中国由来の言葉です。風邪の症状が体内に感染した状態と見なされ、それが「冒」という漢字で表されています。
中国では、風邪のほかにもさまざまな病気を代表的な症状で表すことがあります。そのため、風邪を指す場合には「感冒」という表現が一般的に使われるようになりました。
「感冒」という言葉の歴史
「感冒」という言葉の歴史は古く、紀元前の中国の医学書にも見られる言葉です。当時の医学では、風邪は六淫(陰陽五行説の中の病因)のひとつとされ、体内に侵入する外来の気とされていました。
この六淫説の中で、風寒(ふうかん)という要素が風邪の病因とされ、その症状を「感冒」という言葉で表現するようになりました。現在の日本でも、風邪を指す言葉として「感冒」という表現が用いられています。
「感冒」という言葉についてまとめ
「感冒」は、風邪のことを指す言葉であり、日本でもその表現が使われています。この言葉は中国由来であり、頭がだるくなったり、咳や鼻水などの症状が現れるときに使用されます。
「感冒」という言葉は、昔から使われてきた古い言葉であり、現在も我々の日常会話でよく聞かれる言葉のひとつです。風邪の症状や風邪にかかっていることを表現する場合には、「感冒」という言葉を活用してみてください。