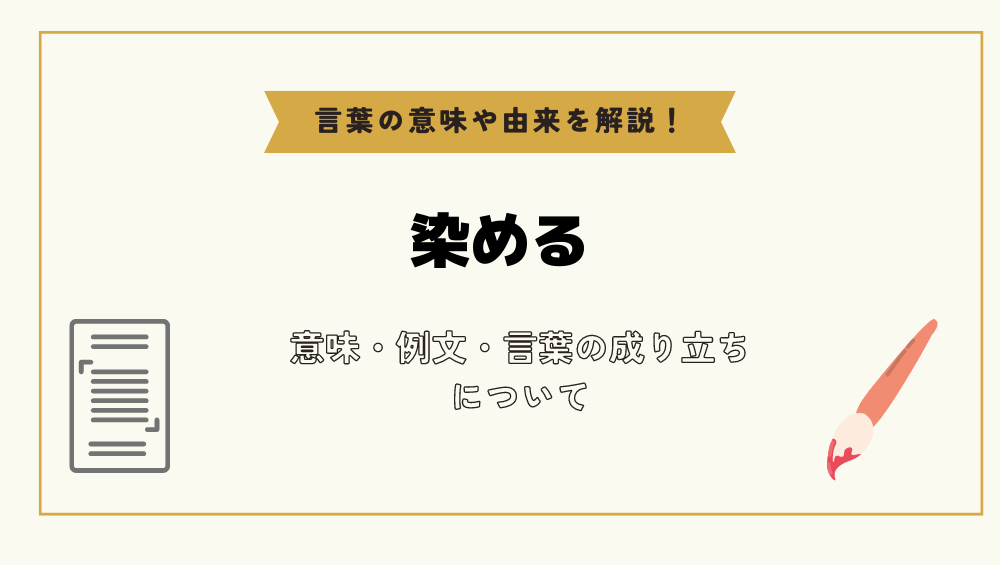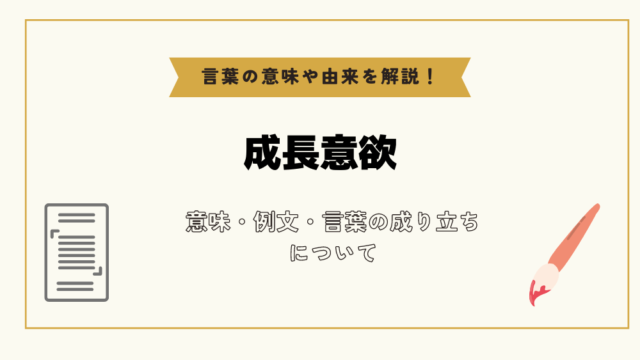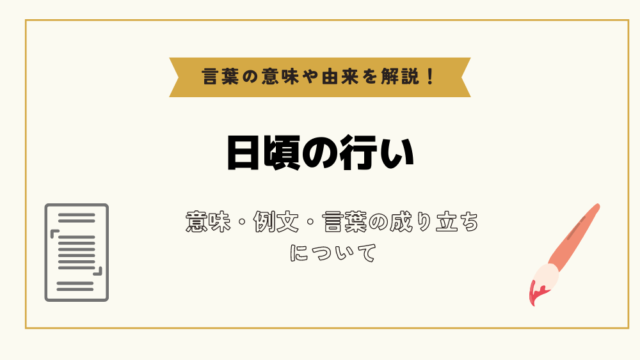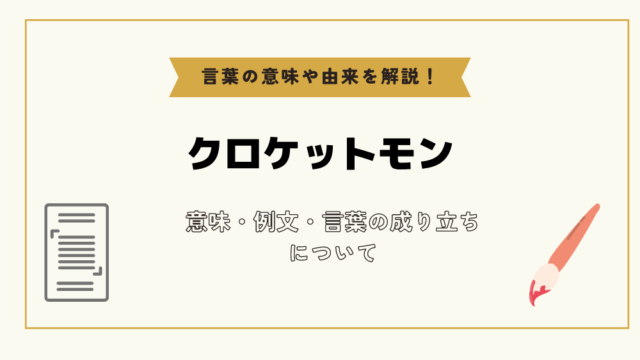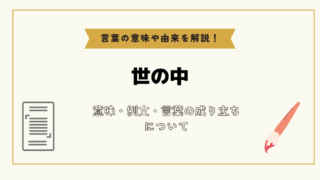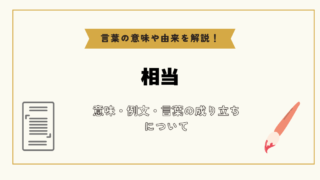Contents
「染める」という言葉の意味を解説!
「染める」という言葉は、物に色や柄をつけることを意味します。例えば、布や髪の毛に染料を使って色をつけることが一般的な使い方です。また、経験や感情が人の心に深く染み込むことも、「染める」の意味の一つです。物理的な染まり方だけでなく、心の中まで影響を与える力を持つ言葉でもあります。
「染める」の読み方はなんと読む?
「染める」は、「そめる」と読みます。日本語の発音にはいくつかのルールがありますが、この場合は「染」の音読みである「そめ」と、「る」を組み合わせて「そめる」となります。
「染める」という言葉の使い方や例文を解説!
「染める」の使い方は、主に他動詞として使われます。例えば、「布を染める」という場合、布に色をつけることを表します。他にも、「髪を染める」「壁を染める」のように、さまざまな対象に対して染料を使って色をつけることを指すことができます。
例文としては「彼女は髪をピンクに染めました」という表現があります。この文では、女性が髪の毛にピンクの染料を使って色をつけたことを表しています。
「染める」という言葉の成り立ちや由来について解説
「染める」は、古代の日本語である「そめる」という表現が起源とされています。日本の歴史において、染色技術は非常に重要であり、特に平安時代以降には発展しました。そのため、「染める」という言葉も古くから使われていたと考えられています。
「染める」という言葉の歴史
「染める」という言葉の歴史は、日本の染織技術の歴史と深く関わっています。古代の日本では、植物の葉や木の皮、昆虫の体液などを使って染料を作り、それを布に染める技術が発展しました。江戸時代には絹織物や木綿織物の染色技術が磨かれ、美しい模様や色使いが特徴となりました。
現代では化学染料や合成染料が一般化していますが、伝統的な染め技術も多くの人に愛され続けています。
「染める」という言葉についてまとめ
「染める」という言葉は、色や柄を物につける行為を表す言葉です。それだけでなく、経験や感情が人の心に深く染み込むこともあります。また、古代の日本においては染織技術が盛んに行われ、染めることが文化の一部として重要視されていました。現代でも染織技術は進化し続けており、伝統的な染め技術と新しい技術が融合してさまざまな魅力的な作品が生み出されています。