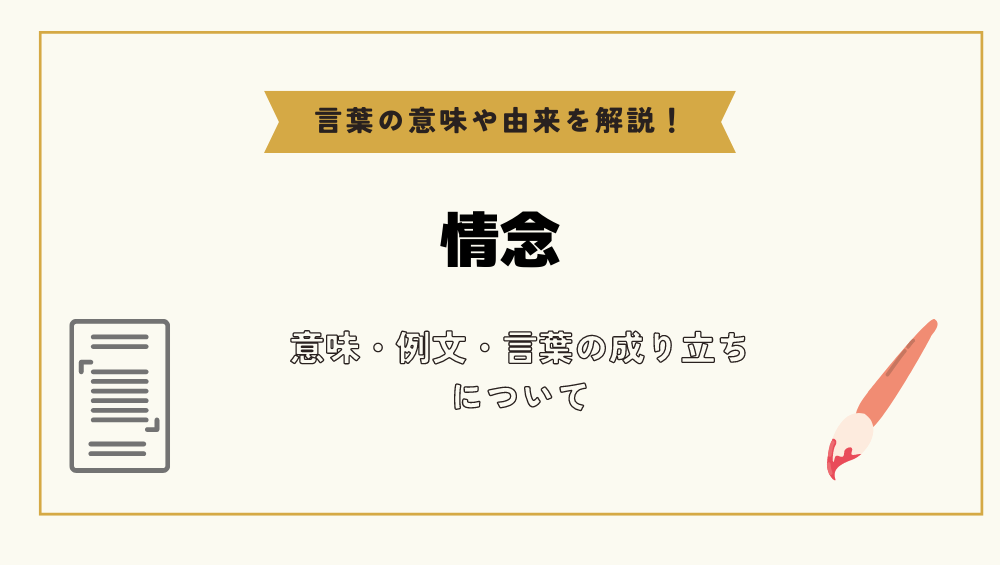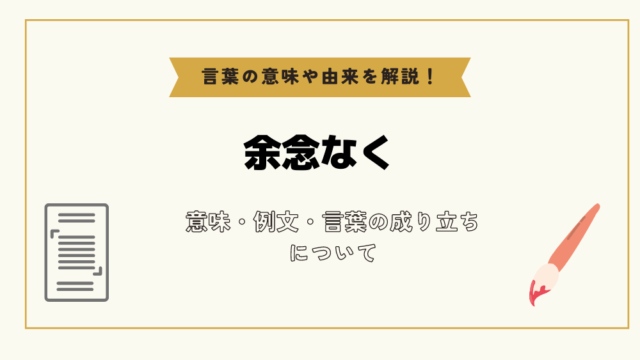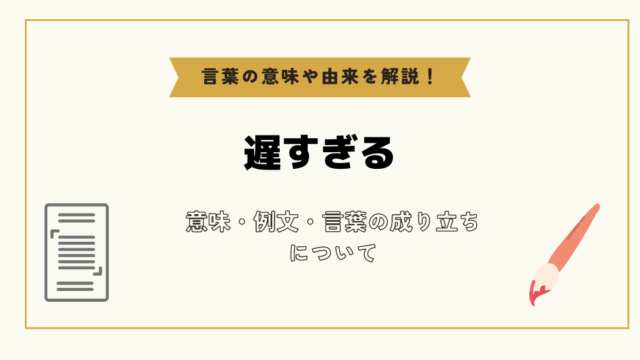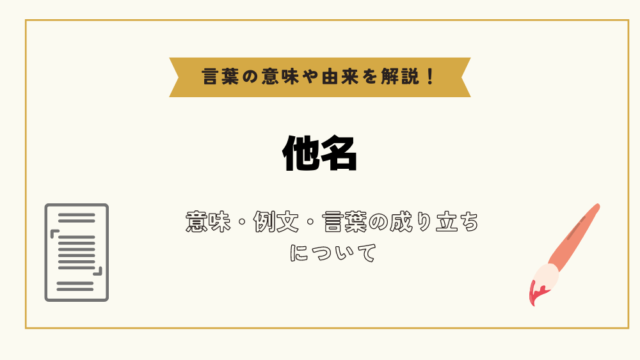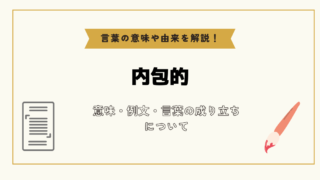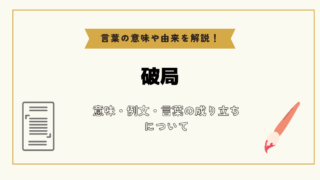Contents
「情念」という言葉の意味を解説!
「情念」とは、心に湧き起こる強い感情や情熱のことを指します。
人間の内に秘められた熱い思いや感情を表現する言葉として使われます。
情念には、愛情や悲しみ、怒りや喜びなど、様々な感情が含まれます。
情念は、人間特有の感情であり、その深さや抗えない強さが魅力です。
情念には人々の心を揺さぶる力があり、さまざまな芸術作品や文学作品にも表現されてきました。
「情念」という言葉の読み方はなんと読む?
「情念」という言葉は、「じょうねん」と読みます。
漢字の「情」と「念」は、それぞれ「こころ」と「おもい」という意味を持ち、合わさって「じょうねん」となります。
この読み方は日本語の一般的な読み方であり、広く認知されています。
是非、正しい読み方で「情念」という言葉を使ってみてください。
「情念」という言葉の使い方や例文を解説!
「情念」という言葉は、自分の心の中に湧き上がる感情や思いを表現する際に使われます。
例えば、ある人が恋人への情念を綴った手紙を書くときには、その深い愛情や切なさを伝えるためにこの言葉を選ぶことができます。
また、小説や詩などの文学作品でも、「情念」は重要なテーマとして扱われることがあります。
登場人物の心の奥に秘められた情念が、読者の共感を呼び起こすことがあります。
「情念」という言葉の成り立ちや由来について解説
「情念」という言葉は、日本の古典文学や仏教の教えに由来しています。
仏教では、心の中の様々な感情や欲望が悩みや苦しみの原因となるとされており、これらを「念」と呼んでいます。
一方で、「情」という言葉は、人間の心の中にある情緒や感情を指す言葉です。
「情念」という言葉は、この二つの言葉が組み合わさったもので、人々の心に湧き上がる強い感情や情熱を表現するために使われるようになりました。
「情念」という言葉の歴史
「情念」という言葉は、古くから日本の文学や芸術、思想の中で重要な役割を果たしてきました。
特に、平安時代の歌物語や室町時代の浄瑠璃などの文学作品では、登場人物の情念が鮮やかに描かれています。
また、江戸時代には「情念残滓」という言葉が使われ、江戸文化における感情や情緒の表現方法を指す言葉として注目されました。
現代でも、これらの文化や歴史的背景から派生した情念の表現は人々に感動を与えています。
「情念」という言葉についてまとめ
「情念」という言葉は、人間の心の中に湧き上がる強い感情や情熱を表現する言葉です。
愛情や悲しみ、怒りや喜びなど、さまざまな感情が「情念」として表現されます。
綴られた手紙や文学作品などで見る情念は人々の心を揺さぶりますし、歴史的背景から生まれた言葉でもあります。
心の奥底に秘められた情念が、人々の共感を呼び起こし、感動を与えることもあります。