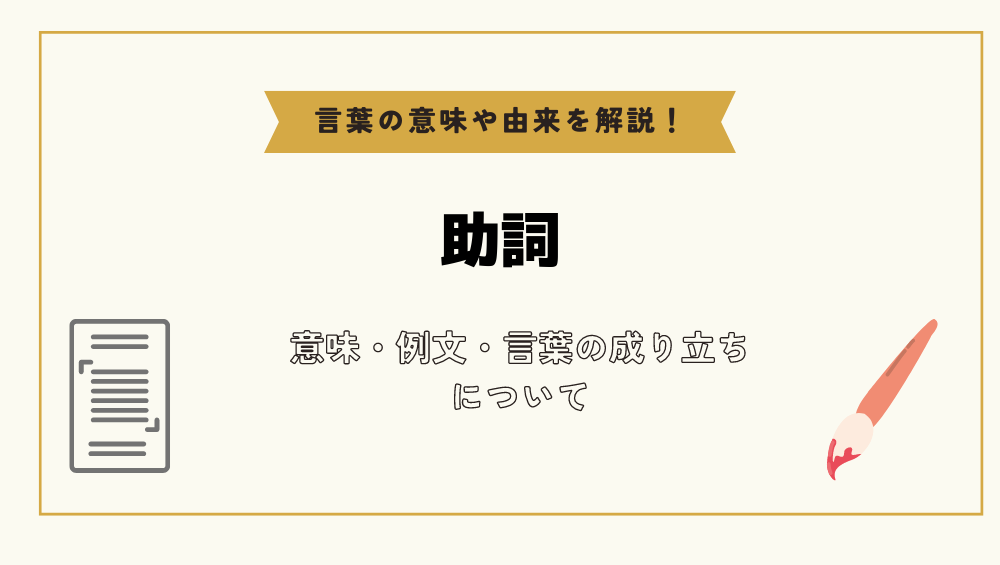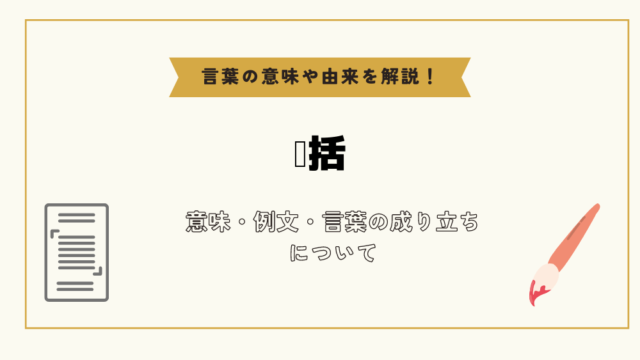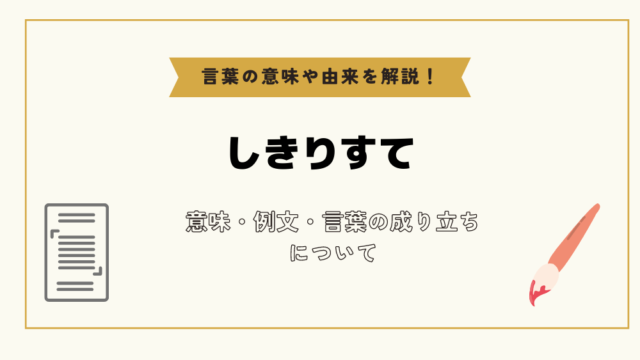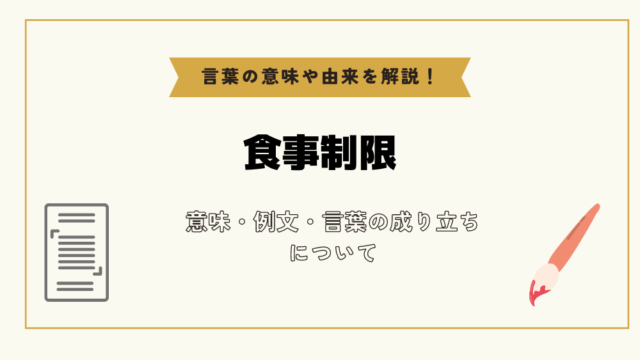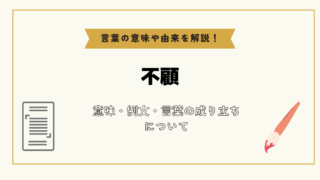Contents
「助詞」という言葉の意味を解説!
助詞(じょし)とは、文章において、文節や句を結びつけ、その関係や役割を示す役割を持つ日本語の品詞の一つです。
助詞は主語や目的語、修飾語など文中の要素を示す役割を果たしています。
「助詞」という言葉の読み方はなんと読む?
「助詞」という言葉は、「じょし」と読みます。
日本語では、漢字を使って表記される単語が多いため、正しい読み方を知ることで他の人とのコミュニケーションがスムーズになります。
「助詞」という言葉の使い方や例文を解説!
助詞は、文の要素を結びつけるために使用されます。
例えば、「私は学生です」という文では、「は」が主語である「私」と述語である「学生です」を結びつける役割を果たしています。
他にも「が」「を」「に」「と」などの助詞があり、それぞれに独特の役割があります。
「助詞」という言葉の成り立ちや由来について解説
「助詞」という言葉は、中国の文法書である「文選」が日本に伝えられた際に使われるようになりました。
その後、日本独自の文法の一部として発展していきました。
「助詞」の成り立ちや由来については、詳しい解明が困難であり、明確な情報は存在しません。
「助詞」という言葉の歴史
助詞は、古代日本の文章ではすでに使用されていましたが、その存在は明確な文書に残っていません。
現代の助詞の形態は、中世から近世にかけての日本語の変化とともに形成されました。
助詞は、日本語の文法の基本的な要素として、現代に至るまで使用され続けています。
「助詞」という言葉についてまとめ
「助詞」は、文章において文節や句を結びつけ、その関係や役割を示す役割を持つ日本語の品詞です。
文中の要素を明確にするために欠かせない存在であり、正確な使い方を理解することは日本語を学ぶ上で重要です。
助詞の成り立ちや由来については詳しく分かっていませんが、古代から現代まで日本語文法の基本的な要素として存在し続けています。