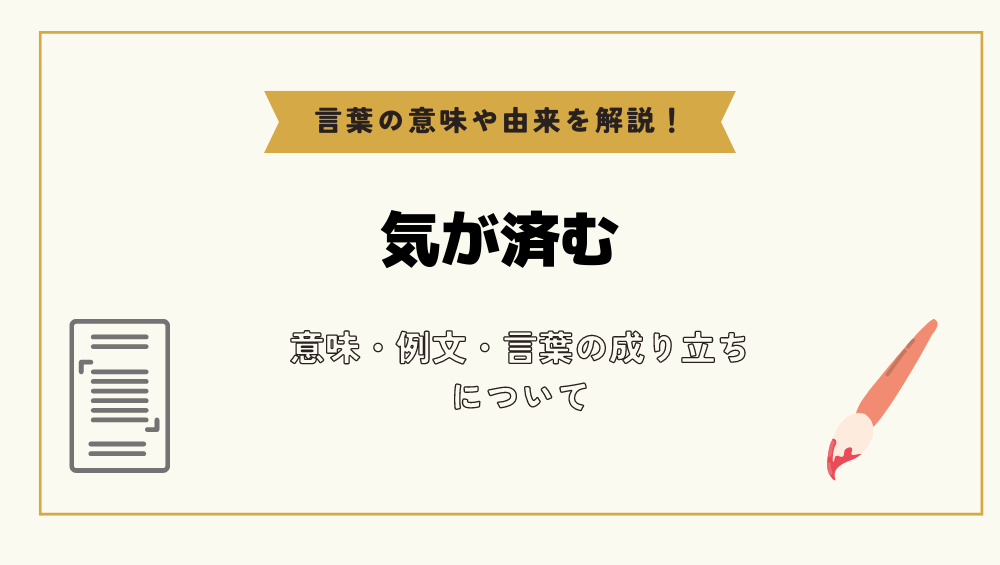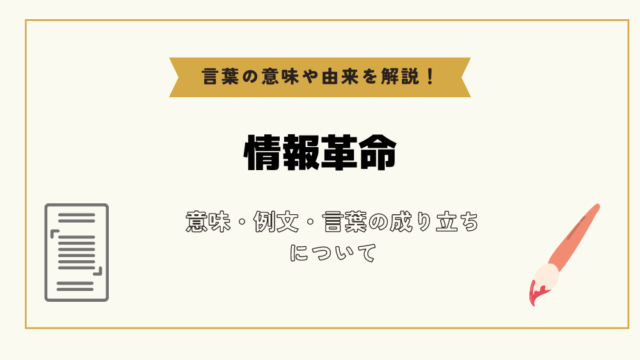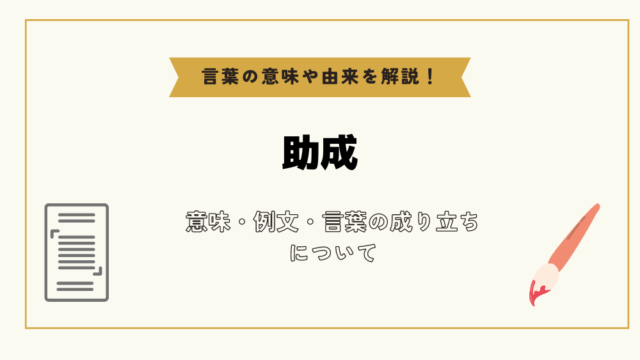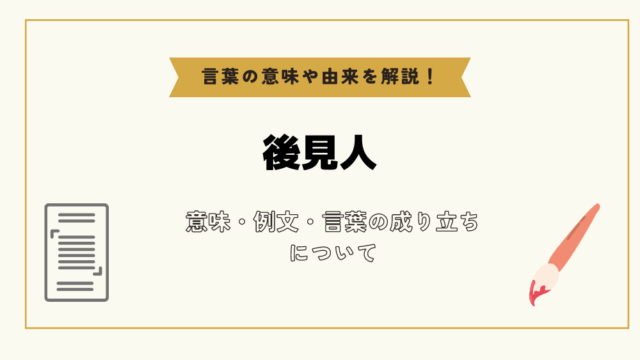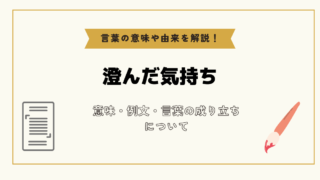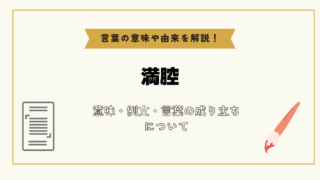Contents
「気が済む」という言葉の意味を解説!
「気が済む」という言葉は、自分が満足することや納得することを意味します。
何かを行ったり、話し合ったりして、自分が晴れやかな気持ちになることを表現する際に使われるフレーズです。
自分が思うように行動や成果を得たり、他人の言うことを聞き入れたりすることで、内心の安堵感や達成感を感じるときに使用されます。
「気が済む」の読み方はなんと読む?
「気が済む」の読み方は、「きがすむ」と読みます。
日本語の基本的な読み方に従っており、特別なルールや発音はありません。
日本語教育を受けた方や日本語を母国語とする方なら、一般的にこの読み方を知っているでしょう。
「気が済む」という言葉の使い方や例文を解説!
「気が済む」は、自分が求める状態や満足度を表現する際に用いられます。
例えば、仕事でプロジェクトを完了した際に「やっと気が済んだ」と言いたいと思うかもしれません。
ほかにも、「気が済むまで話したい」というように、自分の思いや意見を相手に伝えるために使うこともあります。
「気が済む」という言葉の成り立ちや由来について解説
「気が済む」という言葉の成り立ちは、江戸時代にさかのぼることができます。
当時、人々は「済む」という言葉を用いて、儀式や行事などの完了や確認を表現していました。
その後、「気が済む」という表現が生まれ、人々が心理的な満足を表す際に使われるようになりました。
「気が済む」という言葉の歴史
「気が済む」という言葉の歴史は、江戸時代にさかのぼります。
当時の人々は、身分や立場に応じて適切な言葉や敬語を用いていました。
その中で「気が済む」という表現が生まれ、人々が自分の意見や願いを伝える際に使われるようになりました。
現代でも、この表現は広く使われています。
「気が済む」という言葉についてまとめ
「気が済む」という言葉は、自分が満足や納得を感じることを表現する際に使われます。
自分が思うように行動や成果を得たり、他人とのコミュニケーションで自分の思いを伝えたりすることで、内心の安堵感や達成感を感じるときに使います。
江戸時代から現代に至るまで、その意味と使い方は変わらず受け継がれています。