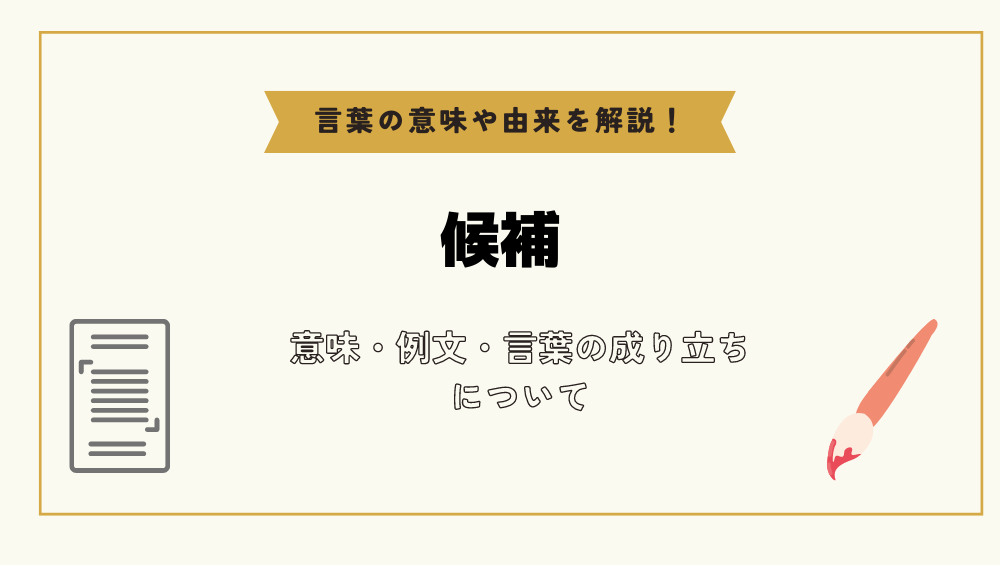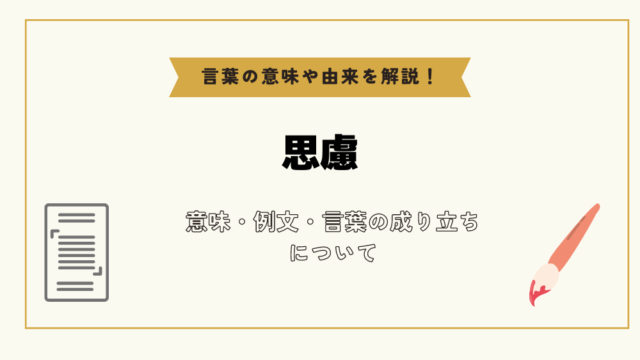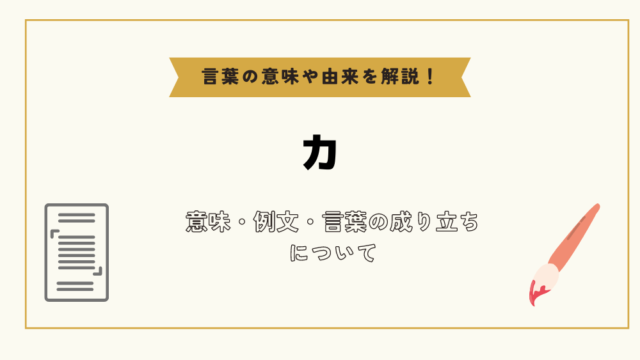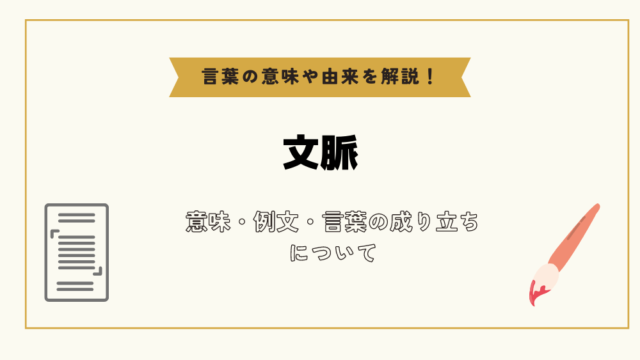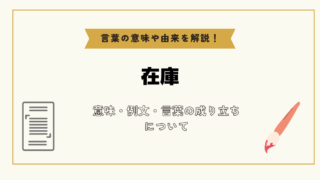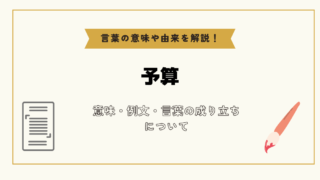「候補」という言葉の意味を解説!
「候補」とは、最終決定や選定の対象として挙げられる人物・物事・案などを指す言葉です。この語は、複数ある選択肢の中から最終的に選ばれるかもしれない状態を示し、必ずしも確定ではないというニュアンスを含んでいます。ビジネスシーンでは新製品名の候補、学術分野では研究テーマの候補、日常生活では旅行先の候補といった形で、多岐にわたって使われています。
「候補」という言葉は、選ばれる可能性を持つだけでなく、まだ検証や比較のプロセスが残っていることも示しています。そのため「暫定的」「未確定」といった意味合いが裏に隠れている点が特徴です。選考過程や意思決定の手前で用いられるため、「選択肢」よりも具体的で、「決定」よりも手前の段階を表す言葉だと言えます。
「候補」の読み方はなんと読む?
「候補」は一般的に「こうほ」と読みます。音読みのみで構成されるため、送り仮名が付くことはありません。訓読みや訓+音読みの混在がないことから、読み間違いは比較的少ない語ですが、同音異義語の「広報(こうほう)」と混同されるケースはしばしば見受けられます。
「候」の字は「そうろう」とも読みますが、現代日本語の日常会話でこの読み方が出てくることはほとんどありません。併せて「補」の読み方が「ほ」である点も確認しておくと、同音語との差異がより明確になります。書き言葉では「候補者」と続けて用いられることが多いので、前後の文脈で読み方を判断するのが安全です。
「候補」という言葉の使い方や例文を解説!
「候補」は「候補に挙がる」「候補から外れる」など、動詞とセットで使われることが多いのが特徴です。そのほか「第一候補」「複数候補」といった形容詞的な前置きで、優先度や数を補足する使い方も一般的です。
【例文1】新商品のネーミング候補を今週中に三つ提出する。
【例文2】彼は次期代表の有力候補に名前が挙がっている。
【例文3】旅行先の候補として、北海道と沖縄を比較検討した。
【例文4】時間の都合で、映画鑑賞の候補はリストから外した。
ビジネスメールでは「次回会議で候補案を共有します」といった定型表現が便利です。スピーチやプレゼンでは「現時点での第一候補」「バックアップ候補」と区分することで、聴衆に優先順位を明確に示せます。なお法律文書や公的文書で用いる際は、「候補者」「候補地」などの接尾語を加えることで、対象をより具体的に限定できます。
「候補」という言葉の成り立ちや由来について解説
「候補」は中国の古典語「候補(ほうほ)」に由来し、「官職に推挙される人物」を指したのが起源とされています。「候」は「うかがう」「うかがい知る」を意味し、古代中国では天候や時機を伺う行為を表しました。「補」は「補う」「欠けた部分を埋める」という意味です。二つの字が組み合わさることで、「適切な人や物を補うための伺い立て」というニュアンスが生まれました。
日本には奈良〜平安期に漢籍とともに伝わり、律令制下では官位に就く人物を推薦する語として定着しました。近世以降、政治だけでなく学問や芸能など多様な分野に広がり、明治期には西洋の「candidate」の訳語として用いられるようになります。現代では「候補地」「候補案」など対象を問わない便利な語として定着しました。
「候補」という言葉の歴史
日本での「候補」は、古代律令制時代の人材登用から選挙制度の普及、そして企業の人事やマーケティングまで、用途を拡張しつつ現代語へと進化してきました。奈良時代の官人選抜では「候補」と書いて「こうほ」と読ませていた記録が残っていますが、当時は限定的な専門用語でした。
江戸期には寺社奉行や町役人の推挙文書に「候補」という語が散見されますが、読みは「ほうほ」など揺れがありました。明治期に公職選挙法が成立し、英語の「candidate」を「候補者」と訳したことが転換点となります。その後、大正・昭和の選挙報道で「候補」が一般化し、戦後の民主化により日常用語として定着しました。現代ではIT業界で「候補リスト」「サジェスト候補」といった新たな用法も生まれ、時代の変化に合わせて語義を拡張し続けています。
「候補」の類語・同義語・言い換え表現
「候補」を言い換える場合、「有力視される対象」を示す語を選ぶと文意の揺れが少なくなります。代表的なのは「選択肢」「プラン」「オプション」「案」「候補者」などです。ただし厳密にはニュアンスが異なり、「選択肢」は幅広い可能性を示す一方、「候補」はある程度絞り込まれた対象を指します。
ビジネス文書では「候補案」→「案」「プラン」に置き換えると柔らかい印象になります。採用活動では「候補者」→「応募者」「志望者」に言い換えることで、立場の公平性を強調できます。IT分野の「サジェスト候補」は「推奨ワード」と言い換えても構いませんが、専門性が若干薄れる点に注意してください。
「候補」の対義語・反対語
「候補」の明確な対義語はありませんが、文脈に応じて「決定」「確定」「落選」が反対概念として機能します。たとえば「第一候補が決定」に対し、「決定」は候補の状態が終わったことを示します。また選挙の場合は「当選」と「落選」が対立するため、「候補」の段階と「当選・落選」の結果を対義的に把握できます。
ビジネスでは「採用候補」に対して「不採用」「却下」などが対概念です。学術分野の研究テーマでは、採択されなかった案を「棄却」と表現する場合もあります。反対語を選ぶ際は、最終的にどういう結果になると「候補」の状態が終了するのかを意識すると選択が容易になります。
「候補」が使われる業界・分野
「候補」という語は、政治・選挙、ビジネス、人事、IT、医療、学術研究などほぼすべての領域で重要なキーワードとして機能しています。政治では「候補者」、ビジネスでは「候補地」「候補案」、人事では「採用候補者」といった形で活用されています。
IT業界では検索エンジンの「サジェスト候補」、AIの「生成候補」、プログラミングでは「補完候補」と応用範囲が広がっています。医療分野では「治療候補」「手術候補」という言い回しが、エビデンスと患者の状況を踏まえた選択肢の提示に使われます。学術研究では論文タイトルの「キーワード候補」や新説の「仮説候補」があり、意思決定プロセスを示す語として欠かせません。
「候補」を日常生活で活用する方法
日常会話に「候補」を取り入れると、選択肢を整理しやすくなり、相手に自分の優先度を明確に伝えられます。買い物では「今の第一候補はこのスマホケース」、旅行計画では「ホテルの候補を三つピックアップした」といった言い回しが便利です。
家族会議で夕食を決める場面では、「カレーとパスタが候補だよ」と言うだけで、議論の的を絞れます。またタスク管理アプリに「今週の候補タスク」ラベルを作ると、やるべきことの優先順位付けが容易になるでしょう。こうした用法は相手への配慮にもつながり、「まだ決定ではないが検討中」という柔らかい語感が衝突を防いでくれます。
「候補」という言葉についてまとめ
- 「候補」は最終決定前に挙げられる人物・物事・案を示す言葉。
- 読み方は「こうほ」で、同音異義語の「広報」と混同しやすい点に注意。
- 起源は中国古典で、官職推挙の語として奈良時代に日本へ伝来した。
- 現代では政治・ビジネス・ITなど多分野で活用され、未確定性を示す際に便利。
「候補」という言葉は、選択肢を絞り込む過程を端的に示せる便利な表現です。読み方や歴史を押さえておくことで、同音語との混同を防ぎ、文脈に応じた正確な用法が可能になります。
ビジネスはもちろん、日常の買い物や趣味の計画にも応用できるため、語感の柔らかさと汎用性の高さが魅力です。今後もITやAIなど新しい分野での活用が進むと予想されるので、用語の変化に継続してアンテナを張っておくと良いでしょう。