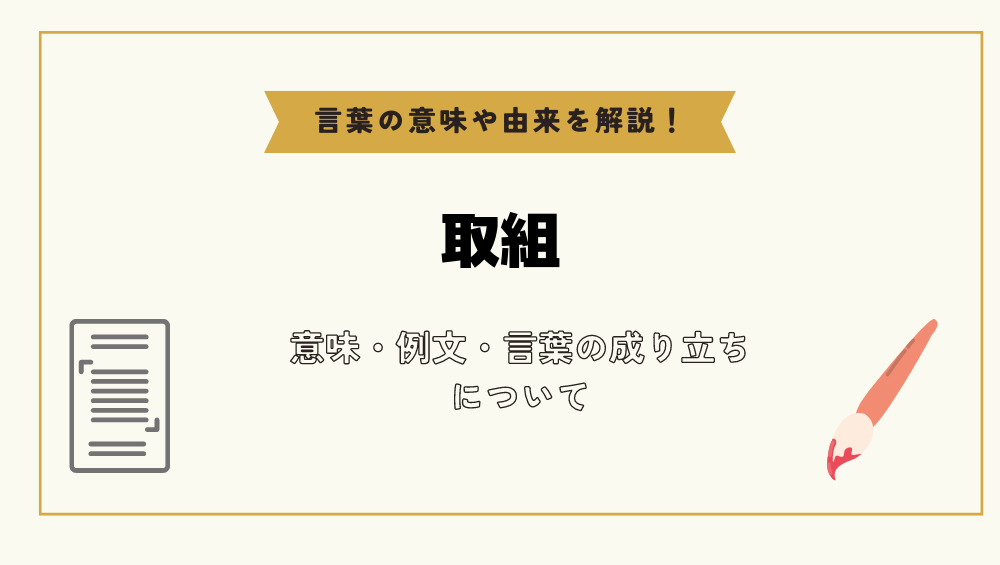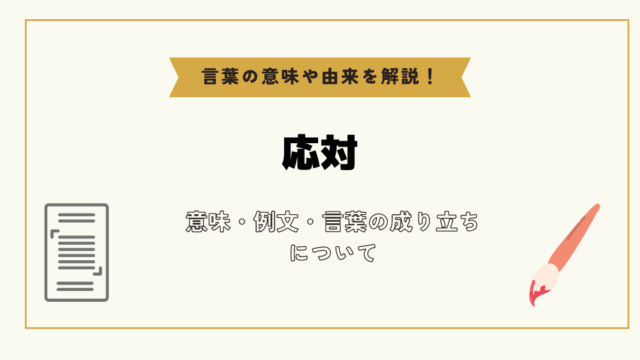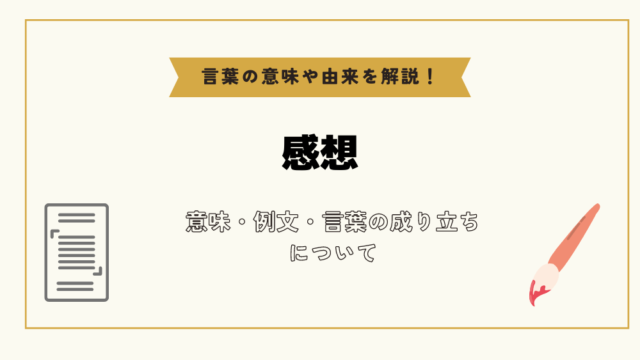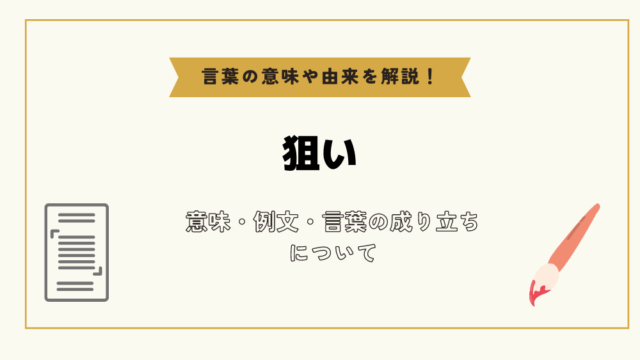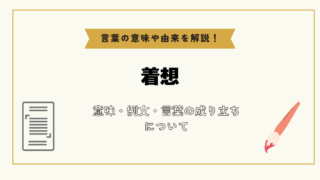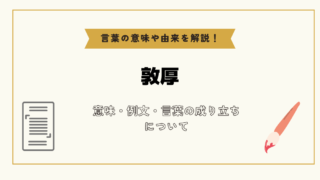「取組」という言葉の意味を解説!
「取組」は「ある目的を達成するために具体的な行動をすること、またはその計画全体」を示す日本語です。ビジネス文書では「環境への取組」「品質向上への取組」のように、目標を示す名詞と組み合わせて使われます。個人レベルでも「健康維持の取組」といえば食事管理や運動などの一連の行為をまとめて指す表現です。単なる「行動」と違い、目標と手段がセットになっている点が大きな特徴です。
似た言葉に「活動」や「努力」がありますが、「取組」はより体系的で計画性が求められる場面に用いられる傾向があります。行政文書・報告書・学校教育など、公的な資料にも頻出し、客観的・定量的な評価を行いやすいのも利点です。
つまり「取組」とは、目的、計画、行動、評価のサイクルを含む“プロジェクト志向の行動”を示す語と整理できます。この定義を押さえることで、読み手にあいまいな印象を与えず、具体性を持った説明が可能になります。
取組の実例としては、自治体が策定する「脱炭素社会への取組」、企業が公表する「コンプライアンス取組方針」、学校が掲げる「いじめ防止取組計画」などが挙げられます。目的が明確であるほど、取組は評価指標とセットで語られる点も押さえておきましょう。
「取組」の読み方はなんと読む?
「取組」は一般的に「とりくみ」と読みます。ひらがな表記でも意味は変わりませんが、公式文書やニュースリリースでは漢字が好まれます。ビジネスシーンで読み間違えが起こることは少ないものの、類似語の「取り組み」と混同しやすいので注意が必要です。
「取組」と「取り組み」は同じ読みですが、公的文書では「取組」という二字熟語が採用されやすいという慣習があります。一方、生活情報誌やウェブメディアでは「取り組み」と送り仮名を付ける表記も多く、柔らかい印象を与えます。このように、ターゲット層や媒体に合わせて漢字とひらがなを使い分けることが読みやすさのポイントです。
音読では「トリクミ」と平板アクセント(頭高型)で読むのが一般的ですが、地域によっては「トリクミ↘」と語尾が下がるケースもあります。日本語アクセント辞典でも前者が標準とされているため、公的な場では平板型を意識しましょう。
会議やプレゼンで読みを誤ると専門性に疑いを持たれる恐れがあるため、「取組(とりくみ)」と括弧付きで1度提示しておくと安心です。読みを示すことで、文脈に不慣れな聴衆にも配慮できます。
「取組」という言葉の使い方や例文を解説!
取組は「○○への取組」のように目的語とセットで使用するのが基本です。特にビジネスではKPIやKGIと結びつき、成果指標が明確な文脈で重宝されます。
【例文1】当社はプラスチック削減への取組を強化します。
【例文2】自治体の防災取組が地域住民の安心につながった。
【例文3】社員の健康増進取組により医療費が10%削減された。
例文に共通するのは「目標」「主体」「行動内容」が一文で示され、読者が成果をイメージしやすい点です。日常会話では「ダイエットの取組が続かない」といった、自分自身の努力を指すライトな用法もあります。
取組を使う際の注意点は、単なるアイデアや意向だけでは不十分ということです。「計画策定→実行→評価」のプロセスを含まなければ、言葉の重みが薄れるため、相手に誤解を与えます。ビジネスメールでは、取組の具体的スケジュールや数値目標を併記することで信頼度が格段に高まります。
「取組」という言葉の成り立ちや由来について解説
「取組」は動詞「取る」と「組む」を連結した名詞化表現で、江戸時代の相撲用語が語源とされています。当時「取組」は力士同士が組み合う番付上の対戦カードを指し、「今日の取組は○○vs△△」のように使われました。
そこから「相対して全力を尽くす行為」へと意味が拡張し、明治期に入るとビジネスや教育でも用いられるようになりました。現代日本語ではスポーツ色が薄れ、プロジェクト管理の概念と結びついたことで「総合的な取り掛かり」という広義の意味を帯びています。
漢字だけ見ると中国語由来の熟語に見えますが、実際は和製漢語であり、日本国内で独自に発展しました。したがって海外では直訳が難しく、“initiative”や“effort”など複数の英単語で説明するのが一般的です。この点は多言語資料作成時の留意事項となります。
「取組」という言葉の歴史
江戸中期の相撲番付表に「今日之取組」という記述が見られるのが文献上の最古の例とされます。その後、明治政府が殖産興業を掲げた際、報告書に「各府県の取組」という表現が登場し、行政分野へ浸透しました。
大正から昭和初期にかけては工場法や教育勅語の解説書で「衛生取組」「徳育取組」などの記述が増え、国策の周知語として機能しました。戦後はGHQの影響を受けた行政改革で「改革取組計画」という語が登場し、計画書のテンプレートとして定着します。
高度経済成長期には企業が「品質管理取組」を掲げてTQCを推進し、平成以降はCSR報告書で「社会貢献取組」が定番となりました。2020年代にはSDGsの普及に伴い「サステナビリティ取組」がキーワード化し、国際的な枠組みの中で再評価されています。このように「取組」は時代ごとに注目テーマを取り込みながら進化を続けていると言えるでしょう。
「取組」の類語・同義語・言い換え表現
取組と近い意味を持つ言葉には「施策」「活動」「プロジェクト」「取り組み(送り仮名付き)」などがあります。ビジネス文脈では「イニシアチブ」「アクションプラン」もほぼ同義です。
類語の中でも「施策」は政策的・制度的なニュアンスが強く、「活動」は個々の行為に視点があり、取組より範囲が狭い場合があります。一方「プロジェクト」は期間やチームが限定される点で、継続的に改善を重ねる取組とは目的が異なる場合もあります。
言い換えに迷った際は「目的の明確さ」「計画性」「継続期間」の3軸で比較すると便利です。たとえば短期集中なら「プロジェクト」、制度化されているなら「施策」、広報向けなら「取組」がフィットします。適切な用語選択により、読者に伝わる情報量が格段に変わるため注意しましょう。
「取組」と関連する言葉・専門用語
取組とセットで用いられる専門用語に「PDCAサイクル」「KPI」「ロードマップ」「アクションプラン」などがあります。これらは取組を体系立て、進捗を測定するツールとして欠かせません。
たとえば「KPI」は取組の効果を測定する指標であり、「ロードマップ」は取組を時間軸で可視化する資料を指します。どちらも取組の透明性を高め、利害関係者への説明責任を果たす役割を担います。
さらにISOマネジメントシステムやESG投資の文脈では「マテリアリティ」「ステークホルダー」という概念も登場します。これらは取組の優先順位や対象範囲を決めるための分析概念で、国際的にも通用するフレームワークです。専門用語と組み合わせることで、取組は単なる意気込みではなく、科学的・論理的な計画として位置づけられます。
「取組」を日常生活で活用する方法
取組はビジネス用語のイメージが強いものの、個人の生活改善にも応用できます。まず目標を1つ設定し、達成基準を数値化することで、取組の骨格が出来上がります。
例として「1か月で体脂肪率を2%減らす取組」を立てる場合、食事記録アプリ導入や週3回の筋トレをアクションプランとします。途中経過を体組成計で測定し、結果をグラフ化すればPDCAが回せます。
家計管理でも「年間貯蓄額を20万円増やす取組」を掲げ、固定費見直しと副収入確保の具体策を実行すると、計画性のある改善が可能です。取組という言葉を使うことで、日常の目標がプロジェクト化され、モチベーションが維持しやすくなります。
「取組」についてよくある誤解と正しい理解
「取組」は壮大な計画でなければ使えないと誤解されがちですが、実際には小規模でも構いません。重要なのは目的と行動がセットになっているかどうかです。
また「取組=成功した施策」と受け取られることがありますが、取組そのものは成功・失敗を問いません。むしろ評価を前提にしているため、失敗した場合も教訓として次の取組へ活用されます。
さらに「取組を宣言したら途中で変更できない」という思い込みもあります。実際には状況に応じて見直し、軌道修正することこそ取組の本質です。柔軟性を失うと形骸化し、形だけのスローガンになってしまう点に注意しましょう。
「取組」という言葉についてまとめ
- 「取組」とは、目的達成のために計画的な行動を行うプロセス全体を指す語。
- 読み方は「とりくみ」で、漢字と送り仮名なし表記が公的文書で一般的。
- 相撲の対戦カードが語源で、明治期以降に行政・教育などへ拡大した。
- 現代ではPDCAやKPIと結びつき、評価と改善を伴う点が重要な特徴。
取組は歴史的に相撲から派生し、行政・産業の発展に合わせて意味を拡張してきた言葉です。現在では目標と計画性を備えた行動全般を表し、ビジネスはもちろん日常生活でも応用できます。
計画・実行・評価をワンセットで考える姿勢が取組の核心であり、単なるアイデアや努力と線引きするポイントになります。今後もSDGsやDXなど新たな潮流と結びつきながら、社会の変化を映す鏡として進化し続けるでしょう。