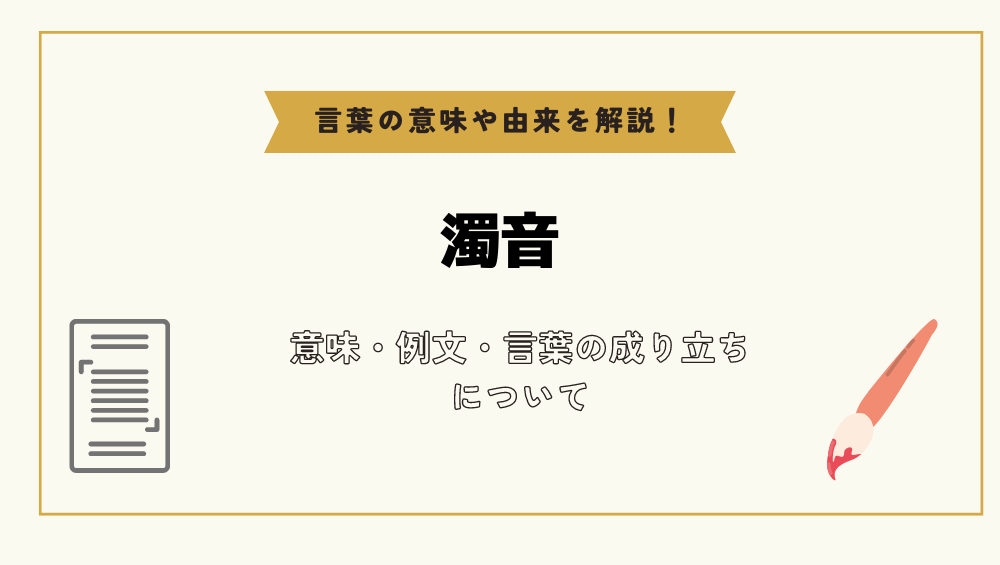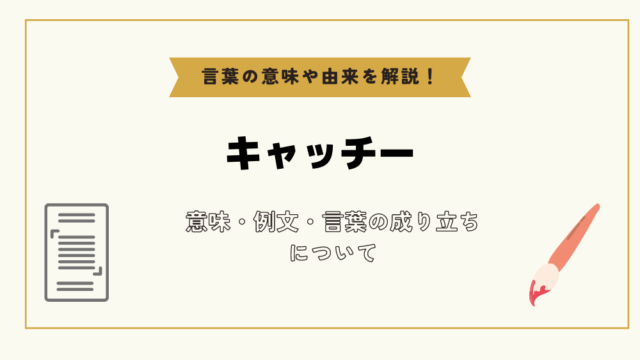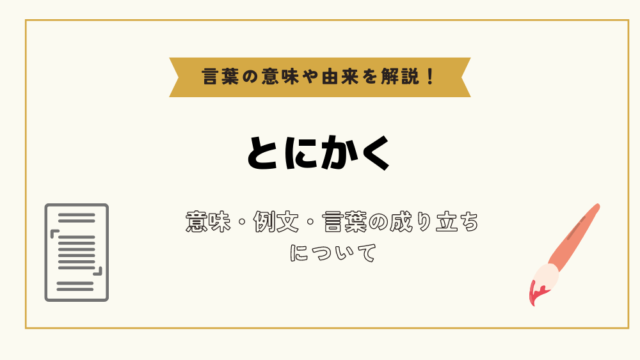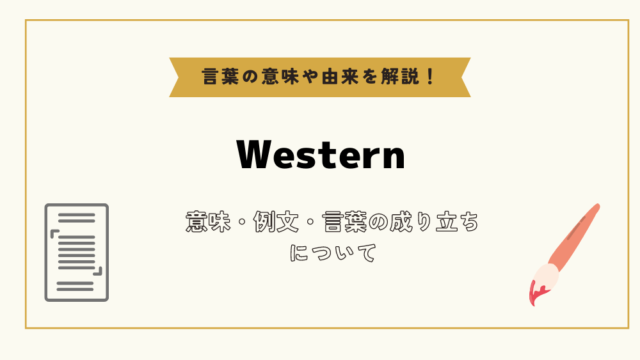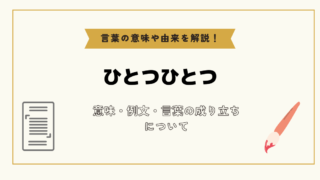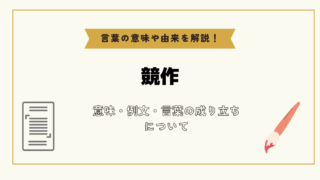Contents
「濁音」という言葉の意味を解説!
「濁音」とは、日本語の音響現象のひとつで、子音の音声のうち、声門を通って発音される音を指します。
これによって、清音と区別される音のことを指しています。
濁音は日本語の特徴的な要素であり、言語の表現力を豊かにします。
「濁音」という言葉の読み方はなんと読む?
「濁音」は、「だくおん」と読みます。
漢字の「濁」は、水の中に泡が立つさまを表現しており、音にも「ぶく」という浮かび上がるイメージが込められています。
このようなイメージから、「濁音」という言葉が付けられたのです。
「濁音」という言葉の使い方や例文を解説!
「濁音」という言葉は、主に言語や音声学の分野で使われます。
例えば、日本語の発音練習をする際には、濁音と清音の違いを意識しながら練習することが重要です。
また、濁音は日本語の文法や語彙にも関連しており、文章や会話において正確な発音をするためには、濁音の適切な使い方を理解する必要があります。
「濁音」という言葉の成り立ちや由来について解説
「濁音」という言葉は、日本語の音声の特徴を表現した言葉です。
漢字の「濁」には、浮かび上がるようなイメージが込められており、声門を通って発音される音の特徴を表しています。
言語学の観点からは、日本語の音声の特徴を分析し、それを「濁音」という言葉で表現したものと言えます。
「濁音」という言葉の歴史
「濁音」という言葉は、日本語の音声学の研究や言語学の分野で使われるようになりました。
明治時代以降、日本語の発音や音韻に関する研究が進み、その中で「濁音」の概念が一般化されました。
以来、日本語教育や言語学の分野で「濁音」という言葉が定着し、普及しています。
「濁音」という言葉についてまとめ
「濁音」という言葉は、日本語の音声の特徴を表現したものです。
声門を通って発音される音を指し、清音とは異なる特徴を持ちます。
日本語の発音や文法の理解に必要な要素であり、正確な発音をするためには濁音の適切な使い方を学ぶ必要があります。
言語学の研究や教育の分野で重要な概念とされ、日本語の特徴的な要素のひとつです。