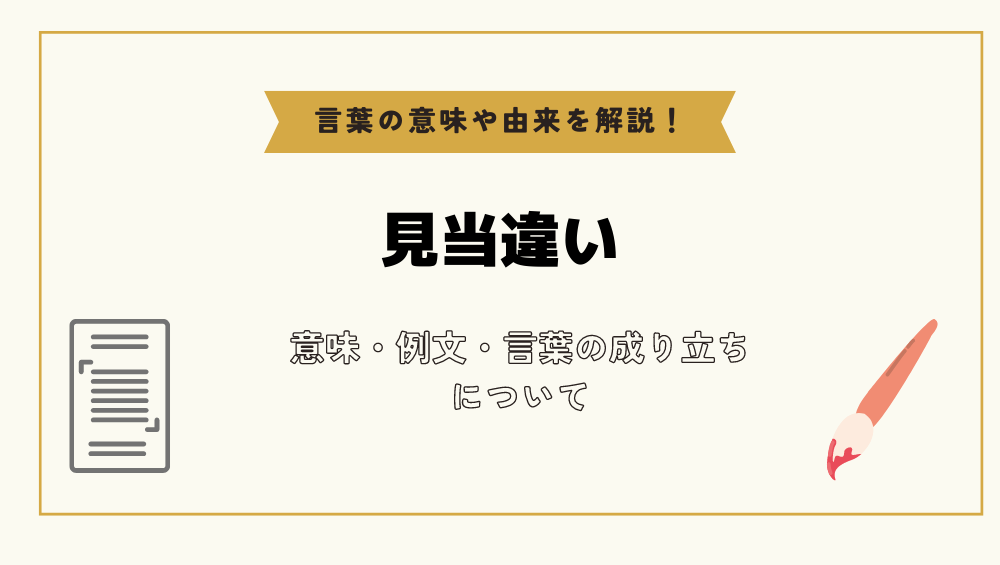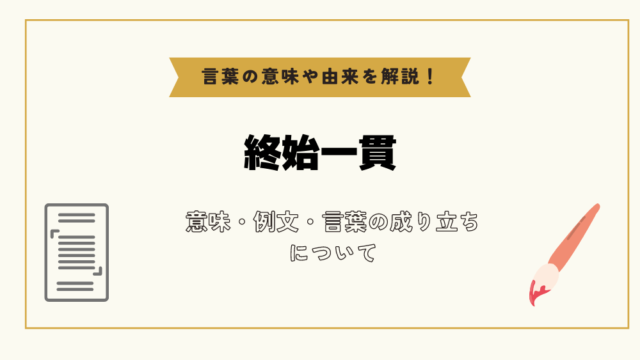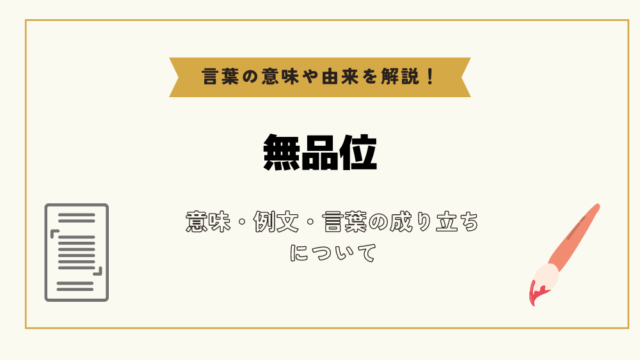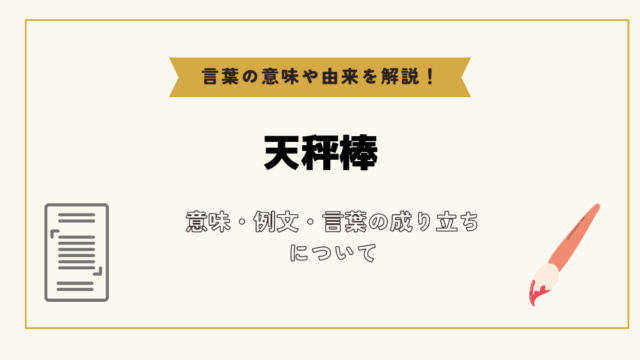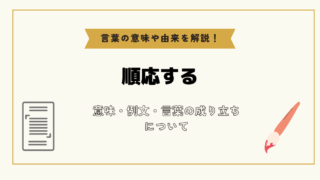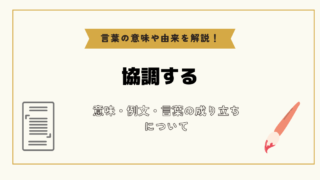Contents
「見当違い」という言葉の意味を解説!
「見当違い」という言葉は、物事の正しい判断や予測が外れることを指します。
つまり、予想と現実が合わず、期待と実際が乖離している状況を指しています。
例えば、友達が新しい仕事に興味を持っていて、その仕事に対して大いに期待して応募するものの、実際には自分の予想とは全く違う状況だった場合、「見当違い」な結果となります。
この言葉は、予測の外れることを表した表現として使われています。
「見当違い」の読み方はなんと読む?
「見当違い」は、「けんとうちがい」と読みます。
漢字の「見当」は「正しい位置や範囲を予想すること」を意味し、「ちがい」は「間違い」という意味です。
両方を組み合わせることで、「予測と実際が合わないこと」という意味が生まれるのです。
「見当違い」という言葉の使い方や例文を解説!
「見当違い」という言葉は、予想が外れた状況を表す際に使われます。
例えば、友人に「今日は寒いから暖かい服を着て行った方がいいよ」と忠告したのに、その友人が薄着で現れた場合、。
「あなたの服装は見当違いだね」と言うことができます。
このように、予測と現実との乖離を表現する際に「見当違い」という言葉が使用されます。
「見当違い」という言葉の成り立ちや由来について解説
「見当違い」の成り立ちは、「見当」という意味が「正しい位置や範囲を予想すること」という意味を持っている点に起因しています。
そして、「ちがい」という言葉が「間違い」という意味を持つことから、「予測が外れること」という意味が生まれたのです。
このように、言葉の成り立ちは、それぞれの漢字の意味が組み合わさることで形成されます。
「見当違い」という言葉の歴史
「見当違い」という言葉の歴史は、江戸時代にまで遡ります。
当時の文献にも既に使用されていたことが確認されています。
現代でも、この言葉は日常会話や文学作品などでよく使用されており、その使用頻度は非常に高いです。
日本語の豊かさや表現力を示す一例と言えるでしょう。
「見当違い」という言葉についてまとめ
「見当違い」という言葉は、予測と現実が乖離した状況を表すために使用されます。
予想が外れてしまうことは誰にでも起こり得ることであり、日常生活でもよく経験することです。
この言葉は、そのような状況を的確に表現するために使われ、日本語の豊かさを示す言葉の一つとして存在しています。