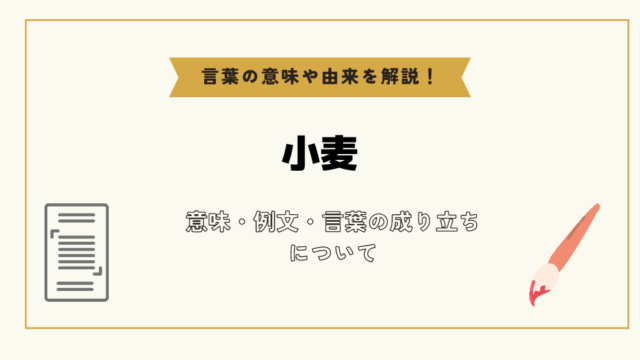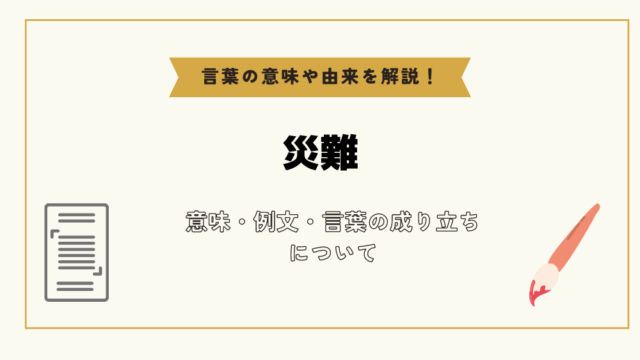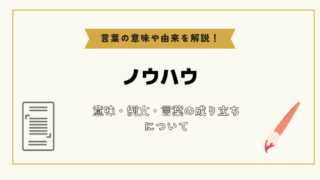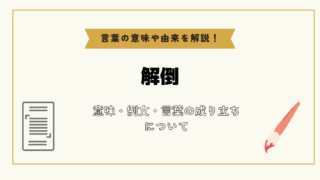Contents
「怪訝」という言葉の意味を解説!
「怪訝(けげん)」とは、驚いたり不審に思ったりする様子を表す言葉です。
何かが予想と違ったり、理解しづらかったりするときに使用されます。
例えば、友達が突然怪しい行動をしたり、意外な発言をしたりすると、私たちは「怪訝だな」と感じることがあります。
。
このように、「怪訝」は他人の言動に対して驚きや不審を抱く感情を表す言葉として使われます。
「怪訝」という言葉の読み方はなんと読む?
「怪訝」は、「けげん」と読みます。
漢字の意味通り、不審や疑念を抱く様子をイメージしながら読むと覚えやすいですね。
「怪訝」という言葉の使い方や例文を解説!
「怪訝」は直接的に使われることは少なく、より口語的な表現として使われることが多いです。
例えば、「彼の態度が怪訝だったので、何かあったのか尋ねてみました。
」と言ったり、「怪訝な顔をされてしまったので、自分の言葉遣いに問題があったのかと思いました。
」と言ったりすることがあります。
。
このように、「怪訝」は相手の行動や表情に対して不審を抱く時や、自分自身の言葉や行いに問題があるのではないかと疑念を持つ時に使われることが多いです。
「怪訝」という言葉の成り立ちや由来について解説
「怪訝」は、漢字の「怪」と「訝」の組み合わせで構成されています。
「怪」は、驚きや不思議さを表し、「訝」は疑問や不審を意味します。
。
この2つの漢字が合わさって「怪訝」となり、驚きや不審を抱く様子を表す言葉になりました。
「怪訝」という言葉の歴史
「怪訝」は、江戸時代から使われてきた言葉です。
当時の人々は、現代と同じように相手の行動や表情に対して驚きや不審を感じることがあり、その感情を「怪訝」という言葉で表現していました。
そして、長い年月を経て、現代まで受け継がれてきたのです。
「怪訝」という言葉についてまとめ
「怪訝(けげん)」という言葉は、驚きや不審を抱く様子を表します。
相手の意外な行動や言葉に対して使われることが多く、口語的な表現としてもよく使用されます。
江戸時代から使われている言葉であり、現代でも人間味あふれる表現として親しまれています。