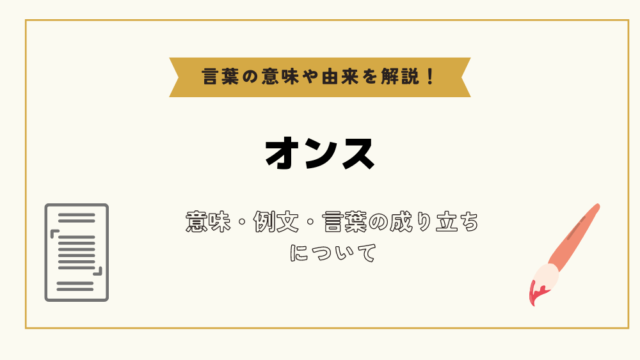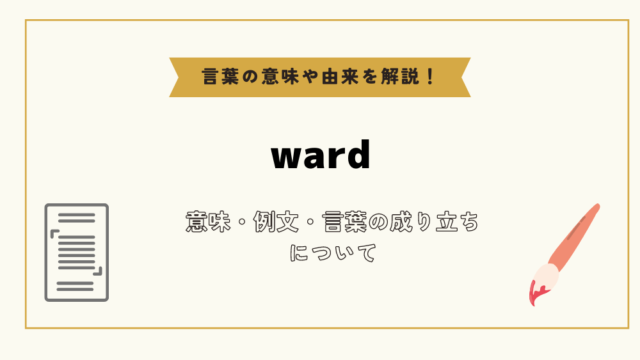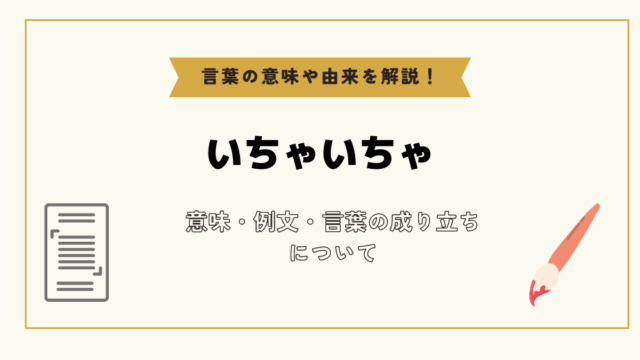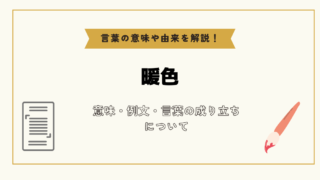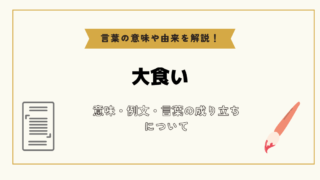Contents
「磯」という言葉の意味を解説!
「磯」という言葉は、海岸や浜辺にある岩の上を指します。
海に接する地域ではよく使われる単語です。
磯は一般に、波や風などの自然の力で形成された地形であり、海の風景や生態系を特徴づける重要な要素です。
「磯」という言葉の読み方はなんと読む?
「磯」という言葉は、「いそ」と読みます。
ただし、地域によっては「しょ」と読むこともあります。
どちらの読み方も一般的ですので、場合に応じて使い分けることが大切です。
「磯」という言葉の使い方や例文を解説!
「磯」は、海や海岸に関連する文脈で使われることが多いです。
例えば、「磯に立つ」という表現は、海に立ち寄って立ち止まることや、海辺での散歩や釣りなどのイメージを想起させます。
「磯遊びを楽しむ」という表現もあります。
ここでの「磯遊び」とは、磯での潮干狩りや海水浴など、海辺での楽しみ方を指します。
「磯」という言葉の成り立ちや由来について解説
「磯」という言葉は、古くは「石磯」と書かれていました。
これは、海辺にある石や岩が集まった地点を指す言葉です。
その後、漢字の変遷により「磯」と書かれるようになりました。
磯は、波や風によって地形が変化しやすいため、昔から漁師や海の近くで生活する人々にとっては重要な存在でした。
「磯」という言葉の歴史
「磯」という言葉の歴史は古く、日本の文学や歌にも登場します。
例えば、古代の歌人・大伴家持が詠んだ歌「磯の石ぞ波にうちわたる」は有名です。
また、近代の小説家や俳句の名手たちも、磯を題材に多くの作品を生み出してきました。
磯は、その美しさや豊かな生態系などが人々を魅了してきたのでしょう。
「磯」という言葉についてまとめ
「磯」という言葉は、海岸や浜辺にある岩の上を指す単語です。
海や海岸に関連する文脈で使われ、海辺での散歩や釣り、潮干狩りや海水浴といった楽しみ方をイメージさせます。
「磯」の成り立ちは「石磯」から変化してきたものであり、漁師や海の近くで生活する人々にとっては重要な存在だったと言えます。
また、日本の文学や歌にも登場するなど、その美しさや魅力が多くの人々を惹きつけてきました。