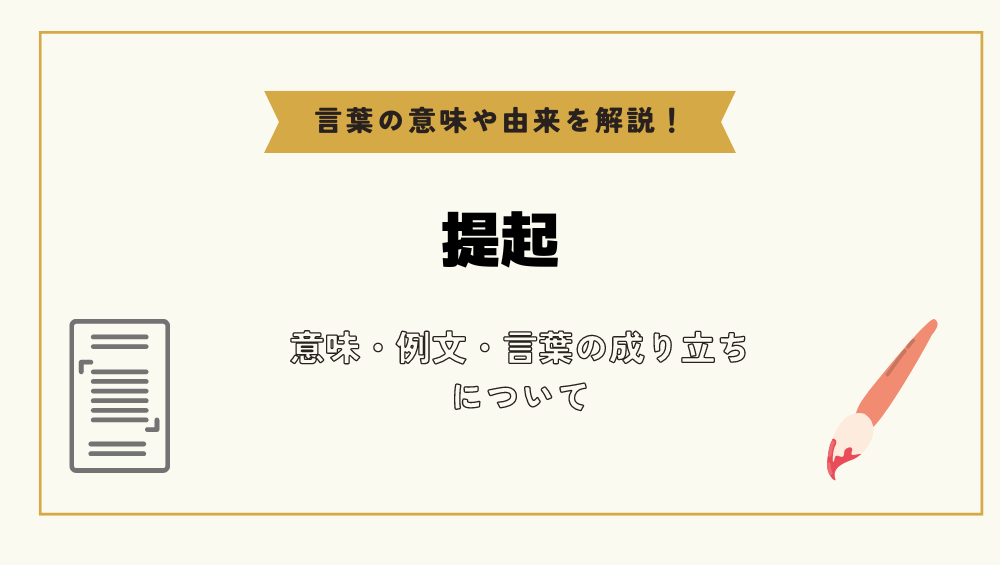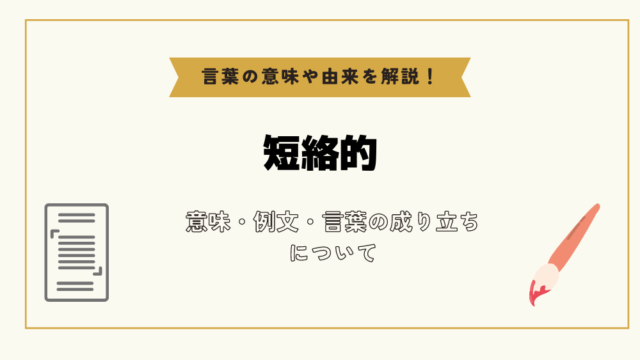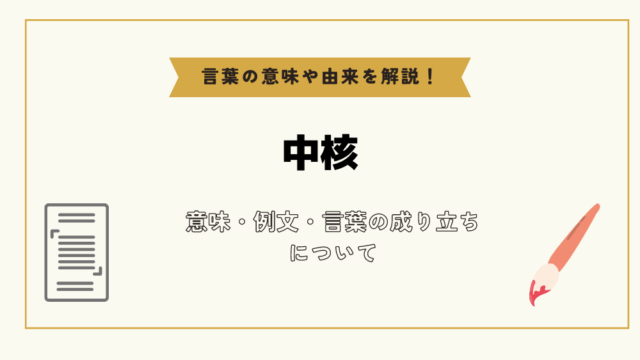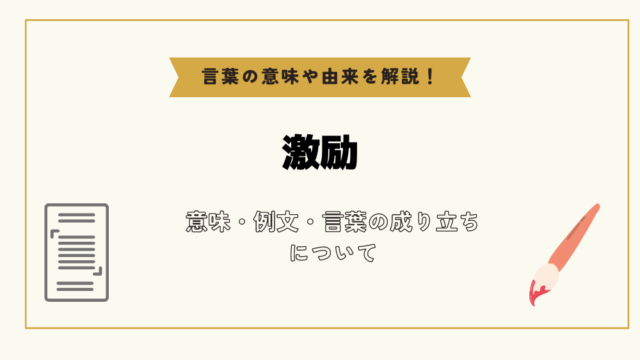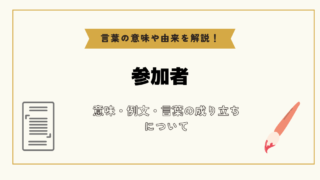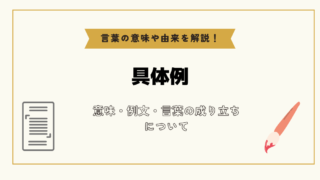「提起」という言葉の意味を解説!
「提起」とは、問題・課題・訴えなどを公の場に取り上げ、検討や議論の対象にすることを意味します。この言葉は法律、ビジネス、学術など多様な分野で使われ、単に「言及する」より踏み込んで「正式に取り上げる」というニュアンスがあります。たとえば裁判所に訴訟を起こす場合の「訴え提起」や、経営会議で新しい課題を「提起」する場面が典型例です。
\n。
提起の対象は「問題」だけに限られず、提案・疑問・改善策など幅広く含みます。日常会話では「〜について提起したいのですが」と前置きすると、聞き手に「ここから大事な話が始まる」ことを予告できます。
\n。
さらに「提起」は「提出」「提示」「提案」と混同されがちですが、提出は書類を渡す行為、提示は見せる行為、提案は解決策の提示を意味し、提起は「議論の場に載せる行為」だと整理できます。
\n。
つまり提起は、物事をスタートラインに乗せ、人々が向き合うきっかけをつくる強い動詞です。この特徴を踏まえておくと、文章でも会話でも適切に使い分けられるようになります。
「提起」の読み方はなんと読む?
「提起」は「ていき」と読みます。音読みのみで構成され、訓読みや混読はありません。
\n。
「提」は「さげる・もちあげる」の意を持ち、「起」は「おこす・たつ」の意を持ちます。この二字が結びつくことで「話題を持ち上げ、立ち上げる」というイメージが生まれます。
\n。
読み間違いとして最も多いのは「ていおこし」や「ひきおこし」で、いずれも誤用です。書面では正しく「ていき」とルビを振るか、ふりがなを付けると安心です。
\n。
なお「提」も「起」も常用漢字内のため、公文書や契約書でもそのまま使用できます。
「提起」という言葉の使い方や例文を解説!
提起はフォーマルな場面で多用される一方、日常でも応用できます。「問題を提起する」「疑問を提起する」のように、目的語として扱う名詞が広いのが特徴です。
\n。
コツは、単に「言う」「出す」より強いインパクトが必要なときに選ぶことです。場を動かし、周囲を巻き込むイメージで使うとしっくりきます。
\n。
【例文1】研究会で新たな仮説を提起した結果、活発な議論が生まれた。
【例文2】株主総会で経営陣の報酬体系に疑問を提起する株主が増えている。
\n。
【例文3】先生は環境問題の深刻さを提起し、生徒に行動を促した。
【例文4】市民団体が行政に公共施設のバリアフリー化を提起した。
\n。
例文からわかる通り、提起の主語は個人・団体いずれも可能です。また「提起された課題」「提起されるべき論点」のように受け身形も自然に使用できます。
「提起」という言葉の成り立ちや由来について解説
漢字の構成から見ると、「提」は手へんに“是”と書き、もともと「手で持ち上げる」を表しました。「起」は「走る人+己」で、地面から立ち上がる動作を示す象形文字です。
\n。
この二字を合わせることで「手で持ち上げて立たせる=話題を世に持ち上げる」比喩表現が誕生したと考えられています。古代中国の文献には「提起」の語は見当たりませんが、「提」と「起」を並べて使う用例があり、日本語に取り込まれる過程で熟語化したとみられます。
\n。
明治期には欧米法を取り入れる翻訳語として「提起」が定着しました。特に「訴訟提起」という法律用語は、英語の“bring an action”に対応する訳語として採用されています。
\n。
そのため「提起」は外来概念を日本語漢語で表現した明治新造語の一種と位置づけられます。
「提起」という言葉の歴史
江戸以前の文献には「提起」の熟語がほぼ見られず、明治維新後の法律翻訳が出発点とされます。司法制度が近代化される中で、裁判所に訴えを「提起」する手続きが条文に明記されました。
\n。
大正〜昭和期には新聞や雑誌が「問題提起」という表現を多用し、一般社会にも浸透しました。これにより法律用語から社会用語へと守備範囲が拡大したのです。
\n。
戦後は学術界や広告業界でも普及し、1970年代の市民運動・学生運動ではスローガンとして頻繁に登場しました。現代ではSNSでも「提起」という単語がハッシュタグ化し、気軽に使用されています。
「提起」の類語・同義語・言い換え表現
「提起」と近い意味を持つ言葉には「提示」「提出」「発議」「問題提案」「喚起」などがあります。
\n。
ただし完全に置き換えられるわけではなく、ニュアンスの違いを押さえることが重要です。たとえば「提示」は情報を示す行為、「提出」は書類を渡す行為、「発議」は会議の議題として正式に提出する行為を指します。
\n。
「喚起」は注意や関心を呼び起こす意味が強く、議論の場に乗せるかどうかは二次的です。文章では「〜を提起する」の繰り返しを避けたいとき、「〜を発議する」「〜を提示する」といった表現でリズムを調整できます。
「提起」を日常生活で活用する方法
提起というと堅いイメージがありますが、家庭や友人同士でも応用可能です。家族会議で「来年の旅行先について提起したい」と言えば、和やかに討議が始まります。
\n。
ポイントは「場を整え、相手への配慮を示しつつ、核心を明確にする」ことです。単に意見をぶつけるのではなく、議論の土俵を設けるイメージで使うと、対話が建設的になりやすいからです。
\n。
仕事のメールでは「本件について以下の三点を提起させていただきます」と前置きし、箇条書きで要点を示すと読み手に負担をかけません。子育ての場では、子どもに「なぜ学校で宿題が必要なのか」を疑問として提起させ、主体的に考えさせる教育手法も有効です。
「提起」についてよくある誤解と正しい理解
「提起」は批判的・攻撃的な言葉だと誤解されることがあります。しかし実際には議論の入口を作る行為であり、必ずしも否定的ではありません。
\n。
もう一つの誤解は「提起=解決策を示すこと」とするものですが、提起は問題を掲げる段階であり、解決策提示とは別工程になります。この違いを押さえないと、議論が途中で空中分解する恐れがあります。
\n。
また「提起したから責任を負う必要はない」と考えるのも誤りです。議題を持ち込む以上、説明責任や論拠の提示が求められます。適切な根拠を準備し、建設的な議論に導く姿勢が大切です。
「提起」という言葉についてまとめ
- 「提起」とは、問題や課題を正式に取り上げて議論の場に載せる行為を指す語。
- 読み方は「ていき」で、書面でも口頭でも同じ表記・発音を用いる。
- 明治期の法律翻訳で生まれ、訴訟提起を通じて社会に広まった歴史を持つ。
- 使用時は根拠と説明責任を伴い、単なる発言より強い意味を持つ点に注意する。
提起は議論のスタートラインを作り、物事を前進させるために欠かせない概念です。読み書きはシンプルですが、持つインパクトは大きく、適切な場面で使うことでコミュニケーションを円滑にします。
法律・ビジネス・日常のいずれにおいても、提起の背後には「責任を持って課題を共有する」という倫理が必要です。この記事を参考に、あなた自身の現場で効果的に「提起」を活用してみてください。