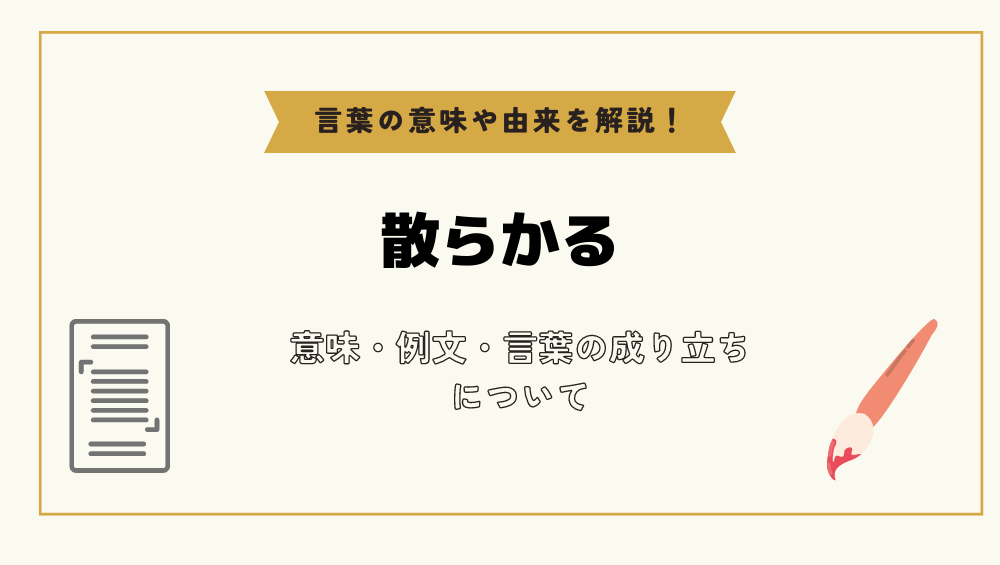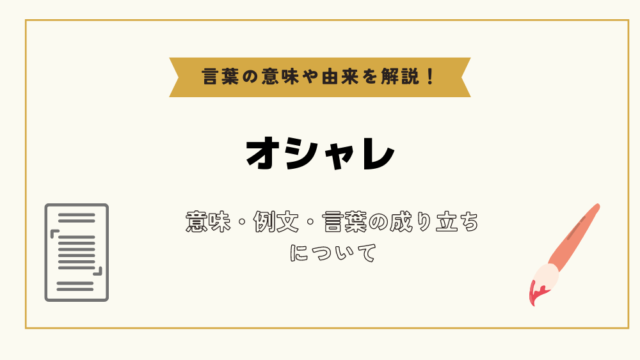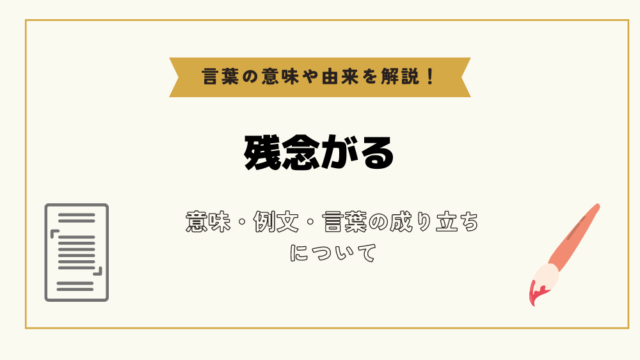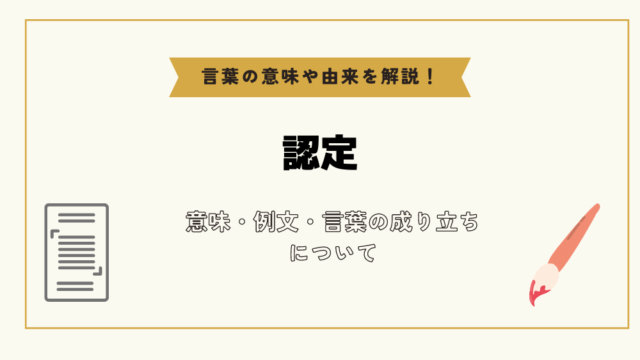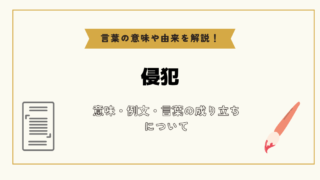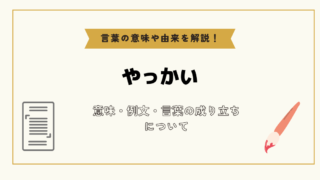Contents
「散らかる」という言葉の意味を解説!
「散らかる」とは、物や場所が乱れて整理されていない状態を指す言葉です。
散らばる、乱れるといった意味合いを持ちます。
例えば、自室が散らかっているときは、物が散乱していたり、整理整頓されていなかったりする状態を指します。
「散らかる」という言葉の読み方はなんと読む?
「散らかる」は、「ちらかる」と読みます。
これは日本語の特徴的な読み方で、漢字の「散」は「チャン」という音で読まれることが一般的ですが、この言葉では「チ」の部分が「チ」ではなく「チィ」となって「ち」と読まれる特例です。
「散らかる」という言葉の使い方や例文を解説!
「散らかる」という言葉は、物や場所が乱れて整理されていない状態を表現するときに使います。
例文をいくつかご紹介しましょう。
。
1. 「部屋がいつも散らかっていて探し物がなかなか見つからない。
」
。
2. 「机の上が散らかっていて、集中できない。
」
。
3. 「子供たちのおもちゃが散らかっていて通り道が狭くなってしまった。
」
。
このように、「散らかる」という言葉は日常生活でよく使用される言葉であり、乱れた状態や整理されていない様子を表現する際に便利です。
「散らかる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「散らかる」という言葉は、古くから使用されてきた日本語です。
その成り立ちは、漢字の「散」と「かる」という部分が合わさることで形成されました。
漢字の「散」は、物事がばらばらに分散する、広がるといった意味を持ち、「かる」は、「解ける」「乱れる」といった意味を持ちます。
これらが組み合わさって、「散らかる」という言葉が生まれたのです。
「散らかる」という言葉の歴史
「散らかる」という言葉の歴史は古く、日本語が発展していく中で生まれました。
具体的な起源については明確な記録は残されていませんが、日本語として使われるようになったのはかなり昔からであると考えられています。
日本の風土や文化に根付いた概念であるため、古代から言葉として存在していたと言えるでしょう。
「散らかる」という言葉についてまとめ
「散らかる」とは、物や場所が乱れて整理されていない状態を表現する言葉です。
読み方は「ちらかる」となります。
日常生活でよく使われ、物事の乱れた様子や整理されていない状況を表現する際に利用されます。
この言葉は古くから使用されており、日本語の風土や文化に根付いた言葉として成り立っています。