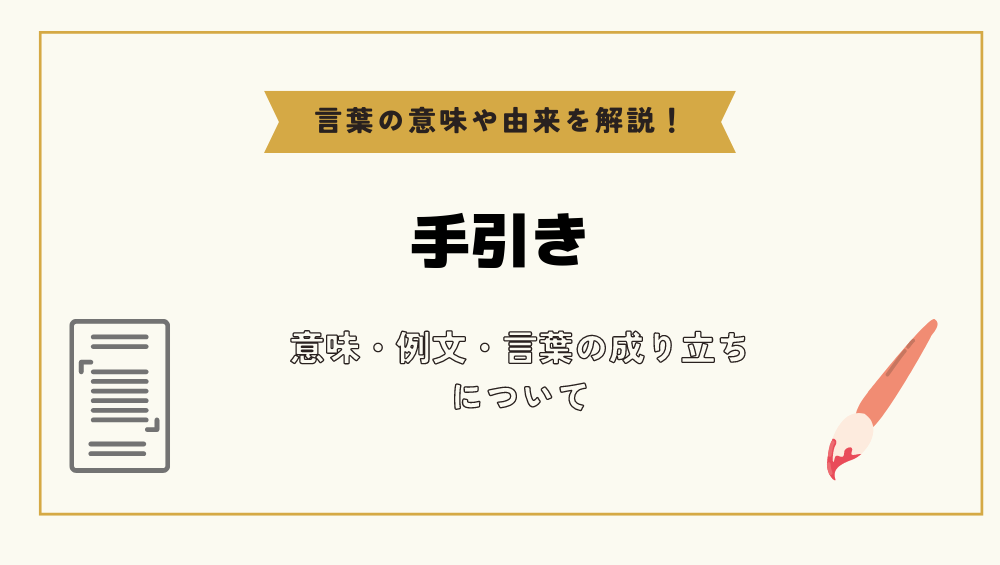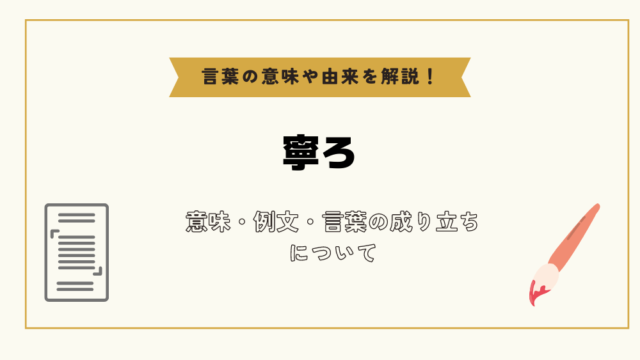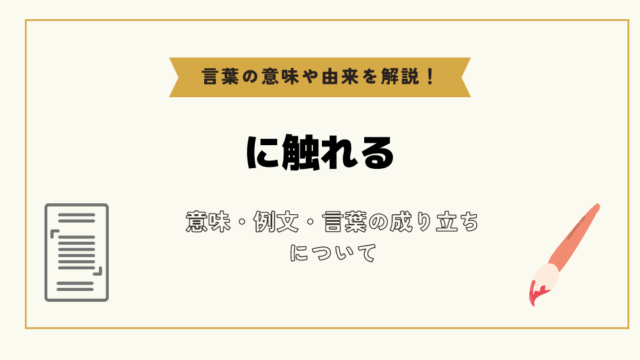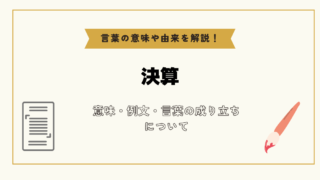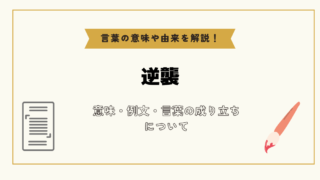Contents
「手引き」という言葉の意味を解説!
手引きとは、指導や案内をすることを指す言葉です。
何かを始める際に、人々が必要な情報や方法を提供する役割を果たします。
手引きは新しいことに挑戦する人々にとって非常に重要な存在であり、道案内のような役割を果たします。
例えば、旅行先で地図や案内板を使って観光名所を巡る際、手引きがなければ迷ってしまうことでしょう。
また、ビジネスにおいても、新入社員が仕事を覚える際に上司や先輩が手引きをしてくれると、効率的に業務を覚えることができます。
「手引き」という言葉の読み方はなんと読む?
「手引き」の読み方は「てびき」となります。
この言葉は「て」と「びき」という2つの文字から構成されています。
「て」は手、そして「びき」は引くことを意味します。
このように、読み方からも手引きの意味や役割が想像できます。
「手引き」という言葉の使い方や例文を解説!
「手引き」は、特定の目的を達成するために他の人を指導したり案内したりする際に使用される表現です。
例えば、会議で新しいプロジェクトに参加するメンバーに対して、リーダーが手引きをすると、スムーズにプロジェクトに取り組むことができます。
「手引き」はまた、旅行ガイドが観光客に対して観光地の案内をする際にも使われます。
ガイドが観光客に対して観光名所の特徴や歴史、アクセス方法などを手引きすることで、観光客はより楽しい旅行ができます。
「手引き」という言葉の成り立ちや由来について解説
「手引き」は「手」と「引く」の2つの言葉から成り立っています。
「手」とは、人が物を掴むために使う部分であり、また人や物を支えるためにも使われます。
「引く」とは、力を加えて物を自分の方へ動かすことを意味します。
このように、「手引き」という言葉は、手で物を引っ張るように他の人を方向づけたり、道案内したりすることを表現したものと考えられます。
「手引き」という言葉の歴史
「手引き」という言葉の歴史は古く、江戸時代から存在していました。
当時は、農作業や工芸などの技術を後輩や子供に伝えるために使われていました。
江戸時代の農村では、先輩が手引きをして後輩を指導し、農作業の技術を教えました。
また、伝統工芸の師匠も弟子に手引きをして技術を伝えることが一般的でした。
その後も、「手引き」という言葉は広く使われ続け、現代でも指導や案内の役割を表す言葉として広く認知されています。
「手引き」という言葉についてまとめ
「手引き」は新しいことに挑戦する人々にとって欠かせない存在です。
手引きは道案内や指導をする役割を果たし、人々が目的を達成するために役立ちます。
読み方は「てびき」となり、指導や案内の際に使われる言葉です。
また、江戸時代から存在し、農作業や伝統工芸などの技術の伝承において重要な役割を果たしてきました。
手引きは人々が導かれることで、より効率的に目標を達成することができます。