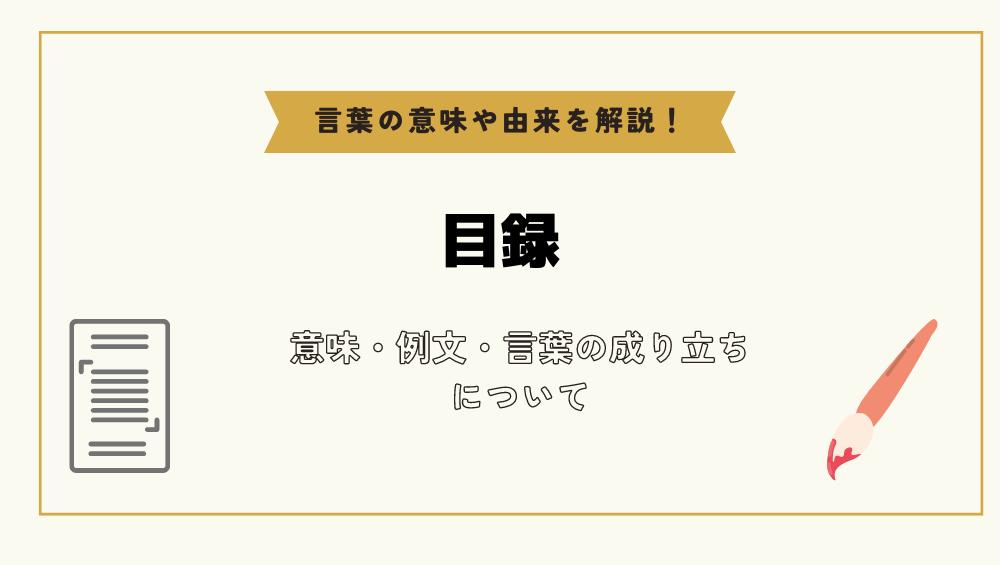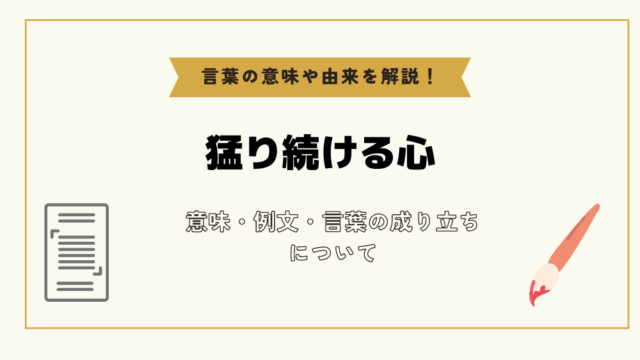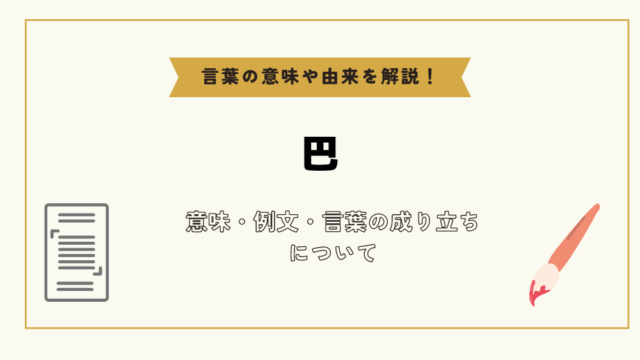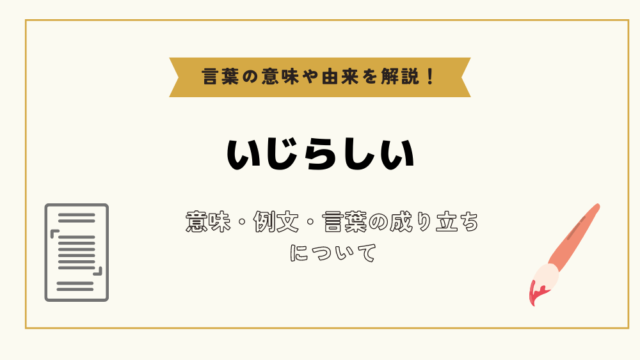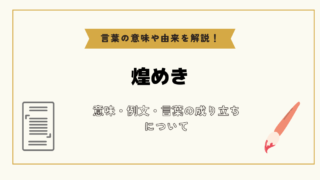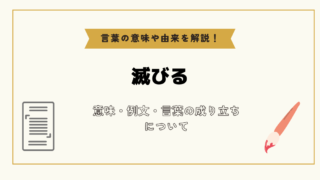Contents
「目録」という言葉の意味を解説!
「目録」という言葉は、物事や情報を整理して一覧にしたものを指します。具体的には、本や資料などを項目ごとにまとめた一覧表のことを指すことが一般的です。目録は、探し物がある時や情報を調べる時に便利に活用されます。
「目録」という言葉の読み方はなんと読む?
「目録」という言葉は、「もくろく」と読みます。この読み方は、一般的な読み方であり、日本語の辞書でも「もくろく」と表記されています。
「目録」という言葉の使い方や例文を解説!
「目録」という言葉は、本や資料などを整理する際に使われます。たとえば、図書館で本を借りる際には、まず目録を検索して本の場所や所蔵情報を調べます。また、商品のカタログやオークションの出品リストにも目録が使用され、商品の一覧や詳細情報が示されます。
例文としては、以下のような使い方が考えられます。
1. 図書館で目録を参照して、欲しい本の場所を調べました。
2. オンラインショップの目録を見ながら、欲しい商品を探しています。
「目録」という言葉の成り立ちや由来について解説
「目録」という言葉は、中国の古書の仕組みに由来しています。古代の中国では、書物や文献を整理する際に、それらの一覧表を作成しました。この一覧表が「目録」と呼ばれるようになり、その後、日本に伝わりました。現代日本では、書物だけでなく、様々な物事や情報を整理する際に「目録」の概念が活用されています。
「目録」という言葉の歴史
「目録」という言葉の歴史は古く、中国の古代から存在しています。中国では、紀元前2世紀頃から、書物を整理するための目録制度が確立されていました。また、日本でも奈良時代には目録が作成されており、古代の書物や仏教の経典を管理するために使用されていました。現代でも、目録は書物だけでなく、様々な分野で活用されています。
「目録」という言葉についてまとめ
「目録」という言葉は、物事や情報を整理して一覧にしたものを指します。本や資料の一覧表として広く使われ、図書館やオンラインショップなどで活用されています。「目録」の使い方や読み方、「目録」の成り立ちや由来、そして歴史を解説しました。