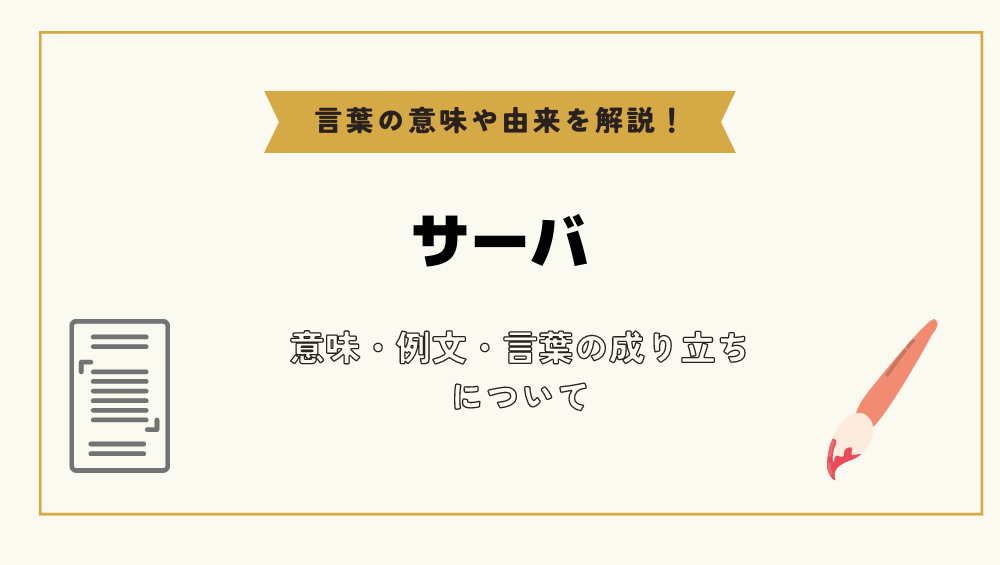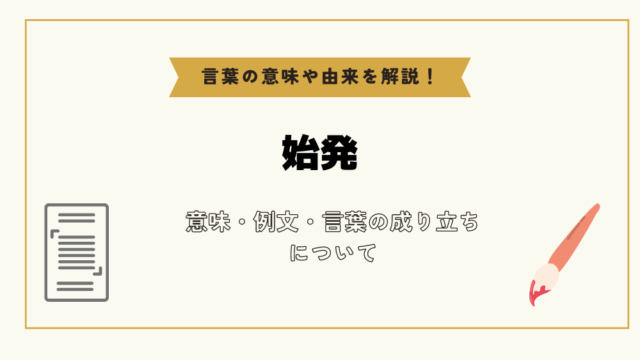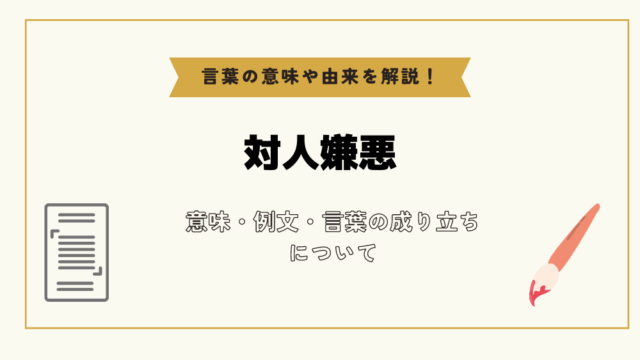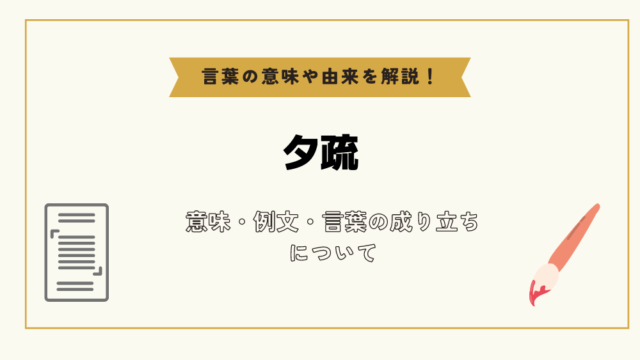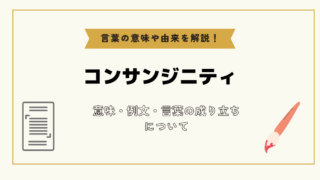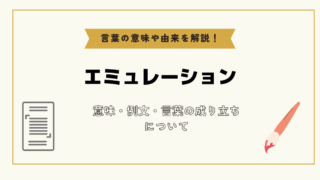Contents
「サーバ」という言葉の意味を解説!
「サーバ」とは、コンピューターネットワーク上で他のコンピューターに対して情報やサービスを提供する役割を持ったコンピューターのことを指します。
一般的な家庭用のパソコンとは異なり、サーバは高性能なハードウェアとソフトウェアを搭載しており、安定した動作と大量のリクエストの処理が可能です。
例えば、ウェブサイトのアクセス時には、ユーザーの情報を要求してきたブラウザ(クライアント)からのリクエストをサーバが受け取り、必要なデータやファイルを送り返します。
このように、サーバは情報を提供する役割を果たしているのです。
「サーバ」という言葉の読み方はなんと読む?
「サーバ」という言葉は、日本語読みで「さーば」と読みます。
英語の原音をそのままカタカナで表記したものです。
言葉自体は外来語ですが、日本語の文脈でよく使われているため、広く認知されています。
「サーバ」という言葉の使い方や例文を解説!
「サーバ」という言葉は、IT関連やウェブ業界などでよく使われます。
例えば、「ウェブサーバ」「メールサーバ」「データベースサーバ」など、特定の機能や目的を持ったサーバを指すことがあります。
また、「サーバに問題が発生している」「サーバの応答が遅い」など、サーバの動作状況やトラブルに関連した表現もよく使われます。
「サーバ」という言葉の成り立ちや由来について解説
「サーバ」という言葉は、英語の「server」という単語が由来です。
英語の「to serve」は「提供する」という意味であり、それがコンピューターネットワークの文脈で用いられるようになりました。
日本へは1980年代に導入され、その後、ネットワークの普及とともに一般的な言葉となりました。
「サーバ」という言葉の歴史
「サーバ」という言葉は、コンピューターネットワークの発展とともに普及しました。
初期のコンピューターネットワークは主に大規模な研究所や企業内で利用されていましたが、インターネットの普及により、一般の人々にもサーバの存在が広く知られるようになりました。
現在では、ウェブサイトやアプリケーションの開発など、多くの分野でサーバが重要な役割を果たしています。
「サーバ」という言葉についてまとめ
「サーバ」とは、コンピューターネットワーク上で他のコンピューターに対して情報やサービスを提供する役割を持ったコンピューターのことです。
日本語読みで「さーば」と読みます。
IT関連やウェブ業界などでよく使われる言葉で、特定の機能や目的を持ったサーバが存在します。
由来は英語で「提供する」という意味の「to serve」であり、ネットワークの普及とともに一般的な言葉となりました。