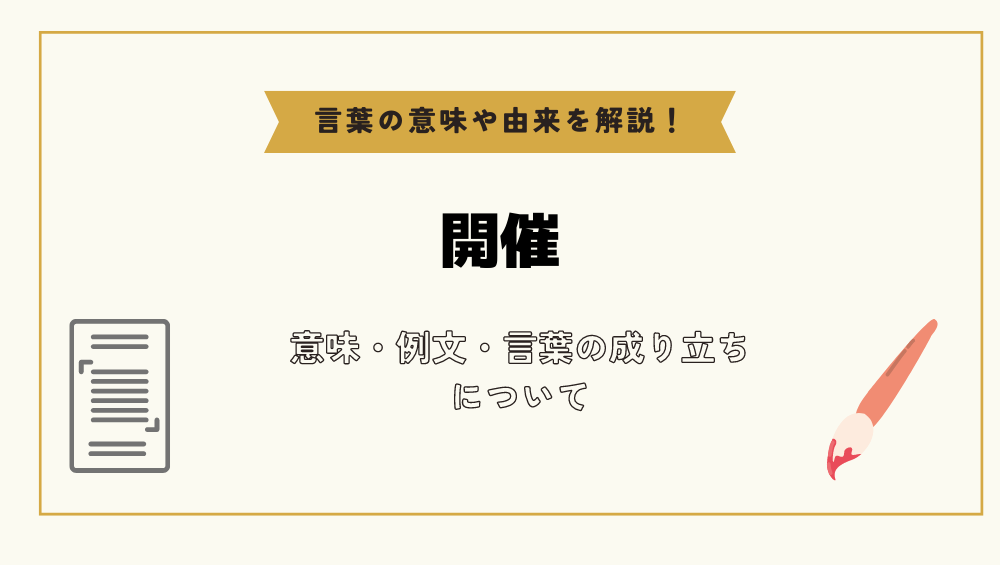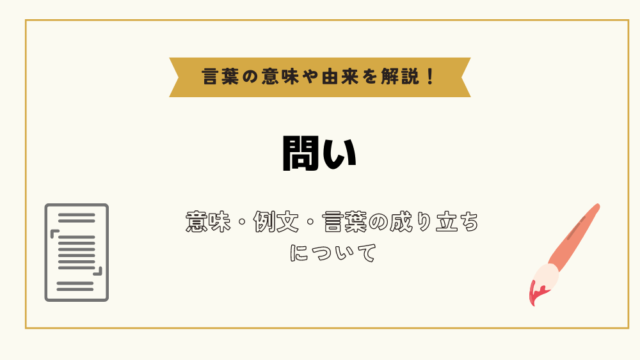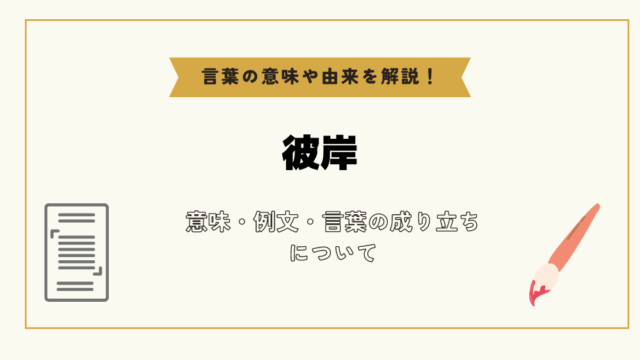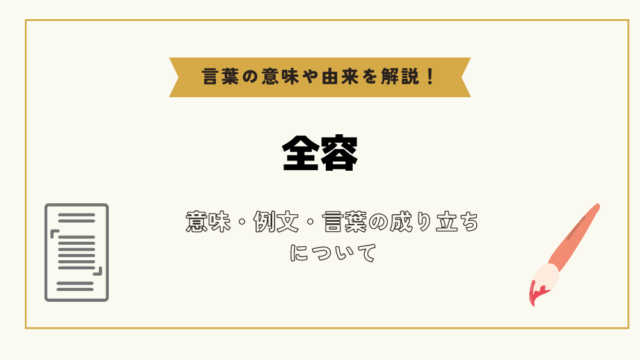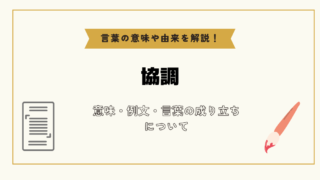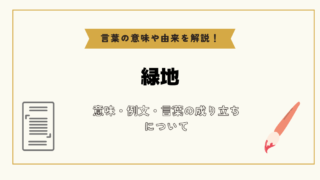「開催」という言葉の意味を解説!
「開催(かいさい)」とは、行事やイベント、会議などをあらためて設け、一定の日時・場所で実施することを指します。準備段階から当日の運営に至るまでを包括した「行事を開き、催す」という一連の行為を示すのがポイントです。英語では“hold”や“host”に相当し、単に“open”や“event”ではニュアンスが異なるため注意が必要です。
日本語における「開催」は、組織や個人が主催者となり、多数の参加者を前提とするケースで使われることが一般的です。規模の大小は特に限定されず、近所のバザーから国際会議まで幅広く適用されます。
【例文1】町内会が夏祭りを開催する。
【例文2】国連が気候変動サミットを開催した。
「開催」の読み方はなんと読む?
「開催」は音読みで「かいさい」と読みます。難読漢字ではありませんが、日常会話では「かいさいする」の発音が早口になり、「かいさえ」に近く聞こえることもあります。送り仮名は付けず「開催する」または「開催した」と活用し、ひらがな表記に崩すことはほとんどありません。
ビジネス文書や報道では、読み仮名を振らずに用いても誤読されにくい単語として定着しています。
【例文1】来週のセミナーは東京で開催します。
【例文2】定例会議の開催日程を調整する。
「開催」という言葉の使い方や例文を解説!
「開催」は動詞「する」とセットで使われるのが基本です。主語には「主催者」または「イベント名」が置かれ、目的語に「○○を開催する」とするか、「○○が開催される」と受け身にします。能動形は企画側の主体性を示し、受動形は行事自体の客観的な存在を強調できるという違いがあります。
また「開催日時」「開催場所」という形で名詞を修飾し、情報を整理する用法も便利です。文章で重複する場合は「催行」「実施」へ言い換えると読みやすくなります。
【例文1】運動会を安全に開催するためにガイドラインを作成した。
【例文2】展示会はオンライン形式で開催される予定だ。
「開催」という言葉の成り立ちや由来について解説
「開」は“ひらく”を意味し、「催」は“もよおす”を示します。「催す」は古く万葉集でも見られる語で、当時から宴や儀式を行う意がありました。二字が組み合わさった「開催」は、近代以降の公的行事の増加に伴い定着した和製熟語です。
明治期の新聞には「博覧会ヲ開催ス」の表現が頻出し、西洋型イベントを紹介するうえで便利な語として拡散しました。漢語調のため硬い印象を与えますが、今日では行政文書からSNS告知まで幅広く用いられています。
「開催」という言葉の歴史
江戸末期までは「祭(まつり)」や「会」を使うのが一般的で、「開催」はほとんど登場しませんでした。明治維新後、政府主導で博覧会・勧業博が各地で行われた際、官報や新聞で統一的に「開催」が採用され語彙が急拡大しました。戦後になると国際的なスポーツ大会や万国博覧会の告知に伴い、一般市民にもなじみのある日常語となりました。
パソコン通信やインターネットが普及し「オンライン開催」という新たな概念が登場したのは1990年代後半です。コロナ禍ではバーチャル空間での「開催」が日常化し、語の適用範囲がさらに広がりました。
「開催」の類語・同義語・言い換え表現
「開催」を別の表現に置き換えるときは文脈と規模感が鍵になります。公式度が高い場合は「挙行」「催行」「実施」が適切です。カジュアルな場面では「開く」「やる」「行う」が自然で、催し物であれば「イベントをやる」が最も口語的です。
一方、文化行事では「披露」、学術分野では「セッションを行う」、スポーツでは「試合を主催する」など専門性を帯びた語も選択肢になります。同義語を使い分けることで文章にリズムが生まれ、読者の理解が深まります。
【例文1】記念式典を挙行する。
【例文2】オンライン講座を実施する。
「開催」の対義語・反対語
「開催」の対義語として最も一般的なのは「中止」です。予定されていた行事が行われなくなる際に使われます。事前に決定する場合は「延期」も対義語的に扱われますが、厳密には時期を改めて開催する前提があるため完全な反対語ではありません。
稀に「休止」「打ち切り」が用いられることもありますが、これはシリーズ化されたイベントや番組の停止を示し、単発行事の「開催」とはややニュアンスが異なります。
【例文1】悪天候のため花火大会は中止となった。
【例文2】国際会議は感染症の拡大を受けて延期された。
「開催」と関連する言葉・専門用語
イベント運営の現場では「開催可否」「開催要項」「開催通知」など複合語が多数派生しています。特に「開催可否」はリスクマネジメントの文脈で頻繁に使われ、天候やパンデミック対応を含む意思決定プロセスを指します。
他にも「プレオープン」「レセプション」「閉会」に至るまで、開催を中心に前後のフェーズを示す語が体系化されています。国際大会では「オーガナイジング・コミッティー(組織委員会)」が開催権を握り、スポンサー契約では「タイトルホルダー」が開催名に社名を冠するケースも珍しくありません。
「開催」についてよくある誤解と正しい理解
1つ目の誤解は「開催=大規模イベント」という認識です。実際には数人の読書会でも「開催」で問題ありません。規模よりも“日時と場所を定めて行う”ことが本質だからです。
2つ目は「開催」はリアル空間のみという誤解です。オンライン会議やVRライブも開催と呼べます。最後に「開催」は主催者だけが使う語だと思われがちですが、参加者視点でも「セミナーが開催される」と受け身で表現できます。誤解を解くことで、場面に応じた適切な言葉選びができるようになります。
【例文1】友人宅でボードゲーム会を開催した。
【例文2】メタバースでファッションショーが開催された。
「開催」という言葉についてまとめ
- 「開催」とは日時・場所を定めて行事を行うことを意味する語。
- 読み方は「かいさい」で、送り仮名は付けず「開催する」と活用する。
- 明治期の博覧会報道を機に定着し、オンライン開催へと拡張している。
- 能動形と受動形の使い分けや類語との選択が円滑なコミュニケーションに重要。
「開催」はビジネス・学術・地域行事などあらゆるシーンで活用される便利な言葉です。日時と場所を確定し実施するという核心を押さえれば、規模を問わず正しく使えます。
またオンライン化の波により、リアルとデジタルの壁を越えた「ハイブリッド開催」など新しい表現も登場しています。言い換え表現や対義語を覚えておくことで、急な中止・延期の案内もわかりやすく伝えられます。
今後もイベント形態は多様化しますが、「開催」の持つ“場を設ける”という根源的な意味は変わりません。読み書きに自信を持ち、ぜひ日常やビジネスで活用してみてください。