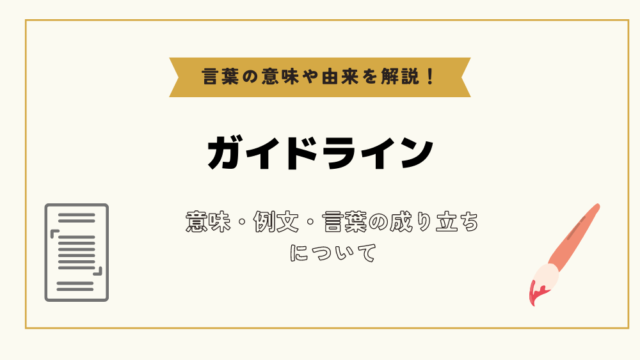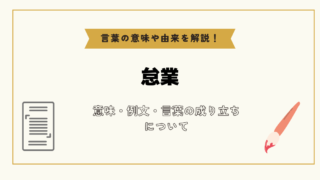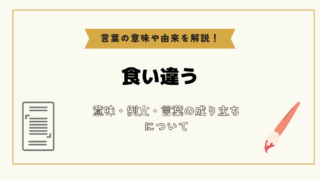Contents
「唆す」という言葉の意味を解説!
「唆す」という言葉は、他人をだまして間違った行動や考えに導いたり、悪影響を与えたりすることを意味します。
ひそかに相手の心を惑わせ、悪事を働かせる様子を表現した言葉です。
例えば、友人に対して間違った情報を与えて、その友人が困ったりトラブルに巻き込まれるよう仕向ける場合などに使われます。
また、政治やビジネスの世界では、敵対者や競合他社を欺いて自分の利益を追求する行為にも用いられます。
「唆す」の読み方はなんと読む?
「唆す」という言葉は、「そそす」と読みます。
日本語の読み方は「そそす」となりますが、漢字の「唆」は他にも「サ」という読み方もあります。
しかし、一般的には「そそす」と読むことが多く、この読み方が一般的とされています。
「唆す」という言葉の使い方や例文を解説!
「唆す」という言葉は、他人を誘導して悪い行為や思考に導くことを表現する際に使用されます。
例えば、「彼女に対して嘘の情報を教えて、他の人との関係を悪化させようと唆すなんて最低だ!」というような使い方があります。
また、「彼の発言が人々を唆して、混乱を引き起こしてしまった」というように、マスメディアや政治家の行動が他人の意思や行動に影響を与える状況でも使われることがあります。
「唆す」という言葉の成り立ちや由来について解説
「唆す」という言葉は、漢字の「唆」と「す」という文字が組み合わさって成り立っています。
漢字の「唆」とは、人を誘惑する、そそのかすという意味です。
また、「す」という部分は、動詞の終止形である「す」という活用形です。
ですので、「唆す」という言葉は、「誘惑する」といった意味を持つ言葉として、日本語に定着したものと考えられます。
「唆す」という言葉の歴史
「唆す」という言葉の歴史は古く、平安時代にまで遡ります。
当時の文献にも「唆す」という表記が見られます。
日本人の間では、昔から他人を惑わせる行為は非常に悪いとされ、重大な罪とされました。
しかし、時代が経つにつれて、社会の変化や人々の考え方によって、「唆す」の概念も変化していきました。
現代では、悪意を持って他人を騙すことや誘導することが問題視される傾向にあります。
「唆す」という言葉についてまとめ
「唆す」という言葉は、他人を欺いて悪い行動や思考に導くことを意味します。
その読み方は「そそす」といいます。
使い方や例文を解説すると、他人の関係を悪化させるために嘘の情報を教える場合や、人々を混乱させるために言葉を使う場合などがあります。
また、「唆す」の成り立ちや由来は、「唆」という漢字が「そそのかす」という意味を持ち、動詞の終止形である「す」と組み合わさっていることから、日本語に定着したものと考えられます。
歴史的には平安時代から存在し、現代では悪意を持った行為として問題視される傾向にあります。