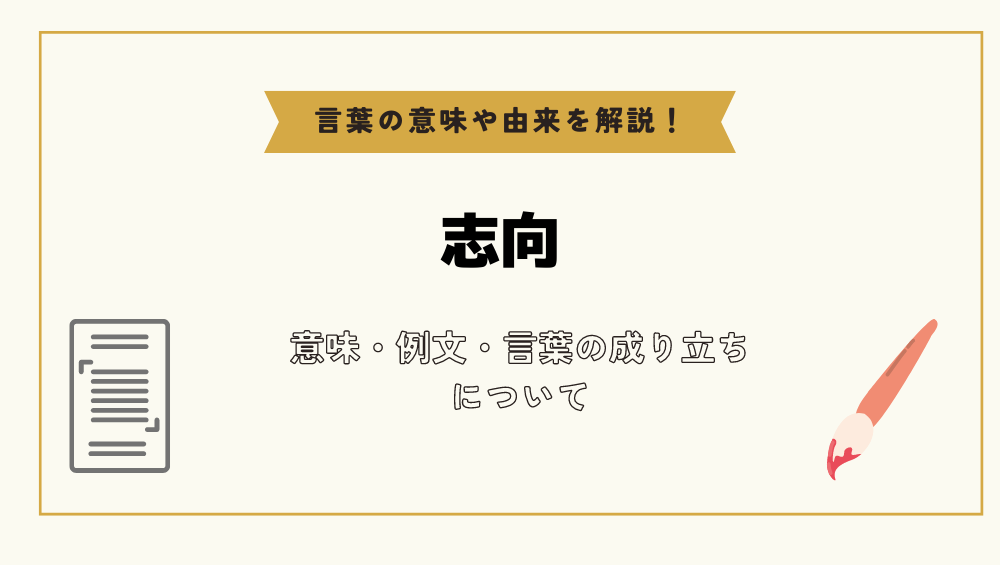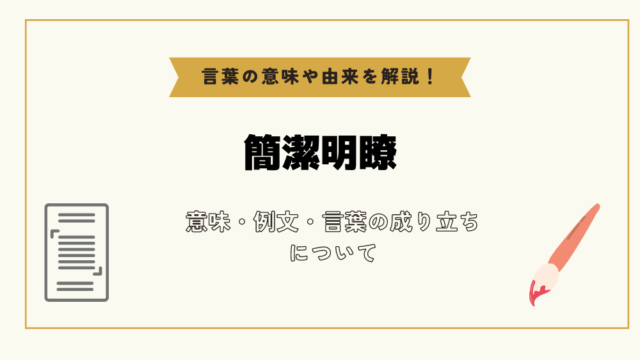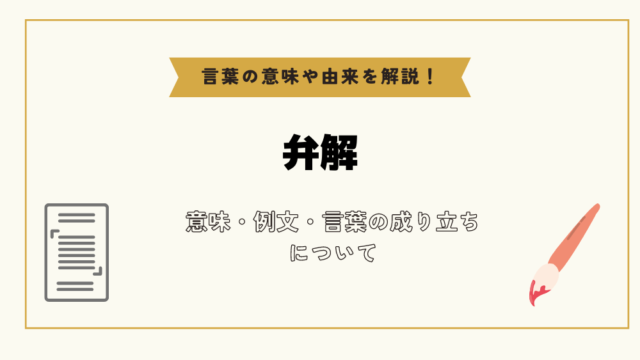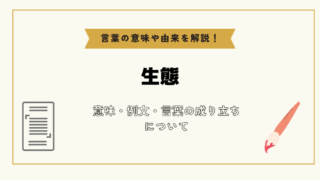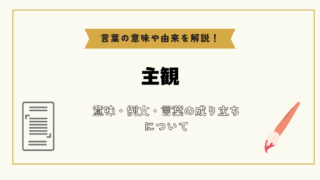「志向」という言葉の意味を解説!
「志向」とは、ある目標や方向へ意識を向けて行動・思考する姿勢を指す言葉です。単に「好き嫌い」や「傾向」を示す場合もありますが、根底には「こうありたい」「こうなりたい」という主体的な意図が存在します。心理学や哲学の分野では、目的指向性(goal–orientedness)を表す概念としてもしばしば用いられます。
ビジネス文脈では「顧客志向」「成果志向」のように、組織や個人が優先すべき価値基準を示すときに登場します。教育現場でも「主体的・対話的で深い学び」を支えるキーワードとして「学習者志向」が語られます。
重要なのは、「志向」は外部からの強制ではなく内発的動機づけに基づく点です。したがって同じ行動でも、志向の有無で学びの深さや成果の質が変わります。
近年ではキャリア形成において「ライフ志向」「ワークライフバランス志向」という言い回しが浸透しています。これは「仕事か、生活か」という二項対立ではなく、どちらにも価値を置く意識変化を示しています。
「志向」の読み方はなんと読む?
「志向」は一般に「しこう」と読みますが、同じ漢字を使った「指向(しこう)」と混同されがちです。「志」は“こころざし”を意味し、理想や信念に向かう気持ちを表します。一方「指」は“ゆびさす”で、物理的・具体的な方向を示します。
したがって「志向」は精神的・価値的な向きを示し、「指向」は技術的・物理的な向きを示すという使い分けが基本です。例えば「音が一方向に指向するスピーカー」は「志向」でなく「指向」です。
なお「志向性」という語はドイツ語Intentionalitätの訳語として哲学書に登場しますが、こちらも読みは「しこうせい」で変わりません。
ルビを付ける場合は「志向(しこう)」とひらがな表記を添えるのが一般的で、学術論文では初出時のみルビを付すのが慣例です。
「志向」という言葉の使い方や例文を解説!
実際の文章での使い方は、対象となる価値やゴールを修飾語として置く形がもっとも自然です。「顧客」「成果」「成長」「安全」など具体的な語を前に置くことで、志向の方向性が明確になります。
修飾語+志向の語順により、「何を大切にしているのか」を一語で示せるため、ビジネス文章で特に重宝されています。同時に、個人の価値観を語るときにも柔軟に利用できるのが利点です。
【例文1】「当社は顧客志向を徹底し、長期的な信頼関係を構築している」
【例文2】「彼女は成長志向が強く、新しい技術を貪欲に学び続けている」
注意点として、「志向が強い/弱い」の表現は比較的曖昧です。客観性を持たせるには、具体的な行動例を併記するか数値データを示すことが望ましいでしょう。
「志向」という言葉の成り立ちや由来について解説
「志」は甲骨文字に遡る古い字形で、心臓を象った「心」と行先を示す「之(いく)」の組み合わせです。それが「志」に“こころざし”の意味を与えました。「向」は口とさじきを描いた象形文字で、前方へ顔を向ける様子が語源とされます。
漢字圏で「志向」が組み合わさった用例は中国の古典には少なく、日本で独自に概念化が進んだと言われています。明治期に西洋の哲学・心理学用語を翻訳する過程で、「intention」や「orientation」などの語を置き換えるため採用され定着しました。
日本語においてはすでに江戸末期の儒学者の書簡に「志向」の語が見られるものの、一般化したのは近代以降です。学術用語として輸入されたのち、昭和期の経営学や教育学で広く使われ、現在の多分野的な用法へと展開しました。
漢字そのものの由来を踏まえると、「志向」は“心を向ける”という直訳的な成り立ちであり、語意が直感的に理解しやすいことが普及を後押ししたと考えられます。
「志向」という言葉の歴史
古代中国の書物では「志」と「向」は独立して用いられ、同一語としての結合例は多くありません。奈良時代の万葉集にも「志向」の熟語は見られず、代わりに「志許(しこ)」が音写語として出現しますが、意味は異なります。
明治維新後、西欧近代思想が流入すると「志向性(intentionality)」が哲学訳語として登場しました。エドムント・フッサールの著作を翻訳した九鬼周造や木田元らが普及させたことで、哲学領域での定着が加速します。
昭和30年代にはドラッカーの経営理論が紹介され、企業の「顧客志向」や「成果志向」が経営戦略の標語として広まりました。同時期、教育心理学では「動機づけ」「目標志向理論」が取り入れられ、日本語論文でも頻用されるようになります。
平成以降はIT業界で「ユーザー志向」「モバイル志向」などの語が次々に生まれ、SNSの普及に伴い個人の価値観を示すハッシュタグとしても使用されるなど、歴史的に見ても適用範囲が拡大しています。
「志向」の類語・同義語・言い換え表現
「志向」と似た意味をもつ語には「志向性」「志望」「意向」「指向」「嗜好」「傾向」「オリエンテーション」などがあります。それぞれニュアンスや利用シーンが異なるため正しく使い分けることが大切です。
最も近いのは「意向」で、“その人の意思がどちらに向いているか”を示す場面で置き換えられますが、意向は行動の伴わない意図だけを指す点で異なります。一方「嗜好」は“好み”を示し、内的な好悪を表すため、外向きの目的意識を含む「志向」とは区別されます。
【例文1】「コスト削減志向」→「コスト意識」
【例文2】「健康志向」→「ヘルスコンシャス」
また、組織行動論では「オリエンテーション(orientation)」がほぼ同義語として扱われ、「マーケットオリエンテーション=市場志向」と翻訳されます。文脈や専門性に応じて、和訳かカタカナ語かを選択すると良いでしょう。
「志向」の対義語・反対語
「志向」は“ある方向へ向かう”概念なので、反対語は“方向を持たない”か“逆方向へ向かう”表現となります。一般的には「無目的」「漫然」「拡散」「願望希薄」「志向性の欠如」などが該当します。
ビジネスや教育の領域では「受動的」「消極的」「反応的(reactive)」が「主体的・能動的」=志向的の反意として用いられることが多いです。
【例文1】「成果志向」に対して「過程重視」は相反する価値観。
【例文2】「顧客志向」に対して「製品志向」は往々にして競合する戦略。
なお、「志向」と「指向」の対比で反対語を構成するケースも見られますが、これは語源が異なるため厳密には対義関係とは言えません。
「志向」を日常生活で活用する方法
「志向」はビジネス用語のイメージが強いですが、日常生活でもセルフマネジメントのキーワードとして活躍します。家計管理なら「貯蓄志向」、食生活なら「減塩志向」、趣味なら「アウトドア志向」など、自分の価値観を言語化するツールになります。
言語化によって目標を明文化すると行動が選択しやすくなり、習慣化のハードルを下げられます。例えば「早起き志向」を宣言し、カレンダーにチェックを入れるだけで行動実行率が向上したという研究報告もあります。
【例文1】「今年はエコ志向を高め、マイボトルを持ち歩く」
【例文2】「家族全員で健康志向のメニューを考案する」
注意点として、志向を掲げすぎると“〜でなければならない”という義務感が強まり逆効果になる場合があります。小さな達成を積み重ねて自己効力感を高めることが継続のコツです。
「志向」についてよくある誤解と正しい理解
まず「志向=嗜好」と思い込む誤解があります。嗜好は“好き嫌い”を示す個人的な感覚であり、必ずしも行動に結びつきません。一方、志向は価値観に根差した行動指針を含みます。
次に、「志向が強い=頑固で柔軟性がない」という誤解が挙げられますが、本来の志向は“目標への集中”であり、方法論に柔軟であるほど達成可能性が高まるとされます。
【例文1】「ベジタリアン志向だから肉料理を避ける」→嗜好の要素も含むが、健康や倫理が動機なら志向としても成立。
【例文2】「成果志向だから長時間労働する」→成果と長時間労働は直結しないため、方法と目的の混同に注意。
さらに「志向=結果主義」と短絡するのも誤解です。プロセス志向と成果志向は対立ではなく補完関係にあり、目的と手段を適切に見極めることが望まれます。
「志向」という言葉についてまとめ
- 「志向」とは、目標や価値に心を向け主体的に行動する姿勢を示す言葉。
- 読み方は「しこう」で、同形の「指向」と区別する必要がある。
- 明治期に西洋語を翻訳する中で定着し、哲学・経営など多分野で発展した。
- 現代ではビジネスから日常生活まで幅広く使われるが、嗜好との混同に注意。
志向という言葉は“心を向ける”というシンプルな構造から生まれましたが、その射程は想像以上に広く、自己啓発・組織論・社会課題の解決などあらゆる局面で活用されています。自分や組織が「何を大切にしたいのか」を明らかにする羅針盤として、志向を意識的に言語化することは大きな意味を持ちます。
一方で、志向を掲げるだけでは成果は得られません。行動へ落とし込み、柔軟に方法を更新し続けることでこそ、その志向は真価を発揮します。この記事が自身の価値観を見つめ直し、次の一歩を踏み出す手助けとなれば幸いです。