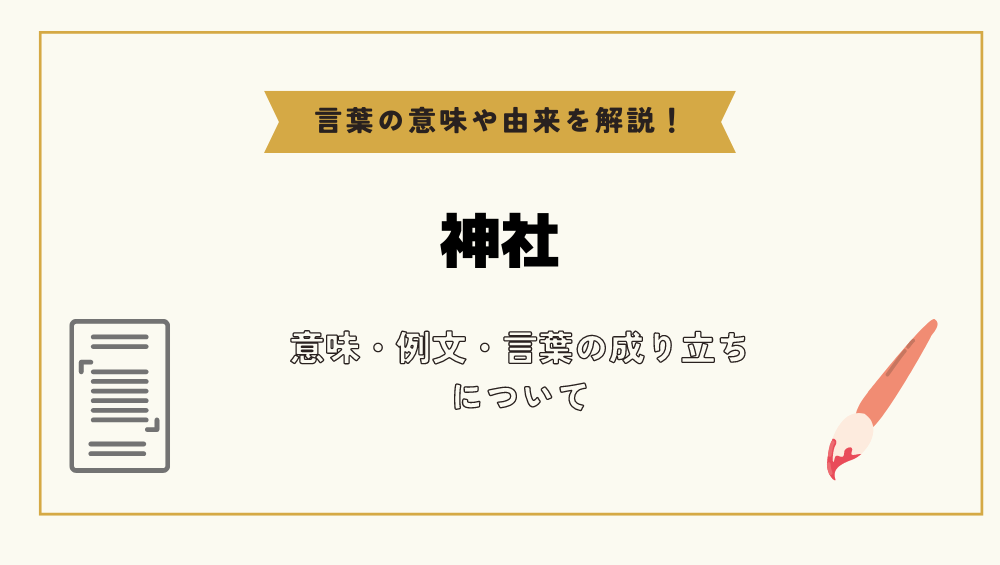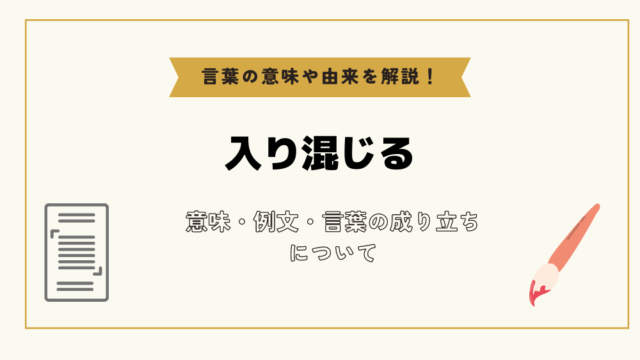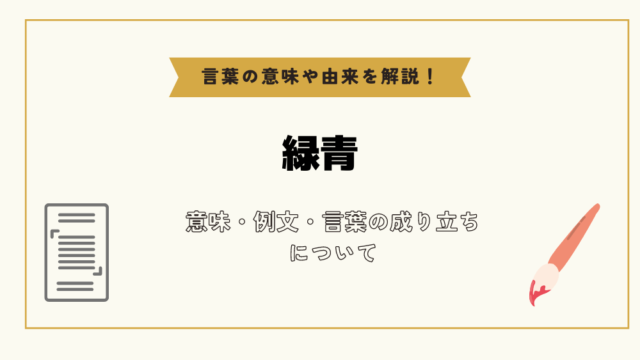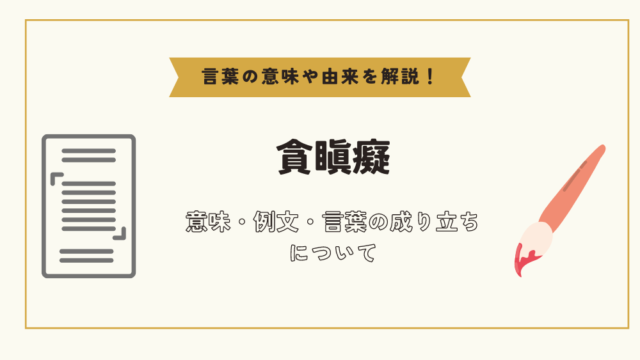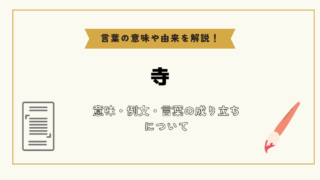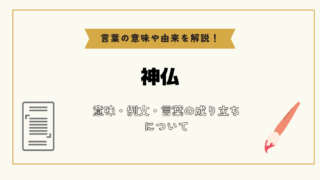Contents
「神社」という言葉の意味を解説!
「神社」という言葉は、日本の伝統的な宗教施設を指す言葉です。
「神」とは、人々が奉る信仰の対象であり、日本の神道の主な信仰対象でもあります。
そして、「社」とは、神を祀る場所や建物のことを指します。
このように、「神社」とは、神を祀るための建物や場所のことを意味します。
「神社」という言葉の読み方はなんと読む?
「神社」という言葉は、日本語の一般的な読み方である「じんじゃ」と読みます。
「しんじゃ」とも表記されることもありますが、一般的な読み方は「じんじゃ」となります。
なお、外国人の方にとっては発音が難しいと感じるかもしれませんが、慣れていない方が発音する際は、音をゆっくりとはっきりと出すようにしましょう。
「神社」という言葉の使い方や例文を解説!
「神社」という言葉は、主に日本の宗教や伝統文化に関連する文脈で使われます。
例えば、「神社に参拝する」という表現が一般的です。
また、「神社で祭りが行われる」といった風景や、「神社には多くの人々が訪れる」といった状況もよく見られます。
さらに、神社の名前を具体的に挙げる場合には、「醍醐宮」とか「伏見稲荷大社」などと言及します。
「神社」という言葉の成り立ちや由来について解説
「神社」という言葉の成り立ちや由来については、古代日本の信仰や宗教の歴史に深く関わっています。
神道の考え方に基づく神社が広まったとされており、古代の王権や地域の信仰に関連する神社が建立されていきました。
また、神社は地域の人々の信仰の拠点としての役割も果たしており、祭りや行事が行われるなど、地域の結束を深める場としても機能しています。
「神社」という言葉の歴史
「神社」という言葉の歴史は、古代から続いています。
古代日本においては、神聖な場所や神々を祀る風習は非常に根強く、宗教的な意味合いも持っていました。
時代が進むと、神社の形態や信仰のスタイルも変化しましたが、現在でも様々な地域に神社が存在しています。
神社は、日本の伝統や文化を象徴する場所として、多くの人々に愛されています。
「神社」という言葉についてまとめ
「神社」という言葉は、日本の宗教や伝統文化に欠かせない存在です。
その意味や読み方、使い方や歴史について解説しました。
「神社」は、神を祀るための建物や場所を指し、日本の神道信仰の中で重要な役割を果たしています。
多くの人々が参拝や行事を通じて神社に訪れ、日本の伝統と文化を感じることができます。